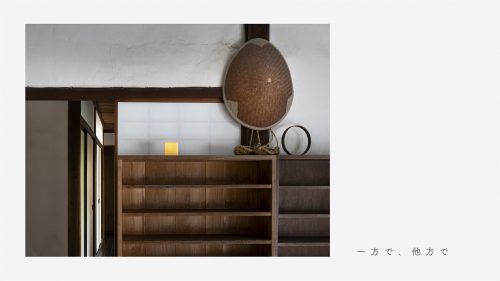生活の中に存在する苦しみの構造に目を向け、自分を守ることの重要性を訴えたイ・ミンギョン著『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』。本書のことばが韓国国内のみならず日本でも多くの読者をエンパワーしている現状から、人々がいかに自分たちのことばを求めているかその切実さが見て取れる。近年では邦訳化がすすみ、本書や『82年生まれ、キム・ジヨン』など、社会に参加し人々にことばを与える作品が殊更に注目を集める韓国文学。今回は、本書の共訳など韓国文学の翻訳を多く手がけてきたすんみ、小山内園子に翻訳家の立場からみた韓国文学が持つことばの力について話してもらった。
――お二人で本書を共訳することとなったのは、どのような背景があったからですか?
小山内「私たちはもともと翻訳仲間で、色々なことを相談しあう仲なんですね。だから以前私が別の仕事で韓国の女性団体に行っていたことも話していました。支援の現場にいると、日韓のフェミニズムのギャップを感じると。それを覚えていてくださったすんみさんが共訳のお声がけをしてくれて、という経緯がありました」
――お二人は本書をお読みになってどんな感想を抱かれましたか?
すんみ「女性たちはこれまで、自分たちの観点で発言できる機会が少なかったと思うんです。男性中心に作られた仕組みの中で作られた観点からでしか物事を見ることができなかった。しかし、江南駅殺人事件がきっかけでいろいろな変化が起こりました。女性たちに新しい意識、新しい気持ちが芽生えたのです。だが、それが何なのかを自分で消化することができない。そんな時に出た本書は、頭の中を整理させてくれる本だと思いました。 マニュアル本を謳いながら、本の半分以上を、女性たちが置かれている状況をかみ砕いて説明することに割いています。いままで当たり前すぎて見えてなかった男性中心の仕組みを、目の前に鮮明に浮かび上がらせてくれる。自分の現在地を教えてくれるような本です」
小山内「この本は、読者の気持ちをまず受け止めることに大体のページを割いていると思うんです。まるで赤ちゃんの背中をぽんぽんと優しくたたくように。そして“それはこう考えればいいんだよ”と伝えてくれる。最初に読んだとき、すぐに対話マニュアルが載っているのではなく、そこから始めることに驚きました。”セクハラされたらこう返そう”ではなく、議論を吹っかけられたり相手の意見を押しつけられそうになったらこう返そうと。対処療法的でない対話集ですよね。気持ちのどこかで諦めていたなにかを起き上がらせ、元気づけてくれる本、というのが原書を読んでの印象でした。翻訳中にいろいろな国のフェミニズムの翻訳書も読みましたが、この本の”気持ちを一度受け止めたうえで、どう対応していくべきか一緒に考える”という段取りをふまえたアプローチは、すごく東アジア的だなと。ちょうど翻訳に取り掛かった時期に、日本でも財務省の事務次官がテレビ局の記者にセクハラ行為をはたらいた出来事など、様々なイシューが起こっていたので、訳しながら個人的にもさまざまなことを振り返り、考えさせられました」
すんみ「渡部直己という、私が大学院に通っていたときの教授がセクハラをしていたことが発覚した事件もありました(2018年6月、元早稲田大学院生の女性が渡部からセクハラおよびパワハラ被害を受けたとして早大側に被害を申し立てた。女性は同年春に退学をしていた)。ちょうどその頃、この本の”大学院の研究室で教授にセクハラを受ければ、学生のほうが学校をやめることにな”るという箇所を訳していたので、複雑な気持ちになりました。特にTwitterに渡部さんの知り合いが渡部さんの著書や授業をほめるようなつぶやきがあるのを見て耐えられなかったですね。それで、周りの人たちが彼の業績や個人的な思い出とこの一件を取り違えて二次被害を生まないでほしいとTwitterでつぶやきました。その後わたしのツイートを見た方々からDMをいただいたのですが、なかにはまさにこの本に書いてあるような被害や差別経験についてのものもありました。そういう体験をしたのに、周りからなかなか共感が得られなくて疲れているということが伝わってきたんですね。心が痛んだし、なんとか自分の心をまもってほしいなと強く思いました。著者のミンギョンさんは、この本を心を守るための”護心術”の本と言っています。そのためのさまざまな方法を提示しているわけです。例えば、”話の流れを変える”対話術。話の流れを変えて自分が有利な立場に立って対話できるようになれば、もう少し自分の意見が言いやすくなるのです。あと、聞く耳を持たない相手とは話さない、という方法もあります。少し極端に思えるかもしれませんが、私自身も自分の心を守るためにはこういった断固とした態度を取る必要もあるんだということに、この本を読んで初めて気付くことができました。まずは私にDMを送ってくれた方々にぜひ読んでもらいたいと思いつつ、頑張って訳しました」
――本書の翻訳にあたり、言葉のニュアンスなどで意識した点はどんなところがありますか?
小山内「この本には多くの対話が描かれているので、どう訳せばリアリティのある会話になるかと悩みました。男性が女性に呼びかける言葉の場合、”君”なのか”お前”なのか”てめえ”なのか、またカタカナなのかひらがななのか、原文の雰囲気は伝わり、日本の読者にもリアリティがある言い回しを見つけたかったんです。それで“実際にそういう言葉はどのように使われているんだろう”とSNSなどで検索して、議論を吹っかけたり絡んでいる男性たちの話法を調べて。特に人称や語尾に注意しながら、生活で使われる言葉を集めました。また、女性の発言で意識的な女言葉は使わないよう注意していました。事前にすんみさんと打ち合わせしたわけでもないのに、訳文をみたらお互いそうなっていて(笑) 共通の認識としてあったんですね。”~なのよ”や”~かしら”といった言葉遣いは用いず、できるだけニュートラルな言葉に訳しました。文章にすると誰が男性で誰が女性か区別しづらいという理由で、あえて女言葉に翻訳するケースもありますが、この本を手に取る方は、女性について女性が書いた本だとわかっているだろうと」
すんみ「そうですね。本書にも書いてあるように女性差別って男性だけがするものではないので、そういう視点をもって翻訳したいという気持ちもありました」
小山内「あと、著者のミンギョンさんやこの本の出版チームの皆さんの”この本を読んで学んでね”というよりは”一緒に連帯しましょう”という姿勢が読者に伝わるような表現という点にも気を配りましたね」
すんみ「以前小山内さんが訳された『ぼのぼのみたいに生きられたらいいのに』(キム・シンフェ著、竹書房)の中に”連帯”という言葉が出てきましたよね。翻訳に取り掛かられていたとき、小山内さんはその言葉をそのまま”連帯”と訳すべきか否か悩んでいらっしゃったなと思いだしました」
小山内「そうなんです。エッセイ集で、何も連帯って政治の話だけでなく、気の合った者どうしで一緒に暮らすのも連帯だよね、と語る場面があるんです。翻訳中はどうも”連帯”という言葉が日本ではピンとこない気がして、言い換えも含めすんみさんに相談しました。”助け合い””分かち合い””絆”といった言葉を使うべきかな、とか話して。でも結局、“連帯は連帯だ!(笑)”とそのまま訳したんですが。今は普通に”連帯”という言葉が使われていますよね」
すんみ「ここ一年で日本でも状況がかなり変化してきていることをこの”連帯”という言葉を通して感じます」
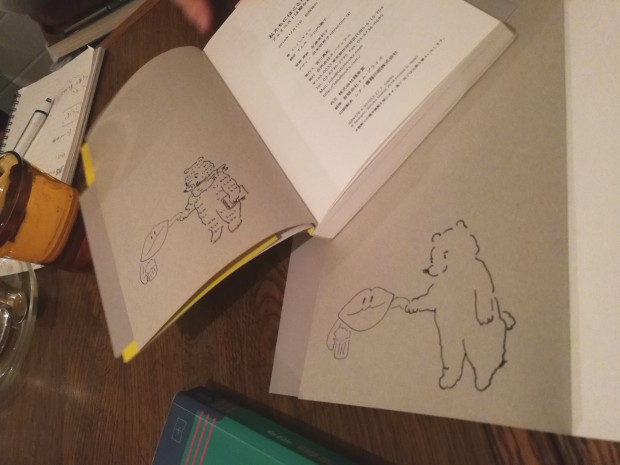
――以前すんみさんは”新しい言葉で自分の日常をつかんでみたい”とおっしゃられていましたが、今まで私たちが使ってこなかった表現が登場するという点も韓国文学を読んでいて楽しい点だなと感じます。
すんみ「いま韓国ではさまざまな価値観が変化し始めています。家族、結婚といった普遍的に思えていた価値観までも揺らぎ始めている。何かが新しく生まれようとしているのだけど、新しいものなので、いままでの言葉では表しきれないわけです。『あまりにも真昼の恋愛』(キム・グミ著、晶文社)という韓国文学を訳していたとき、そんなことを思いました。ここでは既存の社会からはみ出ている人が描かれていて、だからこそ既存の表現では彼らを描き切ることができない。何か新しい現象を目の当たりにしたときその状況を表現しようとするのは、目をつぶって何かを探っているという感覚に近いと思います。『あまりにも真昼の恋愛』の中には”活動する物体の運動感”という独特な表現があって、最初はそのまま日本語に訳せば拙い日本語になってしまうのではないかと懸念して”生き生きする躍動感”などいろんな訳を考えたのですが、やっぱりしっくりこないものがあって。この言葉はこのまま訳した方が、自分の力で何かを新しくつかもうとしている感じが伝わると思いなおしました。江南駅殺人事件もそうですが、日常において知覚の転換があったとき、人は今までの言葉ではなく新しい言葉を必要とするのではないかと思います」
小山内「やはり国が違えば様々な局面での感覚的な違いが生まれる。それが私たちにとって新しい見え方に映る場合もあると思います。例えば、会話において“どこまで言葉にするか”という判断面の違い。日本だったら頭の中だけに閉じ込められている思いが、たとえば韓国の小説やドラマでは”私はこう思う!”とストレートに会話で表現されていることが多いし、その判断が早い。だからこそ、気持ちの通い合い方がより濃いものになっていると思います。新しい見方を得られることは外国文学のたのしみのひとつですが、特に韓国の場合、同じ東アジアのよく似た場面で、全く別のアプローチを知ることができる気がします。ひっ迫した状況が日本社会と韓国社会で共通しているものがあるぶん。今いちばん手が届きやすく、言葉にならないものを言葉にしている外国文学は、韓国文学なのだろうと思います」
――行動におこすまでのはやさは、ミンギョンさんが江南駅殺人事件を受けたった1か月ほどで本書の制作を終えられたことからも見て取れます。
すんみ「韓国では何か事件が起きると、それに関する本がすぐに出るのですが、情報を確かめる時間をとれなかったりで、内容に間違いがあることがわりと多いんです。それは、小さな間違いを気にするよりは早くみんなと共有したい、一緒に考えたいという気持ちの方が大きいからだと思います。間違っている部分は後から正せばいいですから」
小山内「出すべきときに出さないと意味がなくなってしまう、という感覚があるのだと思います。些細な間違いはいいからしっかり主張しよう、という姿勢ですね」
――本特集で韓国文学作家のみなさんからお話をおうかがいしてきましたが、「言葉によって何かを変える」という意識が共通していると感じました。
すんみ「韓国は、日帝時代、朝鮮戦争、軍事独裁政権時代、高度経済成長など激動の時代を過ごしてきました。そういう歴史の中で、韓国文学は”参与文学”という、文学者が作品を通じて社会にコミットする文学がずっとありました。そしてそのような文学の影響力は、かなり大きかった。文学によって人々の意識が変わったり、社会が動く経験を何度もしていて、その経験を人々が内面化したことが大きいんですよね。ですので、現代の作家たちも文学が社会を良くする力を秘めているという認識を持っていると思います。また、いま大衆が何を求めているかにとても敏感に反応する作家も多いです。文学のために文学をやっている人が少ないんですよね」
小山内「”変えられるし、変えなければ”と考える。言葉にする前に言っていいかどうかとためらう私達とは、そこが一番大きく違うのだと思います」
――本書でイ・ミンギョンさんが”よりはっきりした根拠を探しているあいだに、学問的なポジションを築いているあいだに、あなたの声はかき消されてしまうかもしれない。その前にたとえ不完全な姿でも、一度あなたと出会いたいと考えたのでした”と語られていた箇所からも、その切実な姿勢がうかがえます。
小山内「その切実さは、翻訳中に身をもって体験しました。本書内で何度も言及される“江南駅殺人事件”の現場の江南駅10番出口について、ある日ふと、”ここに行ってもいないのに訳すってのはどんなもんだろう”と思ってしまったんです。それで韓国に行き、江南駅10番出口にでかけました。出口に貼られていた被害者追悼のポストイットはすでに別な場所に移されていて、殺人事件の現場として訪れている人間も私以外誰もいない様子でした。行けばすぐわかるだろうと高をくくっていたのですが、いくら10番出口の周りをうろうろしてもそれらしい建物はない。仕方なく道行く人に尋ねてみると、みんな関わらないように無視していくんですね。それで、あれれ?って。せっかくだから、事件が今どう意識されているか知るために、男女それぞれ20人ぐらいに片っ端から聞いてまわりました。”事件を知っていますか? 現場を知っていますか”と。不思議なことに、男女で全く異なる反応だったんです。女性は江南駅殺人事件のことだと察した瞬間、顔を背けて立ち去る。一方男性はのどかなもので”そんなことあったっけ?””いつのこと?”と逆に尋ねてくる。そうやってようやく辿り着いた現場は、10番出口からけっこう離れた雑居ビルでした。カラオケ店は今も運営していました。ちょうど通りがかった女子大生の二人組に”あのカラオケ行ってます?”ときいたら”事件は知ってるけど、今でもふつうに使っていますよ”と。怖くないの?ときいたら”だってもう終わったことだから”と言う。なんだか消化しきれない気持ちのまま、帰りにトッポギの屋台でトッポギを立ち食いして、そこでおばちゃんに顛末を話しました。そしたらおばちゃんは、それまでとってもにこやかだったのに、急に厳しい表情で”だってね、日本でもアメリカでも毎日たくさんの人死んでるでしょ? そういうのは忘れた方がいいよ。あたしの母さんだって祖母さんだって、もっと大変だったんだから。家事もして、子供も育てて、畑もやって。今の女はきれいな服着て仕事して、それだけでもありがたいと思わなきゃ”と。そのときはじめて、ミンギョンさんがこの本を書かずにいられなかった理由がわかった気がしました。放っておくと、こんなふうにどんどん、なにも無かったようにされて被害者個人の話で終わってしまう。だからこそ、こうして声を上げて、本として言葉を残したんだ、と。それは、現場に行ってみないと分からないことだったし”今書かなければ”という切迫した思いを追体験できた。だからこそ、受け取る側が彼らの切実な思いに対してなにを感じるか、どう考えて行動していくかがとても大事なんだと思います」
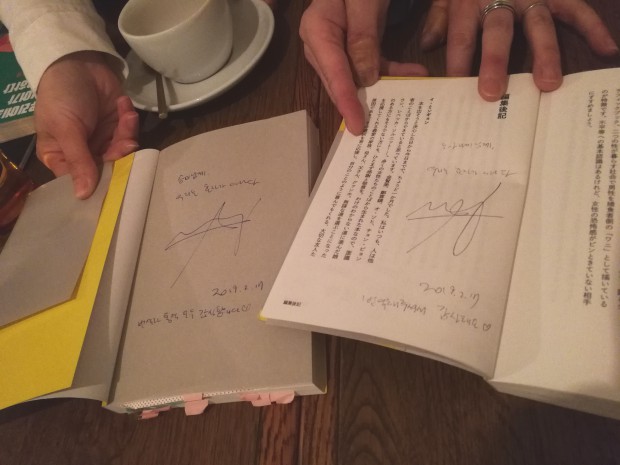
text by Shiki Sugawara
すんみ
早稲田大学大学院文学研究科修了。訳書に、キム・グミ『あまりにも真昼の恋愛』(晶文社)、リュ・ジョンフン他『北朝鮮 おどろきの大転換』(共訳、河出書房新社)など。
小山内園子
東北大学教育学部卒業。社会福祉士。2007年、社会福祉士として派遣された韓国「ソウル女性の電話」にて、差別や暴力被害に苦しむ韓国の女性たちの現状を知る。訳書に、姜仁淑『韓国の自然主義文学 ―― 韓日仏の比較研究から』(クオン)、キム・シンフェ『ぼのぼのみたいに生きられたらいいのに』(竹書房)、リュ・ジョンフン他『北朝鮮 おどろきの大転換』(共訳、河出書房新社)、チョン・ソンテ『遠足』(クオン)など。
『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』
イ・ミンギョン 訳 すんみ・小山内園子(タバブックス)

購入はこちら