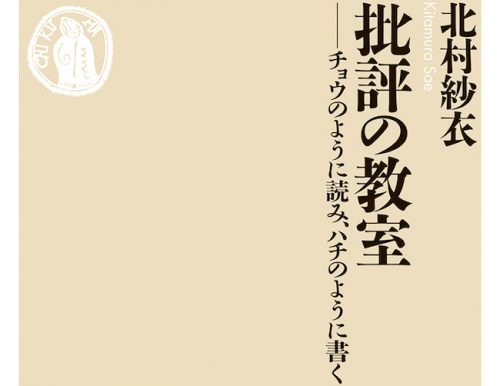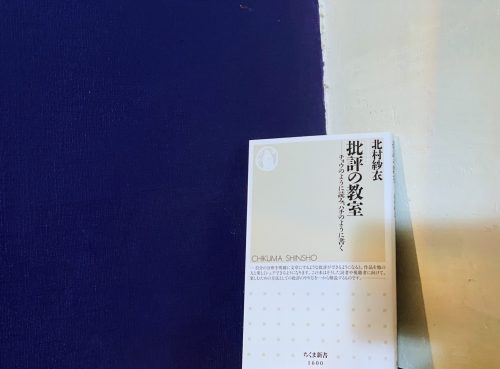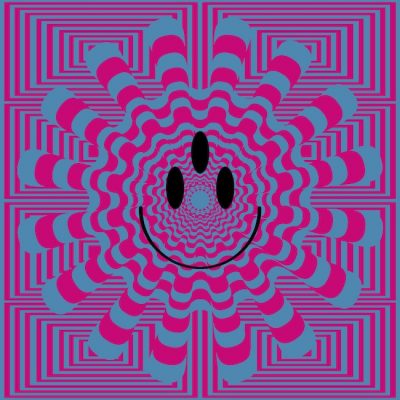2019年5月14日に可決成立した米アラバマ州の中絶禁止法。その後16州が同法案の制定に向けて動き、1973年の連邦最高裁が下した「ロー対ウェイド」の判決が覆される恐れが出てきた。女性による中絶の権利が保障されない可能性がある未来。次の世代が、私たちの世代より少ない選択肢の中で生きざるをえない可能性。それは日本に暮らす我々にとって決して遠くの出来事ではなく、そうした未来が我々にも存在するかもしれないという警鐘である。
『Our Body Issue』ではこの警鐘に対し、様々な側面からまずは自分の身体について知り、ひいてはその身体を愛すること、選択肢を持つことの大切さを考えるきっかけを作りたい。
ここでは社会での個のあり方やジェンダーロールについて新たな視点を与え、解き放ってくれるような5冊の本を紹介する。
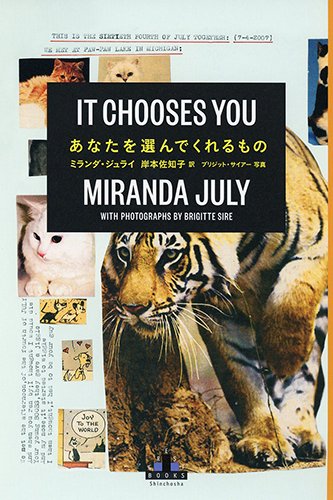
『あなたを選んでくれるもの』
ミランダ・ジュライ
2009年夏、ミランダ・ジュライは自身が監督・脚本・主演をつとめカンヌ国際映画祭でカメラドールを受賞した長編デビュー作『君とボクの虹色の世界』の次作である『the Future』の脚本制作に取り掛かっていたが、完成まであと一歩というところで執筆に行き詰まってしまいネットサーフィンで現実逃避を始めしまう。「べつに仕事から逃げているわけじゃない。これは取材なのよ」と自分に言い聞かせながら。そんな彼女にとってもう一つの気晴らしは毎週火曜に届く“ペニーセイバー”と呼ばれる小冊子を熟読することで、そこにあるLA市民が各々の不用品を売買するための広告欄を眺めながら、ジュライは胸中にそれぞれの品物の後ろに隠れる売り手自身の物語に対する好奇心が育っていくのを発見する。一日中youtubeのリンクをクリックしている彼女にとって、クラシファイド(広告を掲載することの出来るネット掲示板)を使わずペニーセイバーに電話番号を載せる手段をとる人々は何よりもフィクショナルに映ったのであろう、「彼らの物語に脚本の答えが隠れているはず」と取材を敢行する。しかしそこに載ってある電話番号の先の、玄関の扉を開けてくれる人々はジュライの予想に反しあまりにリアルな存在だった。60代後半の革ジャンを売るトランスジェンダーのマイケル、赤の他人のアルバムを買って自己投影するギリシャ移民の主婦パム、自宅の庭に池を自作しウシガエルのおたまじゃくしを育てては売る男子高校生アンドルー……本書は、ジュライが藁をもつかむ思いでペニーセイバーを通じ出会った12人の取材を経て『the Future』の製作を追えるまでの物語で構成されている。
『あなたを選んでくれるもの』で特筆すべきはタイトルのままに、本書に登場する12人がジュライに手を差し伸べている点である。彼女は冊子にある電話番号に片っ端から電話をかけていくが、そのほとんどの人から取材を断られる。それもそのはず、彼らがペニーセイバーに電話番号を掲載した目的は不用品を売ることであり、見知らぬ訪問者に自分の物語を語ることではないのだ。しかしジュライの取材を受け入れた奇特な12人は、まるでずっと誰かに尋ねられることを待っていたかのようにその全てをさらけ出す。
取材を行っていくうち、ぺニーセイバーの人々の話に比べて自分の脚本はなんとつまらないものかと感じ絶望したと言うジュライは「彼の人生はあまりに強烈で、あまりに並外れて重く、あらゆるフィクションを超越していた」と綴る。本書に登場する12篇の物語は、youtubeの“関連動画”やAmazonの“おすすめ商品”のようなアルゴリズムによって提供される心地の良い情報ではなく、知りたくなかったとさえ思えるほどに彼女の心に爪痕を残した。だが皮肉にもジュライを絶望させた、フィクションを超越する現実のエネルギーこそアーティスト ミランダ・ジュライ自身がこれまでくりかえし追求してきたテーマ「見知らぬ人同士のつながり」の本質として浮かび上がり、彼女にヒントを与える。求める情報のみで構成された世界で自慰的に生きるような“選ぶ”ばかりの時代に埋もれていた彼女が、他者に“選ばれる”ことで予想外のインスピレーションを得て『the Future』完成の糸を手繰り寄せるのだ。一人のアーティストがフィクションを求めた末にむせ返るほどの現実のにおいと対峙し、戸惑いながらも生みの苦しみを脱するまでを描く本書は、いま何かに行き詰りを感じている全ての人にひとつの希望を抱かせる。
Amazon
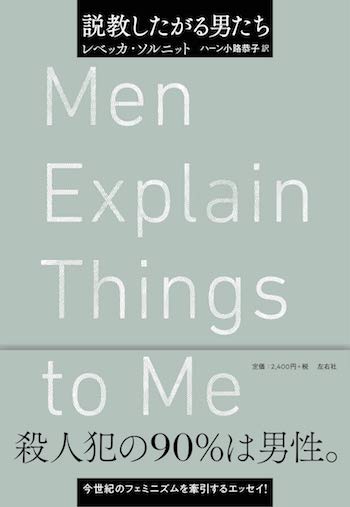
『説教したがる男たち』
レベッカ・ソルニット
“マンスプレイニング(Mansplaining)”は本書の著者レベッカ・ソルニットによる造語で、男性を意味する“man”と説明するという意味の“explain”を掛け合わせたかばん語である。この言葉が意味するところを説明するさい、ソルニットはパーティーで出会ったある男性の逸話を紹介している。「本を何冊か出しているんだよね?」と尋ねる彼に、彼女はエドワード・マイブリッジを最新作のテーマにしていると答えた。すると彼は「マイブリッジについて書かれたすごく重要な本を知ってるかね?」と言い、その本の著者本人であるソルニットの前で得意げに解説を披露した、というものだ。
先日、日本でもこんなツイートが注目を集めた。書物の公共圏についてTwitter上で議論を展開した女性編集者に対し某男性編集者が自論で反論した上に「そんなこともわからないんだったら、出版やめて、クッキーでも焼いてフリマで売ってろ」と発言したのだ。彼の意図したところは見当もつかないが、編集業は男性特有の職業でクッキー作りは女性の職業という見地であれ編集業がクッキー作りよりも格上だという見地であれ、性差別とも職業差別ともとれる大変稚拙で幼稚な偏見が見て取れるつぶやきであったことは確かである。本ツイートが多方面から非難の声が上がり炎上したのを受け、彼がこの女性編集者のアカウントをブロックして議論を一歩的に終えた一連の流れはまさにマンスプレイニングのWikipedeiaページに一例として掲載できるほど典型的な事例だろう。
説教したがる男たち、すなわちマンスプレイニングが発生する状況は「男性は女性よりも知識が豊富である」といった無意識下の性差別が前提となっており、ソルニットは本書内でマンスプレイニングの原因を社会によって築かれた男性性の内在的な欠陥だといている。
一部の男性は、常に男性という社会的役割をロール・プレイするうえで自信を持ち相手をねじ伏せること(マウンティング)を求められる。「男なら泣くな」「男ならプライドを持て」そんな“男らしさの檻”に子供のころから閉じ込められた男性たちは、その内部に根拠のない自信を育てていく。
しかし、ソルニット自身は「念のためにいっておくと、私の周りにはこんな男ばかりではない」、また「現状に甘んじないことがとても大事だと思うし、今の状況が私の価値や仕事を決めてしまうなんて、あってはならない」と強調する。この主張は男性のマンスプレイニング的な性質は生まれ持ったものではなく後天的なもので、女性が社会的地位の向上を求めて社会に規定された“女性らしさ”の枠を飛び越えようとすることと同じく、男性も“男性らしさの檻”を脱し真の自分の価値や役割を認める行為が重要だということを示唆している。実際、先述のクッキーフリマ発言が波紋を呼んでいた一方で、作家の羽田圭介氏が自著のサイン会に訪れるファンに向けクッキー作りに連日いそしんでいたことも話題となった。「クッキーを作ったとツイートしたら、反応が凄くて。何でこんなに、突然?と思ったら……」と本件を振り返った羽田氏は、男性編集者のツイートを「ダサい」と一蹴するとともに彼との考え方の違いを称賛されたことに「一概にそうとは言えず」と明かし、「フィクションの中でフェミニズム的にダメなことを扱ってはいけない理由を、僕は本当は分かっていない。(中略)ただ幸いにも、僕の感覚は世間とそんなにズレているわけではなかったので炎上はしていないということ」と分析する。しかし、社会的役割と実情を取り違えた揶揄発言を感情的に繰り広げる“説教したがる男たち”と、自身の感覚と世間の感覚を俯瞰して主体的に思考する羽田氏の姿は、同じ時代に社会で生きる身として大きな違いがあることが明確であろう。
「言葉を発し、話をきいてもらい、権利を持ち、社会に参加し(中略)自由な人間として生きられるような空間」をソルニットが本書を通じて求めるように、男女問わず社会に生きる我々一人ひとりが、日常の中でこそ性別の役割を再考し疑問を持って主張していくことが自由の空間への扉を開けるのだ。
Amazon

『バッド・フェミニスト』
ロクサーヌ・ゲイ
恐らく、このタイトルを目にした多くの人の頭には“バッド・フェミニスト”とは何だろうか?という疑問が浮かぶだろう。Bad(悪い)という強い意味を持つ単語をふくむこの言葉こそ著者ロクサーヌ・ゲイの主張をそのままに表している。
日常会話においてセクハラ問題や女性蔑視について話題が及んださい「じゃあ、この言葉はセーフ?あれはアウト?」といった質問が議論にのぼる場面を目にすることがある。しかし彼らが理解すべきなのはセクハラとは常にコミュニケーションの中に発生する問題であり、人間対人間のコミュニケーションとは野球のファウルラインのように区切ることはできないし、「何センチ以下のスカートは履かないように」といった学校の校則のように明瞭な決まりも存在しないということだ。そして、フェミニストの在り方を考える上でこのセオリーを持ち込んだのが、本書内に提唱されるバッド・フェミニストの概念である。
「私の好きな色はピンクです。ファッションマガジンを読んで可愛いものを見るのも好きです」「男性的な仕事なんてまったくやりたくないと思っています。家事も含めてですが、虫を殺したり、ゴミを捨てたり、芝を刈ったり、車のメンテナンスをしたり。一つもやりたくありません」と語る著者ロクサーヌ・ゲイは、現在世界規模で声高に提唱され始めている“女性らしいとされているものを捨て、男性の役割をこなすことで自立する”正しいフェミニストの在り方に自分はそぐわないと綴り、その宣言として バッド・フェミニストを自称する。
近年SNS上ではさかんにフェミニズムについて語られるようになり性差別問題への議論の深まりを見せはじめている。その一方で「フェミニストならばかく在るべき」といった一定の正しいフェミニスト像が確立され、それがフェミニズムのファウルライン(超えてはならない枠)を生成し多くの人々を窮屈にさせているのも事実である。ポップカルチャーと社会批評に造詣の深いロクサーヌ・ゲイは、このポイントに焦点を当てる。例えば、“白馬の王子様を待つ”女性の恋愛を描くロマンチック・コメディが好きな人はフェミニストでいることは不可能なのか?ロクサーヌの答えはノー。デートの時に自立した女性でいるか人任せな恋愛を楽しむかはフェミニストであるか否かとは関係ない。女性蔑視的なポップソングに思わず身体を揺らしてしまう自分にハッと気づき罪悪感を覚えてしまう人々だって、社会的に規範された正しいフェミニスト像からすれば“バッド”ではあっても、フェミニストであることは可能だ。誰に決められたでもない自分なりの“グッドフェミニスト”像を自分の頭で考えることで歩を進めていくことこそが本質的な自立といえるだろう――そんなポジティヴで普遍的なメッセージが込められている。
Amazon

『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち:近世の観劇と読書』
北村紗衣
今でこそイギリス文学の「正典」として著名なシェイクスピア作品だが、16世紀末刊行当時はむしろ教養のない作品という評価が一般であった。イギリス文学の代表格としてシェイクスピアの名を広めさせたのは学者や作家など権威者だけの業績ではない。そこには、名の残らない多くのファンがシェイクスピア作品を愛し、楽しんでいたからである。そして、その中心には芝居を見て考え、ムーヴメントを拡大していった女性たちの存在もあった。本書は舞台芸術史を専門としシェイクスピア作品とフェミニズム批評家である北村紗衣が、批評・研究の学術分野が確立する以前からシェイクスピア作品を考察、研究を重ねていた女性たちの働きに焦点を当て一観客であった彼女たちがいかにしてシェイクスピアの権威確立に貢献したかを解説することで、女性の受容のありようを探求する女性文化史の研究書となっている。
著者によって敢行された膨大な量におよぶ当時の資料の解読によって存在が明らかになったシェイクスピアファンの女性たちは、例えば1769年に行われたシェイクスピア記念祭にて『マクベス』の魔女の仮装を披露したエリザベス・ハーバード、気に入らない国王を「キャリバン」(『テンペスト』に登場する醜い様相の怪物)と隠れてあだ名で呼んだアン王女、今回本書の取材でシェイクスピア作品集の校訂に携わっていたことが発見されたメアリ・リーヴァ―がいる。
彼女たちの姿は、現代のファン文化にも共通する点がある。多くのシェイクスピアファンがつめかけたという1769年のシェイクスピア記念祭は今でいうファンイベントであり、そこで『マクベス』の魔女の仮装を披露したエリザベスはコスプレイヤーの元祖とも言えるだろう。またアン王女が行ったフィクション作品に登場するキャラクターに例えて他者(主に政権批判)を揶揄する行為は、2017年ドナルド・トランプがイスラム教徒の入国禁止を提案したさい『ハリーポッター・シリーズ』著者のJ・K・ローリングが「ヴォルデモートも全く足元に及ばない悪者だ」と批判したことをきっかけにハリーポッターファンの間でトランプを“ヴォルデモート”と呼ぶようになった現象にも受け継がれているものだ。
またここで描かれるシェイクスピア作品を受容していた女性たちの姿は、昨年公開の『ボヘミアン・ラプソディ』で再評価されたイギリスのロック・バンド、クイーンにおける人気の火付け役として大きく貢献したといわれる当時の日本の女性ファンに重なる点も多い。1974年当時、クイーンはまだイギリスやアメリカでも注目を集めておらず、すでに人気を博していたKISSやエアロスミスのルックスと比べ“女々しい”と評されていた。そんななか同バンドに目をつけた日本の音楽誌『ミュージック・ライフ』で元編集長を担当していた東郷かおる子氏は、その後の世界的評価に繋がった当時の日本の女性ファンの熱狂の要因についてこう振り返る。「女性ファンの心をつかむには、ルックスだけじゃ絶対ダメ。クイーンが日本で人気になったのは、フレディのどこか危険な香りやパフォーマンスに加えて、彼女たちの心に直接響くカッコいい音楽をやっていたからなんです。それを本能的に、いち早くかぎとったのが、日本の女性ファンだったと思いますね」。75年に行った来日公演の評判をを受けたイギリス本国のレコード会社は、その後クイーンの本格的なプロモーション強化に力を入れ世界的にその魅力を広めていった。
シェイクスピア作品を楽しんだ女性たちの権威に影響されない愛情、それがもとになって築かれた文化の発展が興味深く描かれた本書は、新たな文化に対する受容の様相を探求する一冊となっている。
Amazon
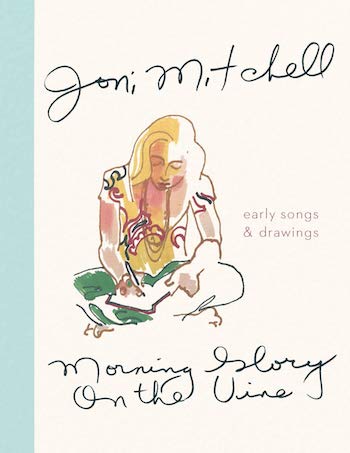
『Morning Glory on the Vine:Early Songs and Drawing』
ジョニ・ミッチェル
60年代後期アメリカで起こった女性解放運動ウーマン・リブは70年代に入ると日本を含め世界規模に拡大していく。それまでの女性シンガーといえば男性聴衆が求める甘いラブソングを綺麗な声で歌うスタイルが一般であったが、60年代以降ジョーン・バエズやジュディ・コリンズの登場により、古い民謡のエッセンスを取り入れた楽曲(フォークミュージック)にのせてプロテスト・メッセージを打ち出す新しい女性シンガーソングライター像が確立された。ウーマン・リブ、そして公民権運動といった社会的なムーヴメントが起こり、ミュージックシーンも大きな転換期を迎えるなかデビューしたジョニ・ミッチェルは、その頃フォークソングで主流となっていた時事問題を直接的に取り上げるやり方ではなく、あくまで心の浮き沈みや怒り、悲しみ、喜びといった個人の感情を詩的な表現に落とし込み社会性をあぶりだす独自の作風で人々の心をさらった。数々のミュージシャンたちとの恋愛を赤裸々に反映させたジョニの楽曲は、時代の代弁者として大衆に向け歌うだけではなく、一人の女性としてありのままの個人性を楽曲に投影させる女性シンガーソングライターの新たな境地を開拓した。
変則チューニングによるユニークなギター奏法と特徴的なヴォーカルで唯一無二の個性を発揮した71年の4作目『Blue』の評価は瞬く間に世界へその名を届け、74年にはジャズへの深い傾倒を示した『コート・アンド・スパーク』、そして80年代にはジョニを敬愛するミュージシャンたちが多数参加した本格的なロック・アルバム『ドッグ・イート・ドッグ』を発表するなど、ジャンルにとらわれない活躍をみせた。遊び心と実験性、飽くなき好奇心と探求心に満ちた彼女の作品はまさにウーマン・リブが求めた自由精神のみならず、クリエイティビティの普遍的な可能性を体現するものであり今日まで世界中の人々の心を癒し、勇気づける。
そんなジョニが『Blue』発表同年の1971年に友人への贈り物として100冊のみ作った本『Morning Glory on the Vine』が今秋初めて一般発売されることが決定している。アーティストとして、一人の女性として新たな時代の騎手であり続けた彼女による手書きの歌詞と詩に、風景画や静物画、友人の肖像画や自画像、抽象画で彩られた本書は、四半世紀の年月を越えて現在を生きる我々を知られざる創造の旅へと誘ってくれるだろう。
Amazon
text Shiki Sugawara
edit Ryoko Kuwahara
text by Shiki Sugawara