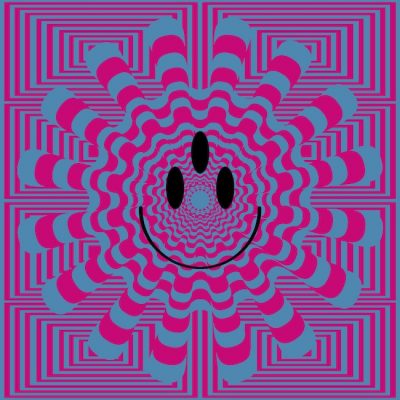『勝手にふるえてろ』に続き、綿矢りさ原作の小説を大九明子監督が再び映画化。第33回東京国際映画祭で観客賞を受賞した『私をくいとめて』がついに公開される。
主人公である黒田みつ子は31歳。人間関係や身の振り方に迷ったときにいつも正しいアンサーをくれる脳内の相談役「A」とともに、一人を楽しむ平和な日常が送っていた。ところがある日、みつ子が多田くんに恋をしたところからみつ子と「A」の関係も変化していく。本作にはみつ子や多田くん以外にも、自分を機嫌良くさせる術を知って楽しく生活している先輩ノゾミさんや、空気を読まずに堂々と生きるカーターなど、魅力的なキャラクターが多く登場する。一人で生きることを卑下するでもなく、誰かと生きることを強制するでもなく、それぞれの選択の一つとして尊重しているが故に成り立つ、楽しくもフルフルと心が揺れるような繊細さを持った作品だ。誰もが思い当たるであろう、ひとりの楽しさと社会からの目に見えない圧力を抱えるみつ子を見事に演じたのんと、原作の魅力を余すところなくヴィジュアライズし、さらに独自の世界を作り出した大九明子監督に話を聞いた。
――原作も好きなので、映画でその繊細さが守られていて嬉しかったですし、改めて選択をしていく人の物語だと思いました。多田くんとの恋愛はあるものの、それはみつ子が生きる中における一つの選択であり、仕事や先輩との関係、友情なども同じように大切に描かれています。映画では原作にない部分、特に温泉での芸人さんへのセクハラの場面などが印象的だったのですが、まず監督に本作を映像化するにあたって決してブラさないと決められた核のようなものがあれば教えていただきたいです。
大九監督「私は小説で、みつ子がAの行動を全部人ごとのようにしているところをとても面白く読んだんです。自分のことなのに、『全く、Aったらさあ』『Aはすごく落ち込んじゃって』みたいに言っているみつ子がすごく面白くて。その何事もないように飄々と生きているみつ子さんが好きだったので、そこはブラさないように、私の好きなみつ子さんを丁寧に描いたつもりです。でも小説では人ごとにしているところを笑いながら読んでいたけれど、映画化するときにはそんなみつ子を痛い目にあわせてやりたいというか、本当は気がついていて、自覚しているということを自分の口で言わせようと思って、小説にはない『嘘、本当に傷ついてたのは私。記憶を抹消するほど悲しかったんだよ』というセリフを作りました。
温泉での場面に関しては、小説では中学生の女の子に対する大人の男性のハラスメントということで大変不快で、それを描くことも素晴らしい綿矢さんの一つの怒りの表現だと思うのですが、プロデューサーからもコンプライアンスの問題もあるので違う表現にできないかという提案があり、それに代わる私らしいシーンは何だろうなとなった時に、女性芸人や女性監督など、職業にいちいち女とつく、その面倒くささなどそういったことに何か一つ力を借りられるんじゃないかと思って。私はお笑いの方たちの才能を一観客として浴びて、そこでゲラゲラ笑ってることが本当に好きなので、こういう表現が失礼になるかどうかを脚本を書いてしまってからとりあえず見てもらおうと思って(出演している人力舎の芸人である)吉住さんに読んでいただいたところ、まさにこういうような思いはすごくあると。それでいつもどうしてるんですかと聞いたら、周りが助けてくれるんですとおっしゃっていたので、それも参考にして、壇上で共演者などが助けてくれようとするんだけれど、最終的にはやはり一人で戦わなくてはいけない、というシーンにしました」
――あそこからのみつ子の感情には思い当たる節がありすぎて泣いてしまいました。のんさんにお聞きします。Aの設定は奇抜なようでいて、実は共感する人も多いのではないかと思います。のんさんは最初この設定をどう感じ、みつ子をどのような女性だと捉えられましたか。
のん「私はずっと一緒に自分の主催のプロジェクトなどをやってくれるスタッフたちがいて色々話を聞いてもらっているのですが、その存在がなかったらAを作り出していたんだろうなと思いました。 Siri やAI などがAのように話を聞いてくれるものになればいいなというのが現状だと思うのですが、Aはみつ子自分自身だから、時々失敗してくれるところとかも含めてより信頼できますよね。自分自身が聞いてくれるというのはめちゃくちゃいいし、Aが欲しいなと思います。実際に自分の中で繋がったのが、BBCの『SHERLOCK(シャーロック)』で、ベネディクト・カンバーバッチが『邪魔しないでくれ、自分の頭の中をしゃべりながら整理しているんだ』と言うシーンを見た時。そうやって自分の中でこれだという考えがあっても、人に聞いてもらった方が明確になったりするし、確信が持てたり、しゃべりながら発想したりというところがすごく自分もあるから、ワトソンのようなAがいてくれたらいいなと思いました」
――では、みつ子は想像しにくいキャラクターではなかった。
のん「そうですね。面白い設定とは思いますけど、考えれば考えるほど素敵な奥深いキャラクターだと思います」

――監督は本作でファンタジー、想像世界の表現でどのようなところにこだわって制作されたのでしょう。
大九監督「そもそも小説の、みつ子がAという脳内人物と話していて、そのAとどういう決着を迎えていくかということの表現がファンタジーといえばファンタジーだし、ワクワクしながらそこに乗っかって加速していった映像での表現たちが本作なんです。小説を読んでいる時からずっと脳内で色がフワフワ漂っていて、レモンチェッロという言葉が出てくるとそれが一気に黄色になったり、盆栽というと緑になったりしていたんだけど、特に飛行機の中のシーンに関しては、主人公の危機にあって綿矢さんが大瀧詠一さんの曲、松本隆さんが書かれたあの(“君は天然色”の)歌詞をフルで載せているということにすごく感動したし、ましてやあれは新聞の朝刊に載っていたわけで、その日朝日新聞をとっていた方はなんて心地よい朝を迎えられたことでしょうという小気味良さもあり、私の中で完全に勝手にスパークしちゃったので、それをそのまま映像にしたらああなったという感じなんですよね。脳内の宇宙を旅するような映画にしたかったので、無理に撮りやすいものに収めず、撮りにくいけど自分の脳内にあるものをどうにか形にしようとしたらあのようになって、ファンタジー表現も生まれました」
――元々監督の中にファンタジーの要素がある?
大九「どうでしょう。おめでたいヤツというか、恥ずかしいですけど、ぬいぐるみとかと話しますし、話させますね。その方が面白いじゃないってことをやりたくなっちゃうんです、映画の中では特に」

――なるほど。年齢的な部分での社会や人との向き合い方も監督としてはしっかり描きたかったところだと思うのですが、そこで31歳という年齢にした理由は?
大九監督「年齢設定に関しては、これはおひとり様の半径を増やしていくという人の話だけど、その感じをファッションではなく楽しく描きたかったんです。例えばインスタにポストするために一人で旅をするのと違って、本当に骨の髄まで一人で何かを楽しむということを楽しめるそれなりの年齢があるなと思って。私の場合は29から30歳になる時にものすごく足掻いたんですね。何も成し遂げないまま朽ち果ててしまう! って足掻いて、一人旅をして。何もしてないのに、バックパッカーで旅をしてることで何かを生み出してるかのような安堵感におさまっていただけの状態ではあるんですけど、そういうことをしてフッと30歳になって落ち着いてみると、別になんてことなかったな、むしろ少し自由になったなと思うところもあって。だから30歳になりたてではまだちょっとそのへどもどしたところでの息が上がったままだから、みつ子にはその息が落ち着いた年齢にはなっていてほしかった。実際にはのんさんの年齢がとても若くてらっしゃるから、じゃあ31歳にしようということにしました」
――本作でののんさんの声の表現は素晴らしかったです。普段の独り言の低音と外での少し高音になる感じなど、一人語りも多い役の中で、声の演技は非常に重要だったと思いますが、そこはどのように掴まれていったのですか。
のん「私はアラサーですけど、結構10代の気持ちのまま今まできている感じもあって(笑)、31歳という年齢に対して10歳くらい重ねないといけないと思っていました。内面の部分は監督にお聞きしてみたことからなんとなく膨らませていって、年齢相応にピシッと見えるように背筋を正したりして。声に関しては、多田くんと会っている時はちょっと浮かれていて高いトーンの声が出たり、そういう感情のトーンで変えてはいきましたがベースは低めの声を出すことにトライしましたね」
――監督にお尋ねになったという内面の部分とは例えばどのようなことだったんでしょう?
のん「私はみつ子は非リア充だと思っていたんですが、どうなんですかねという質問をした時に、 そういうことではなくて、おひとり様をエンジョイしているリア充ですって返ってきたので、ああ、そういうことかととても納得しました。あとは監督が先ほどおっしゃっていた、30歳になる前に海外に旅立ったというお話を聞いたり、そこからなんとなく膨らませていきました」

――本作では何かをしなさいと言う人が出てきません。ノゾミさんやカーター含め、キャラクターたちは基本的に自分で何かを選び、その責任をとって生きているところがとても魅力的でした。キャラクターたちの魅力を活かすためにどのような注意をして造形していきましたか。
大九監督「ノゾミさんやカーターは、小説でのあの二人が面白すぎたので、そのままやったら滑るな、どうやればいいのかなと思いながらだったんですけど、この作品にも何かしら臼田(あさ美)さんには出てほしいとずっと思っていて、ノゾミさんがぴったりだなと思ってお願いして、臼田さんがノゾミさんをやってくれる限りはもうどれだけふざけても大丈夫という安心感がありました。そして会社のシーンはね、カーターがいないとダメですよ(笑)。とは言え、みんな『カーターはどうやる?』と最初は途方に暮れてたんですけど、宮本茉莉さんがぶっ飛んだ衣装を用意してくれたので、そのおかげで私も心置きなく遊べたし、現場でノゾミさんが尽くしまくる芝居を作っていく中で、動きを作って、カーターはどうリアクションするかって考えていったら、自然と『すごい!』って口をついて出てきて。俺はイケメンだから奉仕されて当たり前みたいなヤツだったらちょっと好きになれないなと思ってたのですが、二人の関係性に感動して、私がどんどんますますカーターを好きになったんです。幸せになってほしいなと思いました」
――片桐はいりさん演じる澤田さんも素敵でした。
大九監督「はいりさんもオリジナルの役ですけど、格好いいはいりさんを見たかったんです。みつ子が澤田さんのような仕事ができる人と出会ったらどういう気持ちになるのか見てみたかった。すごいなあ、でも自分は凡人だからああはなれないって思ってしまうかもしれないし、嫉妬みたいなこともあるかなとか、そういうこともちょっとやってみたくて。同時に、そういう先輩たちがみつ子世代に柔らかい眼差しを向けているんだということをちゃんと描きたかったというのもあります」
――ノゾミさんとも、澤田さんとも、女性同士の連帯がありますよね。
大九監督「そこをわかってくれるのは本当に嬉しいです」

――女性同士もそうですし、ノゾミさんとカーターという関係も一般的には特殊かもしれないけど二人の間では成立しているし、カーターの思ったことを言ってしまうというのは忖度しないということでもあるので、みんながそういう風に生きていければいいなと思いましたし、監督の願望も込められているようにも感じました。
大九監督「それはすごくあります。いつも映画を作るときは自分のために、自分が観たいものを作っているところがありまして、好きな人に刺さるといいなと思います。そういう人が映画館に来ることを躊躇してしまうことがすごく心配なので、一見すごく眩しい映画と思ってしまうかもしれないけどそう思ってしまうあなたに向けて私が作った映画ですと伝えたい。そう思ってしまう人であればあるほど、どうにか劇場に足を運んでいただければ、暗がりで私といつものスタッフが待ってます!」
――本当にその通りの作品ですね。最後に、お二人が日頃、押しつけず、押しつけられず自分のチョイスで生きるために心がけていらっしゃることがあれば。
大九監督「私は押しつけられることがすごく嫌で放っておいてほしいので、人と接する時には自分も放っておくように気をつけています。人が怖いんですよ、私は。だから笑っていてほしいなあという部分でものも作っていますし、みんな好きなように好きなことをすればいいと思っている。極端なことを言うと、ちょっとくらい人に迷惑かけてもいい。もちろん罪は犯してはいけないけれど、みんな迷惑をかけなさすぎるというか。みんなもっと好きなことができればいいですよね」
のん「私も押しつけられるのは好きじゃないんですけど、めちゃくちゃ押しつけたい人なんです」
一同笑
のん「なんでわかってくれないのって。10代の時までは自分が正義だと思って正論を言っていると思っていたからなんですけど、そんなわけはなかったんですよね(笑)。今でもそれがちょっと拭えないところがあるんですが、だいぶ柔らかくなりました。20代前半までは、現場でピリピリしている感じだったんですが、そしたら自分がやりづらいということに気づいて、勝手にしてればいいのかなって。自分が自由にしてるのが一番だなと思って、今回の現場では省エネを開発しました。待ち時間でも現場でボーッっとしてたら『ボーッとするな!』って思われるんじゃないかなって、ピリピリしてる風にしたり、馬鹿にされないぞとキッと構えてたんですけど、今回はボーッとしてみようと思って初めて実践してみたんですよ。そしたらわりと良くて」

――それが林遣都さんの「よーいスタートで目の色が変わる」と言うコメントに繋がっているんですかね。
のん「ああ、そうかも。いや、でも省エネは後半戦だったから林さんは目撃していないかも。最初はターボをかけて待ち時間もテンションをあげて五感を開いてみつ子に乗っかっていくみたいな感じで。後半のあたりの待ち時間に、こう……(省エネを再現しようとする)……ちょっと今はできないんですけど、できるんですよ、現場では」
一同爆笑
大九監督「そんなことしてたの気づかなかったなあ。存在を消してたから気づいてないのかな」
のん「すっごく上手になっちゃったんで」
大九監督「(笑)」
のん「本当に何も考えないということができるようになったので、これから省エネを大切にしていきたいと思います!」
『私をくいとめて』
12月18日(金)より全国ロードショー
https://kuitomete.jp
原作:綿矢りさ「私をくいとめて」(朝日文庫/朝日新聞出版刊)
監督・脚本:大九明子 音楽:髙野正樹
劇中歌 大滝詠一「君は天然色」(THE NIAGARA ENTERPRISES.)
出演:のん 林遣都 臼田あさ美 若林拓也 前野朋哉 山田真歩 片桐はいり/橋本愛
製作幹事・配給:日活 制作プロダクション:RIKIプロジェクト 企画協力:猿と蛇 ©2020『私をくいとめて』製作委員会
30歳を越え、一人での生活もすっかり板についてきた黒田みつ子(のん)。みつ子が一人でも楽しく生活できているのには訳がある。脳内に相談役「A」がいるのだ。人間関係や身の振り方に迷ったときはもう一人の自分「A」がいつも正しいアンサーをくれる。
「A」と一緒に平和なおひとりさまライフがずっと続くと思っていたそんなある日、みつ子は年下の営業職、多田くん(林遣都)とプライベートで遭遇し、会話を重ねるようになっていく。相手を思いやる距離の取り方ができ、礼儀正しい多田くんは徐々に気になる存在に。一人の快適さになれ、そこに訪れる変化に戸惑いながらも、一歩をふみだすみつ子の姿とAの会話は優しく、観るものを静かに鼓舞してくれる。
photography Yudai Kusano
text & edit Ryoko Kuwahara