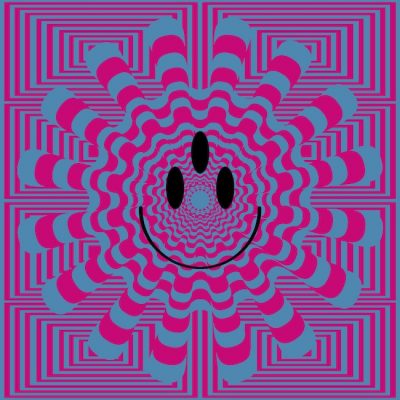フランソワ・オゾン監督が、初めて実話に基づいた物語に挑んだことでも話題をさらった『グレース・オブ・ゴッド』。ヨーロッパを震撼させたこの神父による児童への性的虐待事件、2016年1月に捜査が開始された通称「プレナ神父事件」は、ある一人の告発がきっかけで80人にも上る証言が集まり、プレナ神父は担当する教区を変えながら長年にわたって信者家庭の少年たちに性的暴力を働いていたという驚くべき事実が白日の下にさらされたものだ。2020年3月の一審で、プレナに禁固刑5年が求刑されているが、事件の裁判は現在も係争中で、渦中の神父から上映差し止めを訴えられた。
物語は、20 年、30年経っても虐待のトラウマに苦しむ男性たちが、告発するまでの葛藤と、告発したことによる周囲との軋轢という代償、それでも告発によって確かに生まれた希望を紡ぎ出していく。人生を破壊する性的虐待という暴力の恐ろしさと、再生の過程、それを支える家族の愛ーー。
出演は、グザヴィエ・ドラン監督の『わたしはロランス』で圧倒的な存在感と美しさを発揮したメルヴィル・プポー、『ブラッディ・ミルク』 でセザール賞を受賞したスワン・アルロー、ヴェネチア国際映画祭で監督賞を受賞した『ジュリアン』の父親役が記憶に新しい実力派のドゥニ・メノーシェ。本作で3人揃ってセザール賞にノミネートされ、心をうがつ傷を繊細かつリアルな演技で表現したアルローが見事助演男優賞を獲得した。
オゾンは子供時代の健やかな日々を奪われた被害者たちの魂の慟哭に寄り添いながら、彼らが人間としての尊厳を取り戻す戦いを、緻密かつ緊張感の漂う演出で描き上げた。ベルリン国際映画祭では銀熊賞(審査員グランプリ)の栄誉に輝き、本国フランスで91 万人を動員する大ヒットを記録。なぜオゾンは証言や事実を忠実に再現しながらも、本作をフィクションで撮ったのか?
ーー初めて実際の事件を題材にしましたね。多くの実在の人物も登場します。
オゾン監督「当初のアイデアは、男性の脆さをテーマにした映画を作ることでした。私は強い女性を描くことが多いのですが、今回は苦悩の表情を浮かべる感情的な男性たちを描きたかった。この考えがプレナ事件と重なったのです。被害者団体の“沈黙を破る会”のホームページで子供時代に教会で性的暴行の被害にあった男性たちの証言を読みました。そのうちの一人、アレクサンドルの話にとりわけ心を揺さぶられました。彼は熱心なカトリック教徒で、40歳になってようやく被害について話すことができるようになるまでの苦しみを語っていました。ホームページには彼のインタビューやメディアの記事、アレクサンドルがリヨン教区の幹部たちとやりとりしたメールの抜粋も掲載されていました。この中にはバルバラン枢機卿、聖職者たちから被害にあった人々の相談役で心理カウンセラーのレジーヌ・メールのメールもありました。これらの資料は非常に興味深く、アレクサンドルに連絡を取ったのです」
ーー彼との出会いはいかがでしたか?
オゾン監督「彼は告訴状を出すまでにやり取りしたメールも含む、資料一式を持って来ました。私を信頼し、これらの手紙を見せてくれたことに感動しました。このメールの抜粋は映画の冒頭で聞くことができます。この驚くべき資料をもとに、最初は演劇作品を作ろうとしましたが、やはりドキュメンタリーを撮ろうと思い直しました。アレクサンドルには何度も会いましたし、フランソワとエマニュエルを含む他の被害者たち、その妻子、親戚、エマニュエルの母親、弁護士たちなど、周囲の人々にも会い、ジャーナリストがするような調査をしました。映像を撮ったのではなく、話を聞き、メモをとりました」
ーーなぜドキュメンタリー映画でなくフィクションにしたのですか?
オゾン監督「私の企画をより具体的に被害者たちに話す段階になって、ドキュメンタリーの案に対し、彼らの落胆とためらいのようなものを感じたんです。彼らはすでに多数のメディアのインタビューに応じ、何度もテレビ用ドキュメンタリーに登場していました。彼らはフィクションの監督が近づいてきたから好奇心を持ったのです。『スポットライト 世紀のスクープ』のような映画を思い描き、映画の登場人物となって有名な俳優に演じてもらうのを期待したんです。それが彼らの望んでいることであり、それが私のできることでもありました。それでフィクション映画にすることを決めましたが、恐れもありました。実在の人物たちがとても好きになっていたので、彼らを映画で公正に表現する方法を見つけることができるのか不安だったのです」


ーー脚本の執筆はどのように進めたのですか?
オゾン監督「最初のうちは、この現実の出来事にひねりを加えようと思いました。被害者たちが話をするとき、大抵グレーゾーンを残すのですが、私はダイレクトに進めがちです。それから登場人物の多さに戸惑っていたので、人数を減らそうとも思いました。例えば脚本的な観点における効率化のために、フランソワとエマニュエルの弁護士たちをまとめて一人の人物にしています。これは“コミュニティについての映画”であり(主人公の映画ではなく一つの事象を扱った映画)、現実の出来事とそれらの複雑性に最大限に忠実であろうとしました。
アレクサンドルに彼の教会とのやりとりを時系列で聞き、特にレジーヌ・メールとプレナ神父との面会については細かく説明してもらいました。フランソワとエマニュエルについては彼らの供述書を入手していたのでよりシンプルでした。
“沈黙を破る会”のホームページに掲載されている会員全員のメールや証言も参考にし、彼らの言葉や表現を学びました。劇中でエマニュエルがプレナ神父に『僕は子供だった』と言いますが、これはエマニュエル本人が発した実際の言葉です。正確には映画とは違い、話したのではなく、プレナ神父に当てて書いた言葉ですが」
ーーバルバラン枢機卿、レジーヌ・メール、プレナ神父に会いましたか?
オゾン監督「ドキュメンタリー映画を撮るのをやめた時点で、彼らに会うことには意味がなくなりました。彼らに関して明らかにする新事実はなかったからです。私が作中で描く事件の調査結果や詳細はすでにメディアやインターネットで語られています。事件そのものには手を加えていません。私にとって重要なのは子供時代に傷つけられた男性たちの心の奥を語ることと、彼ら被害者の観点からストーリーを語ることでした。彼らの経験と証言には忠実でありつつ、周囲の人々やその反応については自由に描きました。だから被害者たちの姓を変えたのです。バルバラン枢機卿とプレナ神父とは反対に、彼らはフィクション映画の主人公になったのです」
ーー三人の登場人物に順番に焦点を当てるというアイデアは何から得たのですか?
オゾン監督「ごく単純に、現実、実際に起きたことすべてからです。早い段階で気がつきましたが、あるときにアレクサンドルの歩みは止まり、話は彼なしに進んでいたのです。アレクサンドルの告訴状は警部を動かし捜査が始まり、警察はフランソワに連絡をし、そしてフランソワは被害者団体“沈黙を破る”を立ち上げてエマニュエルと出会います。ドミノ倒しのような展開です。この映画は、アレクサンドルと組織との闘いから始まり、次にフランソワがそれを引き継ぎ、被害者団体を作ります。そしてこの団体からもう一人の被害者、エマニュエルが現れるのです。エマニュエルはてんかん患者という設定にしましたが、実際のエマニュエルは違います」


ーー映画はフルヴィエール大聖堂からリヨンの街を見つめる枢機卿の後ろ姿から始まりますが。
オゾン監督「この映画がリヨンに根ざしていることは重要でした。リヨンはガリア(ガリア人-ケルト人の一派-が居住した地域の古代ローマ人による呼称。具体的には現在のフランス・ベルギー・スイスおよびオランダとドイツの一部などにわたる)でキリスト教が広まった最初の土地で、今でも教会は非常に保守的な伝統を守っています。
地理的にみて、大聖堂はフルヴィエールの丘にそびえ立ち、街を見下ろしています。 これは街に対する教会の影響力のメタファーでもあります。
この映画の狙いは教会を罰するのではなく、教会が持つ矛盾とこの事件の複雑性を提示することでした。あるとき、エリック・カラヴァカが演じる人物が“沈黙を破る”に参加する意義をこう述べます。『教会に反対したくてやってるんじゃない。教会のためにやってるんだ』。
古くなった組織を変えるのは大変なことです。習慣、保守主義、秘密主義によって身動きが取れなくなっていて、皆が自分の身を守ろうとし、誰も行動を起こすことができないんです。それからプレナの問題は、彼の子供に対する振る舞いを除いては、彼は良き司祭であり、教区の信者にも上層部にも気に入られていたということです」
ーー沈黙からついに解放されたアレクサンドルの言葉の響きには緊張感がありますね。
オゾン監督「アレクサンドルと教会組織のメールのやり取りでリズムを作り、ストーリーをすぐに始め、早く本質に辿りつかなければなりませんでした。彼のメールはとてもよく書けていて力強く、絶対に映画で使いたいと思いました。このナレーション部分は出資者を不安にさせましたけどね(笑)。この事件で驚かされるのはすべてが明白に説明されていて、事実が分かりきっているのに、行動がそれに続かないということです。この不公正さはあまりに極端で理解不能でした。
この件ではSNSやインターネットが重要な役割を果たしていて、これが“沈黙を破る会”の 設立を後押ししたのです。この団体が結束するシーンを描くのにメールのやり取りを参考にさせてもらいました。実際には彼らはここまで何度も会ってはいません」


ーーこの映画ではアレクサンドルとフランソワの妻も存在感が大きいですね。
オゾン監督「現実でも彼女たちの存在は重要なのです。彼女たちの支えなしに彼らがこの挑戦に挑むのはかなり難しかったはずです。彼らは闘いを共有してきました。被害者たちは沈黙の中でひどく苦しみ、言葉に出したときからこの件は常に家族に付きまとい、しまいには嫉妬心まで生み出します。フランソワの兄はこう言います。『お前の話にはもううんざりだ。親もその話ばかりだぞ!』観客に“沈黙を破ったこと”が引き起こしうる暴力を体験してもらい、その影響を具体的に見せたいと思いました」
ーー撮影はどうでしたか?
オゾン監督「この映画は急いで作らないとなりませんでした。現実のニュースは流動的だし、予算面の問題もあった。児童への性的虐待というテーマは人を怯ませ、この企画は『融資不可能』と判断されました。多くのロケーションは使用を禁じられ(教会内部のシーンはベルギーとルクセンブルクで撮影)、『まぼろし』のときと同じような状況に陥りました。幸いにもプロデューサーたちと制作チームは企画を信じ、支持してくれたので、このような反対意見やブレーキは私たちにさらに企画を押し進め、これは必要な映画なのだと示そうという力を与えてくれました」
ーーキャスティングはどのように進んだのですか?
オゾン監督「現実の事件の関係者たちの顔を知りながら、彼らに似た俳優を探す必要がないというのは中々ないことです。観客たちは彼らの顔を知りませんからね。
メルヴィル・プポーとはすでに2つの作品で仕事をしたことがありましたが、すばらしい俳優です。円熟した彼はさらに面白いものを持っています。それに、彼自身が信仰について考えを巡らせていることを知っていました。ドゥニ・メノーシェともすでに仕事をしたことがありました。彼のエネルギー、目に見える力強さの中には鋭敏な感性が隠されており、それがフランソワとよく合っていました。スワン・アルローに関しては、『ブラッディ・ミルク』(2原題『Peitt Paysan』。フランス映画祭2018での上映時の邦題。アルロー はこの映画でセザール賞主演男優賞を受賞した) を観て、エマニュエルを演じるのにぴったりな豊かさと脆さを感じました。プレナ役のベルナール・ヴェルレーは、この人物像にカリスマ性と力強さ、ある種の愚直さをもたらし、その複雑性を表現してくれました。難しい役ですが、躊躇なく引き受けてくれました。この人物の恐ろしいところは、自分の行動の重大性をまるで意識していないように見えることです」

ーー音楽はエフゲニー・ガルペリンとサーシャ・ガルペリンが担当しています。
オゾン監督「アンドレイ・ズビャギンツェフの『ラブレス』の彼らの音楽がとても気に入っていて、特に繰り返しと緊張感が良かった。彼らには非常にコンテンポラリーであると同時に、宗教音楽でよく使われる要素、オルガンや子供のコーラスを使って欲しいと頼みました」
ーーこの映画が現実を動かすと思いますか?
オゾン監督「この映画を見たある司祭にこう言われました。『この映画はもしかすると教会にとってはチャンスかもしれない。教会が映画を受け入れられれば、ようやく教会内部で起きた事件の責任を負い、その撲滅のための最初で最後の闘いを始められるかもしれない』。そう期待しましょう!」
7月17日ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開
graceofgod-movie.com
監督/脚本:フランソワ・オゾン 『彼は秘密の女ともだち』『2重螺旋の恋人』『しあわせの雨傘』
出演:メルヴィル・プポー、ドゥニ・メノーシェ、スワン・アルロー、 ジョジアーヌ・バラスコ、エレーヌ・ヴァンサン
製作:エリック&ニコラ・アルトメイヤー 撮影:マニュ・ダコッセ 音楽:エフゲニー&サーシャ・ガルペリン
2019 年/フランス/2 時間 17 分/カラー/ビスタ/5.1ch/原題: Grâce à Dieu / 日本語字幕:松浦美奈
提供:キノフィルムズ 配給:キノフィルムズ/東京テアトル
©2018-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-MARS FILMS–France 2 CINÉMA–PLAYTIMEPRODUCTION-SCOPE
Story
「君もプレナ神父に触られた?」──時は2014年、そのひと言がすべての始まりだった。フランスのリヨンに妻と5人の子供たちと暮らす、40歳のアレクサンドル (メルヴィル・プポー)は、同じボーイスカウトにいた知り合いからそう尋ねられ、プレナ神父(べルナール・ヴェルレー)から受けた性的虐待をまざまざと思い出す。 あろうことか、神父が今も子供たちに聖書を教えていることを知ったアレクサンド ルは告発を決意。だが、最初に相談したバルバラン枢機卿(フランソワ・マルトゥ レ)は、処分を求めるアレクサンドルに同意しながらも、いつまでもプレナを裁こうとしない。不信感を募らせたアレクサンドルは、自分の事件は時効だが、他にも多 くの被害者がいるはずだと、プレナ神父に対する告訴状を提出する。
捜査に動き出した警察は、1991年に枢機卿宛に届いた、プレナ神父による息子への行いを非難する母親の手紙を発見、当時の被害者であるフランソワ(ドゥニ・メノ ーシュ)に連絡が入る。はじめは「大昔の話だ」と関りを拒んでいたフランソワも、 記憶が蘇るにつれ怒りがこみ上げ、警察にすべてを語り「告訴します」と告げる。 フランソワは同時に、知っていながら何もしなかった教区も訴える決意を固めるのだった。
フランソワはバルバラン枢機卿に、マスコミにリークすると宣戦布告、慌てた枢機卿は会見を開き、プレナを「全職務から外した」と発表する。フランソワ自身も 「もう隠れない」と決意、名前も顔も公表してテレビの取材を受ける。さっそくフランソワのもとへ、同じ被害にあったというジル(エリック・カラヴァカ)と名乗る 医師から連絡が入り、全国規模での記者会見を開き、もっと証言や被害者を集めよ うと話し合う。
やがて、アレクサンドルとフランソワ、ジルは互いを知ることになる。パリのテレビ局の顧問を務めるアレクサンドルは、自身の社会的地位と妻の教会系の学校教師という立場を気にして表に出ることを躊躇しながらも、「沈黙を破る」と名付けられた被害者の会の記者会見に参加する。
大々的に取り上げられた会見の記事を読み、自分も証言したいと名乗り出たエマニュエル(スワン・アルロー)も時効前の被害者の一人だった。長年一人で心の傷を抱えてきた息子を見守り、戦わなかったことを後悔していた母親も、会の実務を手伝うことになる。
教会側はプレナ神父の罪を認めつつも、自分たちの責任問題は巧みにかわしていく。アレクサンドルたちは信仰と告発の間で葛藤しながら、沈黙を破った代償── 社会からのバッシングや家族や友人との軋轢とも戦わなければならなかった。果たして、彼らが人生をかけた告発のゆくえは──?
「プレナ神父事件」映画以降の流れ
2016年1月 プレナ神父への捜査が開始。
2018年8月 性的虐待の時効を「成年に達してから30年」まで延長。
2018年11月 118人の司祭がルルドで投票を行い、1950年からの教会内部での児童へ の性的虐待事件に光を当て、対処するための独立委員会の設置が決定。
2019年1月 バルバラン枢機卿、レジーヌ・メール、カトリック教会の5人の幹部 が、15歳以下の未成年に対する性的暴行を通報しなかったこと、彼ら を適切にを救わなかったことに対する裁判が開始。
2019年3月 バルバランは執行猶予付き禁錮6ヵ月の有罪判決。
2019年7月 教会裁判所はプレナ神父を還俗させた。
2020年1月 プレナ元神父の裁判開始。検察から「少なくとも8年」の懲役が求刑。
2020年1月 バルバランの控訴審で、一審を覆し 無罪判決。
2020年3月 バルバランのローマ教皇に表明した辞意が受理される プレナ元神父に禁錮5年の有罪判決。プレナは上訴。
審理は現在も行われている。

フランソワ・オゾン
1967年11月15日、フランスのパリ生まれ。1993年に国立の映画学校を卒業。短編『サマードレス』(96)や長編第一作『ホームドラマ』(98)が国際映画祭で評判を呼び、『焼け石に水』(00)でベルリン国際映画祭のテディ賞を受賞。以降、ベルリン、カンヌ、ヴェネチアの世界三大映画祭の常連となる。セザール賞の監督賞には『まぼろし』(01)を始め、『8人の女たち』(02)、『危険なプロット』(12)、『婚約者の友人』(16)でノミネートされてきた。『しあわせの雨傘』(10)では同賞の脚色賞にノミネート。オゾン初の事実を元にした社会派ドラマ『グレース・オブ・ゴッド 告発の時本作』(19)は第69回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞したほか、2020年のリュミエール賞では最多の5部門にノミネート、セザール賞では7部門8ノミネートされ、スワン・アルローが助演男優賞に輝いた。