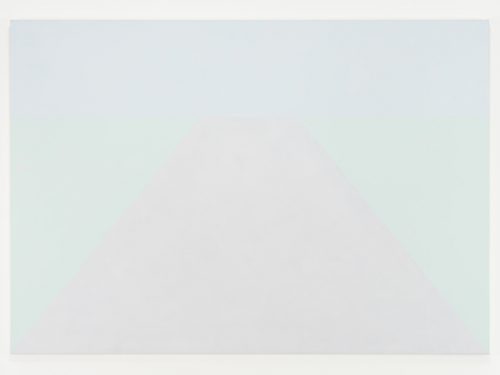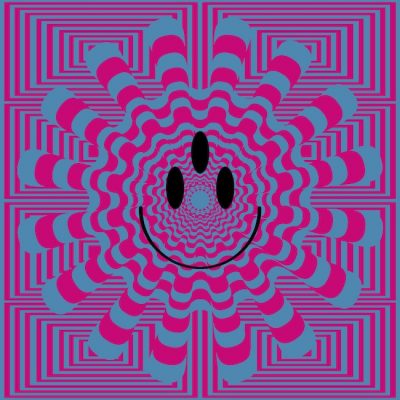アメリカのレーベル「Deathbomb Arc」との契約、台湾のIT担当大臣、オードリー・タン(唐鳳)とのコラボ、そして海外音楽レビュアーから「ヒップホップ界のセンセーション」と呼ばれ、独自の道を築いてきた東京発の3人組ヒップホップユニットDos Monos。今回のインタビューでは「日本vs海外の音楽論」ではなく、「海外のリスナーから見たDos Monos」と「本人たちが音楽を作る上で考えるDos Monos」という視点に注目しながら、新アルバム『Dos Siki』のリリースやアーティストとしての思想、そして作品が生まれ、社会に届けられるまでのダイナミクス、そしてその先にあるものについて聞いた。
――まず、新アルバム『Dos Siki』の作り手の意図と受け取られ方について聞きたいです。日本からは異質な存在、海外ではAnthony Fantano等のレビュアーから「ジャパンから来たクール」な存在として捉えられているDos Monos。「四季」という日本的なテーマを扱い、サンプリングでも和風に感じられるモチーフを取り入れてたことに感じるアイロニーは、意図的なものだったのでしょうか?
荘子it「日本で生きている我々でも、平安時代の和歌で歌われるようなステレオタイプな四季はほとんど感じずに生活していて、例えば夏に『冬の景色』をパソコンで検索すれば、いくらでもデスクトップ上で視覚情報と聴覚情報としてアクセスできる。そこに囚われずに生きていけるというアイロニーはジャケットの時点で表していて、額縁に飾られた4つの季節の要素を全部混ぜているビーチにマンモスがいて、そのマンモスに桜が生えてる。一個の額縁に飾られた、全部が混ざりこんでしまっている四季を自分が好きなように飾って眺めているという状況を作って、ステレオタイプな四季のイメージを刷新するみたいなことを意図しています。楽曲としても4曲が春夏秋冬の順番になっているけど、夏の歌の中に冬っぽい要素があったり、最後の冬の曲にはラテンの常夏感のあるフレーズが入っていたりして。前回の『Dos City』も、東京という街に対しての違和感の表現としての『もう一つの街』でした。シティと全く関係なく生きてきたとは言えないし思ってもいないけど、やはりステレオタイプっと言われているシティとは違うシティボーイに育ってしまった自意識もあるからこその表現で。今回も『いわゆるステレオタイプの四季ってこうだよね』というものに、ちょっとオルタナティヴに『自分たちとしての違うところ』を出しました」
――日本の中で生きていている人だからこそ感じる違和感をパッケージしていることが、外国人から見た時に日本のステレオタイプを浮き彫りにすると。
荘子it「今回ネタとして使っている音も実は日本のものは一切なくて、多く使っているアフリカのものが音階的にペンタトニックスケールが多いからプリミティブに感じますが、『西洋音楽』という和声として凝っているものから見ると、アフリカでもアジアでも一緒くたに『オリエンタル』な感じがしてしまうという音楽的な解像度の荒さはよく見受けられますね。西洋音楽と東洋音楽の違いでいうと、例えば僕らが日本人でありながらスペイン語の名前を乗ったり、ロゴはギリシャ文字だったり、今回のネタもどちらちかというと西洋のものと言うよりもアフリカのものを使っていたりするのも、その中で日本ぽいものあえて使わず、日本以外のオリエンタルなものを日本人が使うことでオリエンタリズムの解像度を上げていくという、西洋圏の中での第三国の様々なものを正確に捉えながら扱うということをやっています」

――自分の属性やバックグラウンドがどのようなものかによって二通りの楽しみ方ができるというのをDos Monosの音楽では感じますが、その受け取り方は想定されていることでしょうか? 例えば自分の場合は「日本人としての自分」と「日本人以外の視点」で聴こえ方が全く違います。
荘子it「日本のそういうガラパゴスなものに毒されているが故の楽しみ方や、その内面化しているものを抜け出した先での面白さというのものの楽しみ方も知った上でやってます。使い分けて楽しむ時に自己批判に行く人も多くて、日本的なガラパゴスに染まり上がってしまった自分をものすごく軽蔑するというか。その気持ちもすごく分かるんですけど、そこもより見つめると両方楽しめるし、気づきも肯定的に得られるんじゃないかな」
――日本人であっても、メタ的に自分を見るためのツールになり得ると。
荘子it「ジェンダーの問題でも、例えば男性がこのご時世においてものすごく自分の男性性に対する自己批判意識を持ったり、あるいは逆に女性が今まで男性の権威に従属して生きてきたことへの違和感があったり、そしてその自己批判と旧態依然とした構造の心地よさとの両方を持ち得ることはあると思うんですが、その葛藤を乗り越えた先でその両方の自分が楽しめるような状況に持っていくというか、そういう陰と陽の両方を楽しむところに行きたくて。そのためにステレオタイプも時には使うし、究極なナンセンスを目指す過程では時々意味ありげなこともしなくちゃいけなかったりする」

――Dos Monosの音楽は、日本では「異質」「不穏」と良く表現されますが、英語だと「楽しい」「エネルギーを感じる」「自由になれる」という表現が多く、感想の差を感じます。アーティスト側はどう感じていますか?
没「日本だと他のヒップホップグループとの比較の上で語られるけど、海外では俺らの音楽だけを聴いてくれている感じがする。コンテクストの差だと思うんですけど、海外ではわりとハードな表現が一般化していて、日本に比べるとポピュラーに聴かれるという中で俺らみたいのが出てくるから、そこも実は相対的な目線で楽しいと思われているかもしれないですね。でも俺らも日本でライブをするときには結構『楽しい』という風に伝わってると思う」
――それぞれリスナーとしての音楽遍歴が異なったり、没さんは米国留学を経験していたりバックグラウンドも違いますが、3人別々の解像度で曲を作っていますか?
荘子it「僕は没みたいに海外留学はしてないけど同じ様に海外の音楽を聴いて育っていて、でもそこでのギャップも何かしらあるとは思っている。TaiTanはもっとドメスティックな日本の演劇とかに親和性を感じているし、それぞれのズレはありつつも三者三様に乗り切れない感じや、一回海外の目線を通して自分たちの面白さを発見する目線はあります。僕はむしろある時期から日本よりも海外の音楽の方が楽しくなったタイプのリスナーなので、そっちの美意識を内面化しているんですけど、自分がそれをそのまま真似て模したような音楽をやるよりも、やはりメタ的な視点でその海外の音楽の美意識を経由した先を考えた時の微妙なバランスの面白いものを作りたいです」
――海外のリスナーが日本の音楽に対しては「洋楽の二番煎じ」という偏見がよくある中で、Dos Monosの楽曲が「オリジナリティーが凄い」という風に、洋楽を通してはいるけれど俯瞰して作り出しているというのが、その曲自体の世界観が評価されるということに繋がっているように思いました。
没「結果的にそうなってるのは嬉しいです」
――客観的に見て「面白い」と感じられるようにプロモーションをすることと、曲を理解するという意味での言語化をするのはどちらも客観的に自分を見る必要がありますが、Dos Monosはそこに長けているように思います。
荘子it「僕はリリックが乗る前のトラックを作る時点で、言語的な構造を備えている面があります。例えば漫画の絵の部分と吹き出しの文字の部分は別で、それがいわゆる言語の領域と図像の領域だとして、音それ自体という空気振動のものを絵だとすると、それが持っているコードがCであったりという記号的な部分が文字で表せるような言語の領域というところがある。絵だけをずっと描いている人とそれを評論する人がいるとしたら、その文字情報と図像という、2つのものの溶け合わせをしている感覚です」
――制作している最中に情報量のバランスをコントロールしていくと。
荘子it「キャラクターっぽいのかな。純粋な絵画だとイメージの領域を追求して、それを評論するときには言語を使う。例えば、キャラクターの絵自体がいかに凝っていて、いかに素晴らしいかを評論で伝える以上に、例えば、草薙素子(当日同席した編集者のファッションが草薙素子風だった)というキャラクターが持っているヴィジュアルや人格などはあらゆるリテラシーの人までその実在感それ自体を伝える能力があって、それがキャラクターの魅力だと思うんです。自分はそういう意味ではキャラクターを作っている感覚。キャラクターの顔が見えるトラックということをかなり自覚的にやっているのは、ニルヴァーナが好きだからっていうのもあります。カート・コバーンは、彼自身がすごく好きだったノイジーなグランジ音楽を商業化するという意味以上に根本的に音楽としてめちゃめちゃポップにして、その構造的に明らかに『顔が見える』ようなものを作れる人なんですよ。『Dos Monosっぽい音楽』ってあるんですけど、それはキャラ化してないとやっぱり面白くないというか、まさにニルヴァーナ的に、自分が好きだったタイプの音楽を抽象化し、キャラクターとして作ってるという感じはあります」
――顔としてのキャラクターを認識すると同時に、自分が感情移入する以前にそのキャラクターを多面的に捉えることができると、作品に深さが生まれますよね。
荘子it「そう、例えば美術館に行って100枚の印象派の絵画とかがある中で1枚ドラえもんの絵があったら、誰でも引っかかるじゃないですか。そこで深読みし出すと、『実はこのドラえもんはこの曲線が良いんじゃないか』となるけど、本来他の絵はそこまで見てもらえない。そういう意味で、俺は『顔の見える』曲を作っている感じです」

――「音楽を届けるためのキャラクター化」という話の先に、音楽をメディアとした際のリリース後の伝え方やリリースを通しての伝え方とかはいかがでしょうか?
TaiTan「例えば、『本当にかっこいい人たちが売れてない』という状況が非常に不愉快という話はよく出ると思うのですが、俺の考えからすると当然そういう存在がいてもいいし、そういう存在を面白がる人がいてもいいし、リスペクトはある。だけど、『アーティストはかっこいい音楽を作っていればそれでいい』的な言説を無邪気に鵜呑みにするのは、あまりにも今の社会の構造を見過ごしているんじゃないかと一方では思う。つまり現代の情報流通量やメディア環境を舐めすぎているというか、音楽を作って充足すること自体は当然誰からも何か言われる筋合いは無いけど、人に聴かせたいと願うなら、果たしてSoundCloudやYouTubeに上げておいたら、いつかジャスティン・ビーバーやBTSがシェアしてくれるんだっけ?というしょぼい1周目の議論になってしまうわけで。その意味でDos Monosに関しては、俺らが少なくとも届けたい層に届けるための情報設計は当然アーティスト側が考えざるを得ないと俺は思ってる。Dos Monosは『俺らは俺らでかっこいい音楽やってて自分たちが満足いく音を作れたから、後は何もやりません』みたいなスタイルをとることも当然できる。だけど俺は、もっと不意打ち的にいろんなリスナーの回路を突き破りたいなと思っているタイプだから、そのために『Dos Monosっぽい動き』を音楽制作以外のすべてアクションの中にも設計していくのが理想。この間の広告(*リリース前の新曲DAW画面を屋外広告として公開。下記参照)を作ったり、オードリー・タンとのコラボ曲に意義や文脈を乗せるとかもそう。『Dos Monosの音楽を作る』という所からは本質的には離れるようにみえるのだけど、Dos Monosの音楽を2020年という現代において届けたいとしたら、そういう活動も自分たちのストレスのない範囲で面白がるべきなんじゃないかなと思っています」

――「アーティストにとっての成功」が曖昧で、本当に楽曲を届けたい人は誰なのかという問題に向き合わずに「海外進出」を目指す人が多い中で、『Dos City』を出してから次のアルバムを楽しみにしていたり、言語もわからないのに「四季」の意味やサンプリングについて深掘りしたりという海外のリスナーが存在していることにロマンを感じます。さらにリスナーや理解者を増やしたいという目標はありますか?
TaiTan「基本的には3人のスタンスってそんなに変わらなくて、俺もDos Monosの音楽が良ければそれで良いけど、かっこいいものを作り続けるためにはそれを可能にする環境も同時に作らなければいけないわけで。俺は比較的メンバーの中でその(音楽を届けていかなければいけないという)役割を担いがちですね。美学は追求しつつ、メンバーの士気というか、グループとしての命も失わせてはいけないというまたひとつの事実にはシビアに向き合ってるつもりです。
SNSなどでリスナーからの反応を見るときも、自分たちの音楽を適切な場所に届けるための情報の経路が機能しているかどうか、機能しているとしたら他の経路にバグ的につなぐにはどうすればいいかを意識していて、いわゆる承認欲求からは離れたことをしている気がする。ただ、ここで大事なのはDos Monosはスタートアップ企業ではないわけで、単純なスケールアウトや上場を目指すみたいな考えではないということですね。あくまでも、俺らが何かアクションを起こした時に積極的に支持してくれたり、面白がってくれる人間の数を増やしたいと思う。ありがちな言葉でいうと『熱量の多いファン』を増やしたい。もちろんその過程でいろんなタイプのリスナーが増えるのは嬉しいですが、その順序は逆転させちゃいけない」
――自分のクラフトに集中するのが本来アーティストのあるべき姿だとした時に、資本主義社会というものに迎合するわけではなくて新たな軸でルールを作って、その中で自分たちがどういう道で進んでいけるのかを試していくのがTaiTanさんのやっていることなのかなと。
没「メインストリームのルールを知っているからこそ逸らせるというのはある。Dos Monosの音楽でも、その露出の仕方や楽曲の仕方も、逸らすのが面白いとわかってるからできる」
荘子it「僕はキャラ化してポップにすると面白いと言ったけど、ニルヴァーナの『売れる』ことへの本質的な面白さを感じていなくて、ポップ化することによって音楽として新しくなるから面白いと感じる。Dos Monosの音楽がポップで活動が特殊であるということの面白さは、ある意味そういう面で評価されるべきであって、それが数値的にスケールアウトしていくということを面白さだと思っていないし、思ってほしくないです。副次的な要素としてリスナー数を獲得し得る構造を備えたこと自体が面白くて、その結果として数字が増えるのは本質ではなく、新しい世界観を作品の中に作り、それが未来予想図になっただけ。誰も想像できなかった未来を創り得たこと、そして活動が真にオルタナティブであるという面白さはそこにある。そこに金や認知がついてくるというのはどうでもいい。行き着くところは同じだけど、どの視点から評価するかという話です」
――これまでもDos Monosは社会の中にあるディストピア感を表現してきています。今までだったら平和ボケしていたり、特に何も危機感のない人たちに向けてナイフを突き刺しているようなリリックとして捉えられていたものが、社会自体がディストピアになりつつある現状において、自分たちの社会に対するスタンスや表現に変化はありますか?
荘子it「自分が前々から持っている世の中に対する考えや人に対する印象とかってそんなに変わっていないけれど、やはり状況が変わったときに表現者として外面的な表現の仕方を変えざるを得ないというのはあると思います。そこを変えずに、『あいつはずっと同じことをやり続けている』ということを評価されるのが本来のアーティストの仕事なんですけど、僕はミュージシャンとして、『現代』という時間のスパンで捉えられる部分と捉えられない部分への対外的な態度の示し方を多少は変える必要があると思っています。完全に平和ボケしている状況だったら確かにナイフを刺してればいいんですけど、こういう状況になっているときにひたすらブスブス刺しているだけでは、それはそれでままごと化している。これまでも、平和ボケしている人に対して音楽でもって釘を刺しているだけという自意識自体がアーティストの甘えであるという部分はすごくあって、それを同じようなやり方でやっていても意味がない。平和ボケしている世の中においてはそれはある種のアイロニーとして機能しているのだけど、その攻撃力もたかが知れてるというところも思っていて、そういう意味で今は別の形を色々とやっていますね。『Dos City Meltdown』の頃と、今年に入って出した『Rojo/Fable Now』は、自分の中で違った出し方をしていますし、今後も形は変わっていくと思います」

photography Yudai Kusano
text Daniel Takeda
edit Ryoko Kuwahara

Dos Monos 『Dos Siki』
Now on Sale
Label:+809
Tracklist:
1. The Rite of Spring Monkey
2. Aquarius (feat. Injury Reserve)
3. Estrus
4. Mammoth vs. Dos Monos
https://music.apple.com/jp/album/dos-siki-ep/1523491093
https://open.spotify.com/album/5ipHjYD5uPZGFVF8ceAtnp
Dos Monos
Twitter https://twitter.com/dosmonostres?lang=ja
https://soundcloud.com/dos-monos