
近年、ピラミッド型の組織とは異なる、独立した個々が集まったフラットなコレクティヴ/コミュニティやその時折でメンバーが変わるアメーバ型の共同体が増加している。一つの価値観を通底させる軍隊型を原型とするピラミッド型では生まれえない、個々の価値観やアイデンティティを尊重することでアイデアや拡散力を発揮するフラットな共同体について、その発足から活動、メンバーの思いなどを伝えることで、様々な未来の形を想像させる「& Issue」。第2弾は、世の中の当たり前に違和感を問いかける「IWAKAN」編集部へのインタビュー。編集長不在という従来のメディアの組織図とは異なるあり方で制作を続ける編集部のエド・オリヴァー、ジェレミー・ベンケムン、Kotetsu Nakazato、蔭山ラナに、コミュニティの作り方から制作の進め方などを聞いた。
――最初に「IWAKAN」の成り立ちから教えてください。Creative Studio REING(https://reing.me/about)が母体となって始まっているんでしょうか。
エド「REINGはジェンダーの視点から企業と一緒にインクルーシヴな広告やイベンドなどいろんなクリエイティヴのコンテンツを制作している東京のクリエイティヴスタジオで、『IWAKAN』編集部の中では私と(ユリ・)アボが所属しています。REINGの仕事も楽しいのですが、企業と一緒では完全には自分たちがやりたいことはやれないので、120%自分たちを発揮できるコンテンツを作りたいと常々思っていました。それが『IWAKAN』という形になりました。成り立ちとしては、2019年の3月に私が新しいプロジェクトの企画担当になった時に、Kotetsuが誰かと一緒にクィアのマガジンを作りたいという趣旨のストーリーをあげていたのを見て、REINGでやらないかと誘ったのが始まり。クィアマガジンを作ろうというこのプロジェクトを社内で通してすぐにアボも入ってくれて、親友で元々クィアの映画イベント『Purple Screen』を一緒に開催していたジェレミーも巻き込んで、2020年5月に4人で『IWAKAN』をスタートさせました。既に自然に隣にいた仲間たち4人で始めて、アボの友達の響(ひびき)ちゃんがPRに入ってくれて、ラナも入って、3号目の制作時には編集部は6人になっていました。今は響ちゃんが忙しくて入れないから5人で回してます。
『IWAKAN』はProduced by REINGとなっていますが、それは編集部の中にREINGに所属している私とアボがいるからというだけ。上下関係は全くないし、REINGのメンバー同士もフラットだし、私たちの活動を応援してくれています」
――自然に隣にいた仲間と始めたということですが、この人となら一緒に制作をできると思ったきっかけなどはありますか。
ジェレミー「面白いことに、創刊メンバーの中で雑誌編集の経験がある人はKotetsuしかいなかったんです。だからスキルではなく、ただこういうテーマに情熱があって伝えたいことがある人が集まっているんですよね」
エド「ジェレミーが言った感覚がこのチームにおいては一番大事でした。世の中にある雑誌は多くが編集部も読者も同じ意見で、議論や考えさせる内容というよりはその同じ考え方であることを前提とした内容を伝えているように感じます。でも『IWAKAN』は部員それぞれがクィアだったりシスジェンダーでヘテロテクシャルのフェミニストだったり全く違う視点を持っている。だからこそ多様な視点でジェンダーを語れるし、このメンバーだからこそ読者も編集部と同じくらい多様なんだと思います」
Kotetsu「Kotetsuは元々『Purple Screen』にも参加していて、ジェレミーやエド、REINGが考えていることを事前に知っていたから、そこに対してのリスペクトや共感が大前提としてありました。だからエドが一緒にやろうと言ってくれた時にもREINGと一緒なら作れると思ったし、ヴィジョンや見たい景色の共有を事前にできているという信頼がありました。ラナや響ちゃんという後から入ってくれた人たちの活動についてはそんなに知らなかったけど、『IWAKAN』というマインドがある程度できた時に入ってくれたということはそこに対して共感してくれてるということ。それだったら一緒にできるなと」
ラナ「私はメンバーで唯一の読者からの参入で、2021年5月に3号目の制作から入りました。元々ジェンダーは興味のあるテーマで、大学で文学におけるセクシュアリティ表現の検閲について研究していました。『IWAKAN』の1号目が出た時に高円寺のtata bookshop & galleryの展示会に行って、自分が研究している検閲の時代とは100年違うながらも、こんなにありのままに大胆に表現していることは自由で格好いいなと衝撃を受けたんです。読者としては、自分が表現しにくいことを『IWAKAN』が言語化、作品化、雑誌化してくれたような感覚で、読者層を限定せずに多様な人に手を差し伸べる姿はすごく面白かった。そこで版元になっていたREINGのアシスタントと『IWAKAN』の編集部員として活動するようになりました」
――クィアのマガジンを作るというスタートだったということですが、Kotetsuさんはなぜ「雑誌」という形にしたかったんですか。
Kotetsu「個人的にずっとzineを作っていて、zineならではの良さもあるけど、届く範囲だったり与えられる影響力に限界を感じ始めていた時だったんです。なので、zineではなく流通範囲が広い『雑誌』にこだわりました。紙媒体にしたかった理由は、今当たり前とされている景色を変えたかったから。書店は自分たちの暮らしの中に当たり前にある風景ですが、その中にクィアとして生きている自分たちの存在は全くないものとされている。だからこそ、自分と近いアイデンティティを持った人たちや、世の中で当たり前とされていることに違和感を感じている人たちがフラッと入った書店で『IWAKAN』という雑誌を目にすることによって、自分たちの存在が当たり前の風景の中にあると証明できるようにしたかったんです。そのためにはウェブではなく、雑誌という形が必要でした」
エド「そう、フィジカルの景色を変えたかった。オンラインにはなんでもあるけど、雑誌を作ってみて、紙媒体にはいろんな力があるんだと気づかされました。例えばある女性がジェンダーに関するモヤモヤを彼氏に話したけど、彼氏はそれは社会がおかしいのではなくて、あなたがおかしいだけと言っていたそうなんです。でもその子が『IWAKAN』を見つけて、彼氏に『私だけじゃない、雑誌になるくらい同じ感覚を持ってる人がいる』と伝えられたと。そういう風に、この雑誌に救われたり、自分のツールとして使っているという話が編集部にたくさん届いています。オンラインは遠くや様々なところに届くという利点があり、紙媒体である『IWAKAN』は地方にまだしっかりとは届いてないけれど、紙媒体ならではの深い繋がりができていると思います」
ジェレミー「ウェブは素晴らしいし、豊かな所になってもいるんだけど、調べていることと関連あることしか見えず、たまたま自分の意見と反対のものと出会うということがほぼない。自分の方向に沿った物しか出てこないんですよね。だけどフィジカルになると、偶然の出会いができる。先週ラナと僕はzineのフェアに出ていたんですが、こういうテーマは全然話されてないと思っていた時に偶然『IWAKAN』を見つけて衝撃を受けたという人がいました。ジェンダーやセクシャリティの問題に関心がない人にも偶然に届く可能性があるんです。ウェブはスピーディで次々に記事が更新されていくけれど、物は残っていくし、人にも渡せるし、心の違うところに接続される気がして、物質的なものにしたかったというのはあります」

――結果的にクィアマガジンではなく、ジェンダーを主軸としながらも政治や様々な社会問題に至るまでを取り上げる内容になっています。その内容はどのように決めていったんですか。
ジェレミー「最初の1ヶ月間くらいは、何を作るのか、誰に向けるのか、何のために作るのかといったことを4人でひたすらディベートし続けました」
Kotetsu「本当にクィアマガジンでいいのかな、これってクィアのためだけの雑誌なのか、そうじゃないよねという議論を4人でたくさんして、みんなで中身を決めていったよね。1号目から3号目までの間にも『IWAKAN』らしさみたいなものは変化していってると思うし、定義づけるつもりもみんなないと思うけど、芯にあるのは、ジェンダーやセクシャリティのことで当たり前とされているものに対して違和感を持ったり、声をあげたり、表現したりすることの大切さだと思います」
ジェレミー「毎号コンセプトは変化するけど、変わらないこととしては、今まであまり聞こえなかった声を届けていくこと。あと、批判するより何かを問いかけたいという姿勢。答えを出したいというわけではなく、いろんな情報を発信していくことによって、みんなが自分で意見を作ることができればいいなと」
エド「そういう想いを、表紙のデザインやタイトルに反映させています。ゲイマガジンだったらゲイのセレブを表紙に載せてという感じだけど、それだとその人やそこに興味がある人しか手に取ろうと思わないから、『IWAKAN』は格好よくて抽象度が高い表紙にして、パッと見では何かわからないけどオシャレで面白そう、みんなが手に取ろうと思えるようなものにしたんです」
――具体的なテーマ決めやページ割りなどの進行はどのように?
エド「毎号の決まった記事のようなものはなくて、毎回メンバーがその期間に社会に必要だと思うコンテンツや気になっている文脈を個々で持ち寄るところから始まります」
ジェレミー「『IWAKAN』は編集長がいないフラットな組織だから、誰か一人の意見で決定ということではなく、一人のアイデアをみんなで共有してさらにブラッシュアップしていく形。ブレストは必ず毎週一回はやっていて、いつも本当に勉強になっています。具体的な流れとしては、最初にみんなでその号の大きなテーマやコンセプトを決めて、その次にそれぞれの担当コンテンツを決めて、そこから個々人で記事を作っていきます」
Kotetsu「企画を作ってきた人が基本的には担当編集になるので、各自の裁量も求められるし、持ち込む企画によって担当量の差が出る場合もあるけど、その人に任せきりにはせず、話し合いながら助け合いながら進めていて。誰も一人で作っているという感覚にはならないし、させない。みんなで話し合って同意を得て進めるという感じだから、ペースはどうしてもスローになるけど、『IWAKAN』にはこのやり方が合っていると思います」
エド「そうだね。話し合いつつも、それぞれに自分のタスクはしっかりやってる感じ。大事なのはやっぱり信頼関係。自分が出したアイデアに対してもう少しこうした方がいいと言われても、信頼してるから嫌じゃないし、みんなのアイデアを受けてどんどんいいものを作っていけるんですよね。さっきKotetsuが話したように、ヴィジョンが一緒だからこそフィードバックしやすい環境になってると思います」
Kotetsu「みんな本当に考えてることもセンスもバラバラだから、話し合いが大変だと感じることもあるけど、ジェンダーの問題は一つの指針があるわけじゃないから多様な声を聞くべきだし、ここに6人しかいなくても6人の考えがあるから、それをなるべくそのまま届けるようにすることは絶対に必要な作業。それに、組織が様々な声を活かす努力をしないということは、排除する社会を作ってしまうことに繋がる。だから時間がかかっても話し合いをやめたくない」

ーーまさにそれが民主主義の土台ですよね。『IWAKAN』にはアーティストから研究者まで幅広い方たちが出演していますが、出演者とのコミュニケーションで心がけていることは? また、読者とのコミュニケーションに関しても同様に教えてください。
ジェレミー「編集部員によっても、アーティストによっても接し方は異なるかな」
エド「そうだね。ただ出演者に対しては、リスペクトを持って丁寧にやり取りすることは基本だと思います。コンテンツを出すときに必ず何回も確認してもらって、修正がないか、写真の使い方は大丈夫かなど、後で落胆させたり驚くような事態にはしない。アーティストの意見を尊重しながら進めます。読者に関しては、『IWAKAN編集部は格好良い、正解』という風にはならないように気を付けています。私たちも正解がわからないからこそこういう雑誌を作っていて、反対意見でもなんでも意見を聞きたい。みんなと距離感を近づけたいし、編集部内だけじゃなくて読者ともフラットでありたいんです。だからいつもアンケートを入れているんですよね。自分たちの声だけだとつまらないし、自己満足になってしまうから、みんなの声を入れることはとても大事にしています」
Kotetsu「エドが言ったように、編集部の答えを示しているわけじゃないから、もちろんその人の回答が『IWAKAN』のどこかで見つかったら素敵なことだけど、探究し続けてほしいし、一緒に探究したいなと思います。新しく関わってもらう出演者に関しては、事前にお会いできたら嬉しいけど、会えなくても大好きな状態で取材できるように一生懸命調べるかな。『IWAKAN』と関わる誰もが嫌な思いをしてほしくないし、リスペクトされていないと感じてほしくないし、関わってくれた人たちの尊厳を守れるような対応を心がけています」
ラナ「私は主にセールス・PRを担当しています。書店さんに『IWAKAN』を案内する時は、店主が第一の読者となります。だから書店ごとにどのような本を置いているのか、どのようなコンセプトを持っていのかをリサーチして、そのお店が持つ様々なテーマの中から『IWAKAN』と一番合いそうな提案を探すのもコミュニケーションの一つだと思っています」
――みなさんは他に仕事を持ちながら『IWAKAN』を作っているそうですが、『IWAKAN』におけるビジネスとクリエイティヴのバランスに関してはどのように考えていますか。
ジェレミー「それぞれに考え方が違うと思うけど、僕はフォトグラファーだから仕事自体がかけ離れてはいないんです。『IWAKAN』でビジネスができたらそれは素晴らしいだろうけど、元々紙媒体の雑誌はお金が得られる業界ではないですよね。それにスポンサーや広告が入ることで表現の自由がどれくらい残るかわからないから、インディーズで自由にやっていたい気持ちの方が強いかな」
Kotetsu「REINGと一緒に企業案件をやったりすることで、『IWAKAN』では自由に制作できるようにバランスを考えてもらっています。Kotetsuも食べていくために創作しているわけではないので、難しいけどバランスをとってやっていけたら」
エド「答えになるかわからないし、これを理解できる企業は少ないかもしれないけど、REINGにとって『IWAKAN』はお金を稼いでいない、だからビジネスになってないということにはならないんですよね。インディーズマガジンを作っていろんなアーティストと出会えることで、REINGでの仕事にもその人脈を持ち込めたりというアセット(有用)になっている。クリエイティヴとお金を秤にかけてどちらかを犠牲にするのではなく、考え方次第でどちらも活かすことはできると思います」
ジェレミー「そう、こういう取材もREINGのマーケティングになっているしね」
――アートやクリエイティヴの重要度が高いとされてる国では本当にごく当たり前にその考え方がなされているけれど、日本では文化にも即時的な利益や効率を求める企業が多いので、その考え方がなかなか通りにくいですよね。
エド「80年代の日本の経済ではクリエイティヴが優先されていましたよね。それは自由に作ってもお金が入ってきていたから。でも今は失敗が許されないから、決まりきったクリエイティヴしか作れない」
ジェレミー「話が逸れるかもしれませんが、少し前に2年ぶりにフランスで過ごして戻ってきて、日本での売り物としてしか扱われていない“文化”に改めてショックを受けたんです。みんなのものであるはずの文化が売るためのものになっている。ギャラリーという看板をつけているけど、現代アートと呼べないようなものに文化やアートという言葉を使って、スーパーマーケットのように売ろうとしているだけの場所もある。そういうものを見ると傷つく。この傷つく感覚も忘れていたなって。
僕が生まれ育ったフランスは26歳まで美術館は無料で、誰でも入れるようになっています。そうすると、友達と家でブラブラするより綺麗なルーヴル美術館でブラブラしようとなる。文化へのアクセスがみんなに開かれているから、たくさんの作品を見たり、映画を観たり、本を読んだりすることで違う意見を持ってることが自然に思えてくるし、知らないことを知りたいという好奇心が高まって、意見が違っていても話せるようになったりと、いわゆる多様さを自然と吸収できる土台ができてくるんです。また、文化を応援するために企業がお金を出したら税金が免除されるという法律があるので、アートに元々興味がなかった企業や人でも美術館に寄付したり、アートを買ったり、アートのプロジェクトを立てたり、人生の中で文化に何かしら触れるような仕組みになっていて、そこが入り口になってさらに興味を持ったり違う考えに触れたりできます。
でも日本では文化がみんなのものではなくビジネスになってしまっているから、お金にならないなら文化的なことをやる必要がないと言われてしまう。自分は2年間こんなに文化のない生活してたんだとショックでした。しかも日本は本来とても豊かな文化を持ってる国なんですよね。でも綺麗な庭園を見に行きたいならお金を払わないといけない。政府の文化ではなく、これは自分たちの文化なのだから、なぜお金を払わないといけないのかという疑問を持った方がいいと思う。文化へのアクセスが特権的になっているし、興味深い意見を持っている人もいるのに語る場所がないし、本当の意味で文化が大切にされていないなと思います。それは政治にも言えます。若者は政治に無関心と言われているけど、政治の情報にアクセスできないようになっているから必要性もわからないだけなんですよね。文化や政治が大切にされていない国が今後どうなっていくのだろうと考えてしまいます」

――本当に様々な垣根が張り巡らされていると思いますが、その垣根に気づくための情報にもアクセスしにくい。だからこそ『IWAKAN』では根本の問題である“政治”というテーマを取り上げたわけですよね。最後に、この記事を読む読者の中には、自分が望むコミュニティを探したいけどどうやって出会ったらいいかわからないという人たちもいると思います。みなさんが自分が欲するコミュニティに出会うまでにどういう動きをしていたかを参考までに聞かせていただければ。
Kotetsu「Kotetsuは自分の作品を作っていたから、自分の想いや伝えたいことが100%含まれた何かを作れたら、その作品が自分をどこにでも連れてってくれるし、色んな人に出逢わせてくれると思います。Kotetsuが足を運んで会いに行った人ももちろんいるけれど、創作したものからKotetsuの考えに共感して会いに来てくれる人たちもいました。でもそれは何か作品を作れる人に関して言えることであって、作品を作れるという特権性もあるから、一概にすべての人に当てはまる方法とは言えないですが」
ジェレミー「僕も作る側だったから、他のアーティストとは展示会などを通して自然にコミュニティができました。例外的かもしれないけど、『Purple Screen』を作った時によく参加してくれていた人たちも友達になってコミュニティができたし、その人たちが新しくプロジェクトをやり出したりしてる。だから興味が近いイベントに参加することも大事かな。興味があっても誰にも話せない、または話さない中ではコミュニティは作りにくいと思うから、興味があるものについて話せるようになる方が本当はいいんだろうと思います。そのせいで距離ができる人たちもいるかもしれないけど、同じ興味を持ってる人はいつか近づくはず」
ラナ「私がまさにそうで、クリエイターじゃないけど、たまたま『IWKAKAN』の展示に行ったところから始まっているから足を運ぶことは有効だと思います。私はコミュニティと呼べるほどのものは持っていないけれど、仲の良い人たちとはお互いの悩みや学びを共有することも多く、高め合う場所がある。自身のことや関心があることを話せる環境に身を置けるようになれたら自然と人も集まるし、自分も引き寄せられると考えています」
エド「難しいけど、自分を100%隠さないことでその自分を好きな人が自然と集まってくると思うから、よくある言葉になるけど、素直でいることが大事かな。私がREINGというコミュニティと出会ったのも、別の会社で働いていた時にREINGの社長と仕事で会う機会があって、その時にメイクもネイルもした自分らしい状態で会ったことで、エドをクィアだと気づいて声をかけてくれたんですね。自分を素直に出していたことで、エドを好きな人が声をかけてくれてコミュニティに入ることができたから、何かシグナルを出した方がいいかなと思います」
Kotetsu「もし自分が今いる環境で自分の好きなものや違和感を感じてることを言えないなら、そこから逃げていいと思います。そこに居続けて違和感を消したり、覆いかぶされたりするくらいなら居続ける必要はないし、そこから逃げて『IWAKAN』を居場所にしたらいい。でもどうしてもその環境に留まらなくてはいけない場合、その人が頑張るんじゃなくて、メディア側だったり行政が情報を届けに行くべきなんですよね。『IWAKAN』や例えばNetflixなどに辿り着ける人たちは環境に恵まれていたり、検索ができる状況にいるけど、検索履歴が残ることに対して恐怖心を抱いていたり、パソコンや携帯を持ってない人もいるから、どれだけメディアやコミュニティ、もしくは国などが格差なく多くの人々に寄り添えるかだと思います」
――確かに誰にでも情報と選択肢が与えられるべきで、そのためには国や行政などが率先して動くべきなんですよね。それができていないなら発信する側から動くと。
Kotetsu「はい。そのためにも『IWAKAN』ももっと地方に行きたいなと思っています。4月中旬を目処に4号目を出す予定ですが、47都道府県全部に置いてもらえるように、ちゃんと足を運んで届けていきたいです」
エド「『IWAKAN』のウェブサイトも公開されたので、雑誌、ウェブ、イベントと多方面から届けていけたらいいなと思います」
photography Marisa Suda(IG)
text Ryoko Kuwahara(IG)
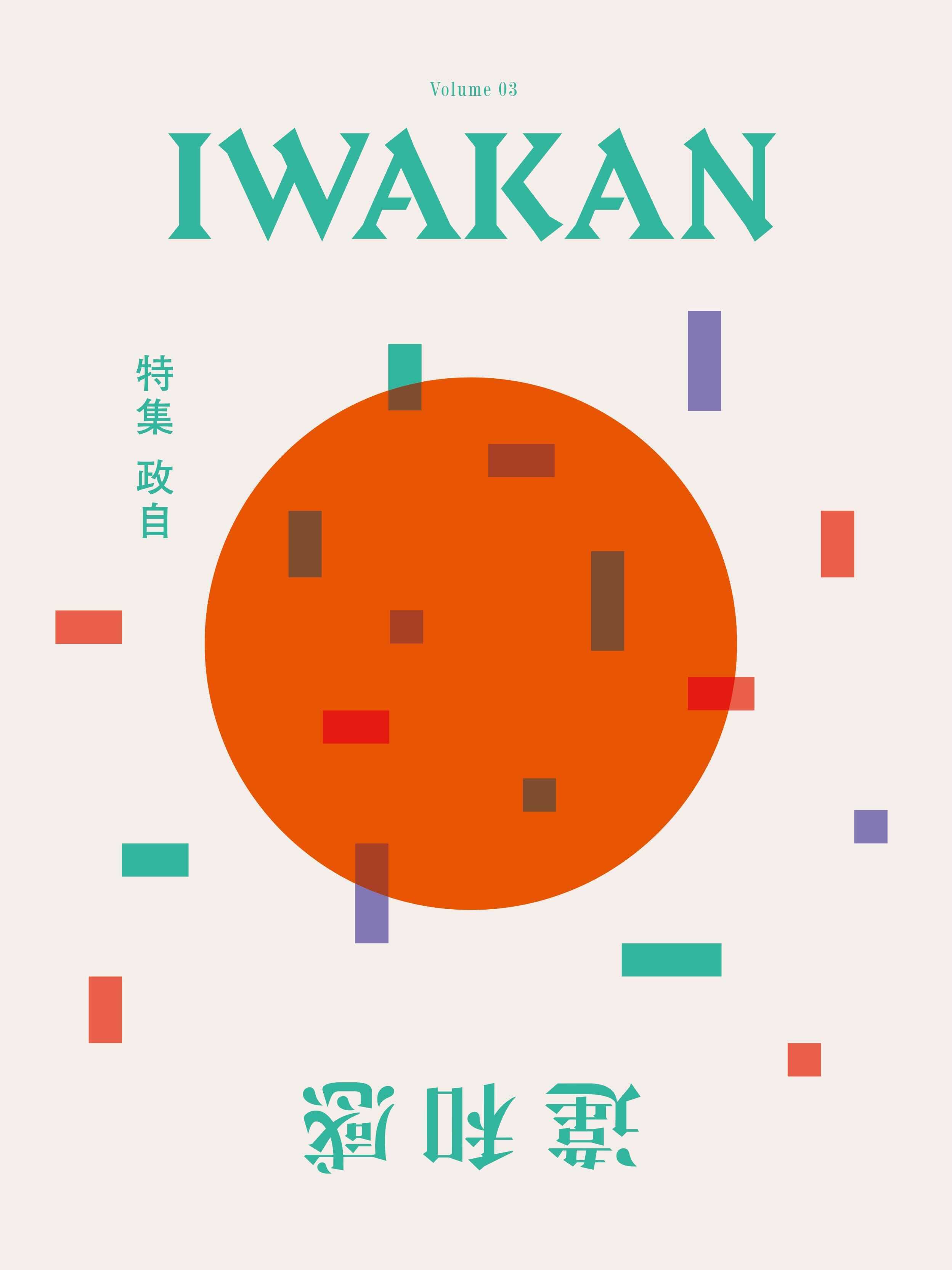
『IWAKAN』
世の中の当たり前に“違和感”を問いかけるマガジン
https://iwakanmagazine.com
https://www.instagram.com/iwakanmagazine/
https://omnilink.iconosquare.com/page/iwakanmagazine
https://store.reing.me/items/51392883






























