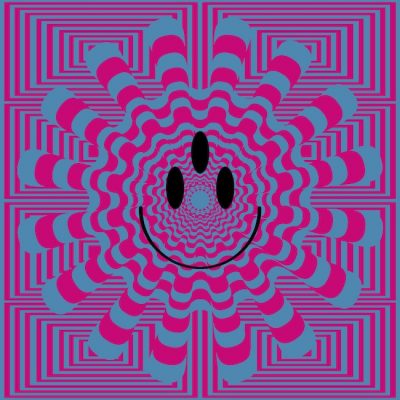1970年代後期、ソ連占領下のエストニアでの二等兵セルゲイとパイロット将校ロマンの実際の愛を描いた『Firebird ファイアバード』。エストニアにおいてLGBTQ +映画として初めて一般劇場公開された本作は大きな反響を呼び、公開から2年後に同国議会で同性婚法が裁決、2024年1月に施行。エストニアは、バルト三国はもちろん、旧ソ連圏では初、世界で35か国目の同性婚承認国となった。
その立役者であり10数年に渡るロビー活動の末に同性婚制定を実現させたペーテル・レバネ監督、セルゲイ役で共同脚本・プロデューサーを兼ねるトム・プライヤー、ロマン役を演じたオレグ・ザゴロドニーが2月9日の日本公開に合わせ来日。本作に感銘を受けた美術家・建築家のヴィヴィアン佐藤が3名にインタビューを敢行し、映画と社会の結びつきやあるがままの自分であることについてなどを語り合った。
――この映画を作るきっかけになったのは、セルゲイさんの回想録を読んだことだそうですね。どうして映画にしたいと思われたんですか。
ペーテル監督「彼らの物語は大変な悲恋ですよね。そのヒューマンドラマ的なところに魅かれたのと同時に、冷戦下のソ連であのようなことが起きていたことに信じられないくらい衝撃を受けたんです。そしてこれがLGBTQの物語としてもすごく稀少なものであるとも思いました」
――だからか2人の出会いの場面の影の映り込み方や背景に至るまでの撮り方や演出が、昔のダグラス・サークの作品などを思わせるような、あえてメロドラマな形をとっているように思いました。
監督「そうですね。今はむしろメロドラマ的なものを控えている作品が多いですが、僕はどちらかというと、思いっきり表現するメロドラマの感じが好きなので、努めてそういう演出をしています」
――先ほどソ連圏という話が出ましたが、今作は単純に優れた作品というだけではなく、実際に映画が媒体となって旧ソ連圏内で初の同性婚の認可へと社会を動かしたり、社会と繋がるようなことを実現しています。
監督「そもそもなぜ我々が映画を作るのかというと、ストーリーを介して、人々の世の中に対する視点を少しでも変える作用となれればという思いがあるからなんです。おっしゃるように、この作品が公開されたことで僕の母国のエストニアでも社会に変化が起こり、今年は同性婚が合法化されました。僕は2010年から友人と2人でLGBTQのアクティヴィストとしてロビー活動をしてきているんですが、2013年にパートナーシップ制度が成立し、そしてようやく同性婚が合法化した。これは誰しもが想像できなかった快挙で、そういう風に社会が少しずつ開かれてきたのは嬉しいし、これからもさらに変化が広がっていくように願っています」


――オレグさんは元々モデル出身ということですが、ご自身でブランドを運営していて、その収益を兵士へのサポートに充てているそうですね。
オルグ「ええ、ユニフォームを提供するという活動をしています。前線で一番問題になっているのが、着替えがないということなんです。ユニフォームの支給にもルールがあり、ズボンであれば1着を6か月間使わないといけない。もし破損すれば書類で申請し、その許可が降りなければ入手できないんです。でも生か死かの戦いを繰り広げている中で、そんな煩しいことをやっているわけにはいかないですよね。実際に戦地に立っている友人から、新しい着替えがないという問題や、着替えられたとしても数週間に1回程度という話を聞いて、僕がなにかしなければいけないと感じたんです。この作品で僕自身も世界から注目を集めているということもあるし、身近には衣服を作れるような人たちもいる、じゃあ行動を起こそうと声を大にして訴えてみたら、生地などを寄付してくれる方も出てきたんです」
――ファッションをメディアにして社会を変えていく活動をしているのは素晴らしいなと思います。日本はLGBTQに対する意識もすごく低いんですね(OECDの性的マイノリティに対する法整備35カ国中34位/ジェンダーギャップ世界125位)。そして、アートや映画が社会にあまり影響を与えないというところも特徴であり、残念なところなんです。
ペーテル監督「日本に来る前に少し調べたんですが、LGBTQをテーマとした日本映画は、現在活発に作られているのでしょうか」
――あることはありますが、社会に影響を与えるようなものにはなっていません。それはアート全般に言えることかもしれないです。例えば、フジロックのような大きなイベントで政治に対して発言する人がいると、フェスに政治を持ち込むな、音楽と政治を一緒にするなという批判があったり、そもそもロックの成り立ちみたいなものをわかっていなかったり、文化全般に対しての意識が独特です。
ペーテル監督「それは非常に興味深いですね」


――プライヤーさんはこのコロナ中、南極やブータンなど多くの国へ旅をたくさんしていたみたいですけど、その旅は今も続いてるのかしら。
トム「旅は続いています。イギリスを10月に離れてからほとんど帰っていなくて、チュニジアに1ヶ月、バリに1ヶ月いた後に1週間だけイギリス帰って、台湾やタイで1ヶ月過ごして、日本に来ました」
――他のインタビューで読んだんですけど、写真家のメイプルソープが今まで見たことがないものを見に行くことが大事だと言っていたことからそれを実践されていたり、マイドフルネスや瞑想も実践されているそうですね。
トム「“現実を問いただす”というようなことに昔から興味があるんです。2023年の1月頃、精神的に迷子みたいな状態になっていたんですね。僕たちはこんな物質社会を生きるために生きているわけがないと悩み、そこからいろんな深い問いが始まったんです。それで瞑想やいろんなプラグラムをやってみて、自分たちが今生きている現実を問いただし、この世に生み落とされた意味ややるべきことは何なのかということを考えていました。それらのマインドトレーニングを通じて、自分たちと自分たちの考えとはイコールではないという気づきに行き着いたんです。自分たちの考えは集合意識によってプログラミングされたものであって、そこから離れて、今この瞬間を生きるべきだと」
――日本は自然災害が多く、痕跡を残さないが故に生まれたものの哀れや侘び寂びといった美学、森羅万象に神が宿るという文化がありますが、もしかしたらそうした文化にもご興味あるかもしれませんね。
トム「まさに。感覚として共鳴するものがありますし、日本の文化に自分が色々と問いをたてていることのヒントがあるような気がしているんです。神は自分たちが目にする全てのものに宿る、なぜなら自分たちのマインドの中にあるものだから。そう考えると、他者と自分とが同じ一つのもので、攻撃すれば自分に返ってくるし、愛を与えればそれもまた自分に返ってくるという気づきに行き着く。これは共時的でもあるし、量子物理学的な話にもなるので長くなるな、また別の機会に話しましょう(笑)。
とにかく今は、この探求の旅がどこまで続くのかわからないけど、どういう発見が待っているかなとゆらゆら身を委ねて流れているところです。この旅でこれまでになく平和でハッピーな気持ちになることができたし、自分はこのままでいいとも思えました」
ーー共時的というところで、本作もセルゲイさんの回顧録や写真から立ち上がってくる血流のようなものが現代に流れているとも言えます。
ペーテル監督「その側面は確かにあると思います。私たちも、これは過去のエネルギーを現代に生きる自分たちの中に蘇らせたという感覚で作っていたのかもしれないです。あるいはセルゲイの当時のエネルギーをこの作品に照射したのかもしれない。でもそれはこの作品に限らず、どんな映画を撮るにしても、それこそ何をするにしても同じことですよね。床の掃除だって、誰かに料理を提供するのだって、私たちは何かしら自分が感じ取ったものをその行為の中に注入している。この映画でも同じことをやっているんだと思います」


――ロラン・バルトによるストゥディウムとプンクトゥムという概念にも通じるお話だと思います。最後にこの作品を作ったことでの変化、そして日本でどのように観てもらいたいかをおうかがいしたいです。
オルグ「こうやって日本を訪れて街中を行き交う人々を見ていると、ファッション一つにしても自由にコミュニケーションを取り合ってる感じを受けたんですね。それは素晴らしいことだし、そうした自由な自己表現、自分のありのままでいるという姿勢を維持してもらいたいなと思います。
そして自問自答もしてほしいんです。本当に私はこの場所にいて、自由にありのままの自分を生きられているのだろうかと。もしそうでなければ、あるいは、もうちょっと社会にこうなってほしいと思うのであればこの映画のように大いに戦ってもらいたいです」
ペーテル監督「この映画を作っての変化は、自分に自信を持てたことですね。今までは、脚本を書くにしても、ストーリーについても、人からフィードバックをもらっていたんですが、この経験を通じて自分の直感を信じていいんだという確信を得ました。今までは音楽やドキュメンタリーの仕事をしてきたのですが、長編監督としても自信が持てましたね。
日本の方にどう受け止めてほしいかということですが、本当に純粋なラブストーリーとして観ていただきたいです。同性愛であり、異性愛であり、あるいは三角関係でありますが、愛というものには変わらないんです。そして、この映画は、私のための映画じゃないと思っている方にこそ観てほしい。エストニアでも意外な層の方たちが賛同してくれましたが、そういう風にこの映画が皆さんのインスピレーションになれれば、そして心の赴くままに自分の真実を生きることができるための掛け声になればと思っています」
トム「僕は撮影前と後でマインドセットがすっかり変わりました。元々は主役を務めるというところから、共同脚本、そしてプロデューサーを務めることになり、撮影開始前の数ヶ月間には一瞬自信をなくしてしまったこともあったんです。僕は果たしてこの作品を担ぐことができるのだろうか。役者として務まるのだろうかという疑念が湧いてしまった。今回は肉体も整えないといけない撮影だったので、そういう面でもすごく怖くなってきてしまったんです。でも、自分の中にある『できないかもしれない』という疑念や不信感に思いっきり立ち向かって、果敢に飛び込んでいきました。 幸い優秀な制作陣が揃っていて、みんなが一丸となって取り組んでくれたので、乗り越えることができた。このヒーリング的な体験を通して、自分の中にあった不信感やストッパーを全部取っ払って、可能性を信じることができるようになったんです。
観客のみなさんには、ロマンとの旅路を一緒に歩んでくださいと伝えたいです。愛を知ること、そして愛を禁じられること、それでも愛を信じて心の赴くままに歩んでいったその旅路を、別れも含めてセルゲイと一緒に体験をしてほしい。ロマンがセルゲイに宛てた手紙は、実際の手紙を一語一句そのままに記しています。『いつも僕は君とともにいる』という言葉を受け取ったセルゲイは、ロマンの死を弔いながらも、一縷の希望を携えて、涙を流しつつもあの笑みを浮かべるんです。それは愛を信じる心に他ならないと僕は思います。愛は他者だけでなく、自分の中にもあるんだという、その気づきがあの笑顔になっているんです。そこをぜひ観てもらいたいです」

photography Marisa Suda(https://www.instagram.com/marisatakesokphotos/)
interview Vivienne Sato(https://www.instagram.com/viviennesato/)
text Ryoko Kuwahara(https://www.instagram.com/rk_interact/)
『Firebirdファイアバード』
新宿ピカデリー他にて全国公開中
www.reallylikefilms.com/firebird
ペーテル・レバネ監督・脚色作品 共同脚色 : トム・プライヤー / セルゲイ・フェティソフ 原作 : セルゲイ・フェティソフ
出演 : トム・プライヤー / オレグ・ザゴロドニー / ダイアナ・ポザルスカヤ
[ 2021年 | エストニア・イギリス合作 | 英語・ロシア語 | 107分| 1.85:1 | 5.1ch | DCP & Blu-ray ]
配給・宣伝 : リアリーライクフィルムズ 日本語字幕翻訳 : 大沢晴美
© FIREBIRD PRODUCTION LIMITED MMXXI. ALL RIGHTS RESERVED / ReallyLikeFilms