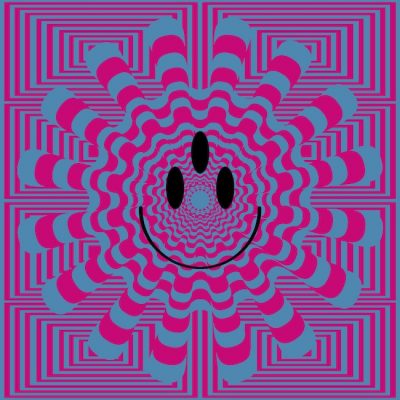最近、アメリカの最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーグに迫ったドキュメンタリー映画『RBG 最強の85才』の日本版ポスターに「妻として、母として、そして働く女性として」というキャッチコピーが書かれていた、という記事を読みました。最高裁判事の地位にまで上りつめるという業績をもってしてもなお、女性はひとりの人間として評価されず、「女性であること」「女としての役割」に縛られるのか、と暗澹たる気持ちになります。
女性の生き方は、つねに他者との関係において決まるものとされてきました。だれかの娘であり、だれかの妻となり、だれかの母となること。他人に(とくに男性に)気に入られること。それが唯一の幸せとされていた時代はとうの昔に終わったはずなのに、女性はいまもなお、ひとりの人間として見られ尊重されることをめざしてもがいている状態です。
女性の身体も同じように、つねに他者に定義され、あるべき姿を決められてきました。美醜を判定され、性の対象とされる一方で、汚れたものともみなされたり、「産む機械」とまで言われたりする。それがいま、世界中で変わってきています。この記事では、他者に定義される女性の身体の問題や、女性の自己決定権をテーマにした書籍を、スウェーデンをはじめとする北欧から紹介したいと思います。

Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd
(モア・マッティンソン『女たちと林檎の木』未訳)
まずは、1933年に発表されたこの作品。スウェーデンのプロレタリア文学を代表する作家のひとり、モア・マッティンソン(1890〜1964 )のデビュー作です。
貧しい労働者階級の暮らしを詳細に、リアルに描いたこの作品は、19世紀に生きたふたりの女性を描いたプロローグで幕を開けます。大きな農場の夫人で、子ども15人の母親であるソフィーは、女友だちのフレドリカと毎週金曜日に洗濯小屋で入浴する習慣があり、これが騒ぎを巻き起こした、という話です。ここで印象的なのが、ソフィーの身体の描写です。 小柄で痩せ細った身体、その瞳は美しく、「力みなぎる、揺るぎのない女の顔」にしわが刻まれています。15人の子どもたちを育ててきたせいで乳房は垂れ、腹は度重なる妊娠のためついた跡だらけ。マッティンソンはそんな彼女の裸体を「人生そのものを刻みこんだルーン石碑に似ている」としています。優しく、敬意に満ちた視線だと思います。
それから時は流れ、20世紀初頭、それぞれソフィーの血を引きながら互いの存在を知らずに育ったふたりの女性、エレンとサリーが出会って意気投合します 。どちらも貧困にあえぎ、酒浸りの夫とたくさんの子どもを抱えて、助けあいながらたくましく生きていくのです。『女たちと林檎の木』は、このふたりの奮闘を通じて、女性の身体だけでなく、その性欲、妊娠、つわり、出産、閉経などについても自由に、リアルに描き切った、当時としては画期的な作品でした。
当時、女性の身体や性について書くのは男性作家の仕事で、女性の身体を、豊満で美しく、男性を誘惑するものとして描くことが主流でした。そんな中でマッティンソンが書いたのは、現実の女性の身体やセクシュアリティーを前面に出した作品でした。『女たちと林檎の木』の刊行当時、ある男性批評家は、マッティンソンの才能を認めながらも、この小説を「陰部を出発点にした描写ばかり」「下卑ている」と批判したそうです。女性の身体や性のあり方を、男性が決める時代だったということですね(いまもそうかもしれません)。そんな時代にマッティンソンは、まさに「陰部を出発点に」して、女性の身体を持って生きるというのがどういうことなのか、現実を突きつけてみせたのでした。
『女たちと林檎の木』はまた、出産の場面をリアルに、つぶさに描いた、スウェーデンで最初の作品だとも言われています。サリーが自宅でたったひとり、幼い子どもを起こしてはいけないと声を殺しつつ出産する場面です。陣痛のリズムを再現した文章は圧巻で、読者は女の身体から赤ん坊が、血やら羊水やら胎盤やら、あらゆる分泌物とともに出てくる場面に立ち会うことになります。壮絶な苦しみの末、産まれたのは男の子で、サリーはぼろぼろになった状態で微笑みます。「この子は子どもを産まなくてすむ」。批評家の男性たちがおののくのも無理はないのかもしれません……
2019年初め、スウェーデンではモア・マッティンソンに関するドキュメンタリー映画が公開されました。トップの映像はその予告編です。マッティンソン自身、5人目の息子を自宅の台所でひとりきり出産するという経験をしています。この予告編の中では、文学研究者エッバ・ヴィット=ブラットストレムがこのできごとに触れ、“マッティンソン自身の書いたものによれば、おそらく家庭内レイプの結果できた子ども” “その意味で、彼女は#Metoo運動の先駆けと言える”と述べています。
英語版 Amazon

リーヴ・ストロームクヴィスト
『禁断の果実』
翻訳:相川千尋
(花伝社)
リーヴ・ストロームクヴィストはスウェーデンを代表する漫画家で、この作品では、歴史を通じて社会が女性器や女性のセクシュアリティーをどのように考えてきたかを、ユーモアたっぷりに描いています。大いに笑えるギャグコミックですが、内容はとても深く、女性のセクシュアリティーのありかたを男性が決めてきたこと、女性に発言権がなかったことがよくわかります。
たとえば、クリトリスを発見した、まったく新しい器官だ、と騒ぐ男性たちの脇で、それ私たち三歳ぐらいのときにはもう発見してたけど……と女性たちがぼやく場面があります。笑えるシーンですが、女性としては恐ろしいシーンでもありますね。科学研究や医学の世界に女性がいないことで、「真実」が男性にとってどれほど都合よく、女性にとってどれほど見当違いなものになってしまうかが、如実に描かれているのですから。ストロームクヴィストはそんなトンデモ言説の数々に、鋭く、ユーモアたっぷりにツッコミを入れていきます。歴史上の、思わず笑ってしまうような奇妙キテレツな学説がたくさん出てきますが、当時の女性たちにとってはまったく笑いごとではありません。生理痛に苦しんでいたら、鼻を手術されてしまったりするのです。(なんだそれ、いったいどういうことだ、と思われた方は、ぜひ本を手に取って読んでみてください。)
女性器、とくに外陰部がタブーとされ、隠され、ないものとして扱われてきた歴史についても、ストロームクヴィストは詳しく記しています。この歴史のせいで、女性たち自身ですら女性器についてあまり知らないということも、けっこうよくあるのではないでしょうか。その意味でも、この本はとても勉強になります。性別にかかわらず、だれにでもぜひ読んでほしい本です(そもそも男性/女性という性二分化のイデオロギーからして怪しいという話も、この本に出てきます)。
いまも科学や医学の世界は(とくに日本では)男性優位ですし、政治的な意思決定の場に女性がまったくいないこともよくあります。それが女性にとってどういう結果をもたらすかは、米国アラバマ州の状況を見ても、いまの日本を見ても明白なのではないでしょうか。女性は自分たちの経験をもっと口に出していい、むしろ声をあげないと自分の身が危ないのだ、ということを教えてくれる作品です。
花伝社
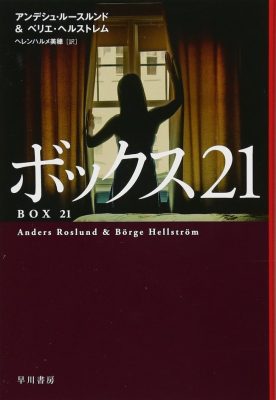
アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
『ボックス21』
翻訳:ヘレンハルメ美穂
(早川書房)
リトアニアで生まれ育った少女ふたりが、いい仕事があるとだまされてスウェーデンに連れていかれ、何年もマンションの一室に閉じこめられて売春をさせられる、衝撃的な物語です。やがて少女たちのうちのひとりが、売春斡旋業者に激しい暴行を受け、病院に搬送されます。そこで危機を脱した彼女は、だれにも理由のわからない、ある大胆な行動に出ます。
男性作家ふたりの合作によるミステリ小説ですが、人身売買と強制売春の被害に遭った少女たちの内面が「からだ」をキーワードに詳しく書かれています。ひじょうにつらい作品ですが、性暴力の問題は女性の身体を語るうえで避けて通れないと思います。この小説の少女たちは、いっさい悪いことをしていないのに、性の対象として、もはや尊厳ある人間ですらなく「モノ」として扱われつづけることによって、自分の身体に激しい恥の意識を覚え、薬で苦しみを麻痺させてなんとか生き延びている状態です。
少々長いですが、本文から引用します。
「リディアは笑いながら、からだのあちこちに石けんをこすりつけた。肌にまだらの模様ができる。首に、肩に、胸に、膣の中に、腿に、足に、石けんを強くこすりつける。
息の詰まりそうな恥辱。
その恥辱を、リディアは洗い流す。男の手。息。におい。ひりひりするほどに熱い湯。恥辱は醜い膜となり、なかなか落ちてくれない。」(p.38)
「リディアには自分なりの儀式があった。毎晩繰り返す儀式。
シャワーを浴び、熱すぎるほどの湯で男たちの手を洗い流す。ロヒプノール四錠、バリウム一錠を、ウォッカ少々で流し込む。それから、サイズの大きな服を着る。ぶかぶかの服。こうすると、からだの輪郭がなくなる。だれにも見えない。だれにも触られない。」(p.62)
彼女たちがさらされている状況はひじょうにおぞましいものですが、それでもこのような心境は、なんらかの形で性暴力を受けたことのある女性なら、多かれ少なかれ経験しているのではないでしょうか。ひとりの人間としてではなく、単なる性の対象として扱われることの、恐ろしさ、嫌悪感、いわれなく押しつけられる恥辱。極限まで追いつめられた少女の反撃が、この小説の中心になっています。
ですが、この作品のすごいところは、「どの女の尊厳が守られるべきかを男が決めている」という社会の構造をも、はっきり描いていることです。その選択が、男性の幻想、偏見の投影でしかなく、現実に即しているとはかぎらない、ということも。あまり詳しく書くとネタバレになりかねないので、このへんでやめておきますが。男性である著者たちにもここまで書けるのだということに、希望を感じます。
早川書房
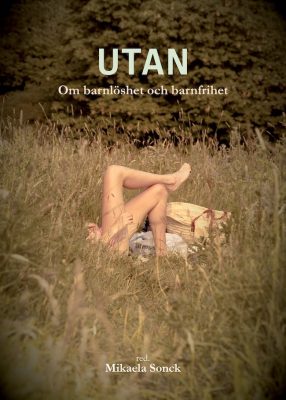
Mikaela Sonck (red.),
Utan
(ミカエラ・ソンク編『無いということ』未訳)
Utanは英語のWithoutにあたる言葉で、この本はスウェーデン系フィンランド人の女性たちが「子どもがいないこと」をテーマに書いたエッセイを集めた本です。ちなみにフィンランドはスウェーデン語も公用語のひとつで、住民の5%ほどがスウェーデン語を母語としています。
不妊治療をしてもうまくいかず諦めた人、養子を迎えた人、体外受精を経て子を授かり、さらに里子を引き取った人、中絶をした人、自らの選択で子どもを作らない決心をした人、子どもが欲しいと思ったことのない人、病気で子宮を失った人……いろいろな女性が、それぞれの立場からとても正直に心境をつづっています。周囲のどんな言葉に傷つけられたか、どんな迷いを感じてきたか。妊娠している女性を目にするのもつらいという人もいれば、悲しみをすでに乗り越えた人も、そもそも悲しみを感じていない人もいます。 「女性性」と「母性」が同一視されがちな現代社会の中で、子どもを持たない女性の現実というのは、あまりおおっぴらに語られることのないテーマではないでしょうか。「産まない」あるいは「産めない」、したがって「非生産的」などと言われる女性たちのひとりひとりに、どんな物語があるかを教えてくれる本です。
上で「女性性と母性が同一視されがち」と書きましたが、本書でひとつ印象的だったのは、自分の子を産めない(産まない)女性たちの多くが「母になれない(ならない)自分は、それでも女性なのか?」「母親ではないが女性であるということは、いったいどういうことだろう?」と自問していることです。(ところで、子どものいない男性は、同じことを自問するのでしょうか? 本書には女性のエッセイしか載っていないので、男性にもぜひ聞いてみたいところではあります。)
スウェーデン系フィンランド人の有名作家であるモニカ・ファーゲルホルムはこの本の中で、「女性がいまだに、なによりも女性として見られるばかりで、ひとりの人間としてなかなか見てもらえないというのは、深刻な問題です」と語り、女性であることを母性と同一視するのは、女性を「人の世話をし、面倒を見る性」「マルチタスキングの得意な“秘書”」、男性を「意思決定を担うボス」として固定化することにほかならない、としています。
実際、母親業ほど神聖化され、同時に軽視されている仕事は、ほかにあまりないのではないでしょうか。母親の愛は偉大だとされ、母性本能なるものが称揚され、母親になる女性はすばらしいとされる。そこから「母親であることこそが女性の喜び」「だからなんでも押し付けて大丈夫」となるまでに、たいした飛躍はありません。
子どものいない女性は自分の女性としての存在価値すら疑い、子どものいる女性は賞賛される一方でキャリアを阻まれたり、旧態依然とした周囲の期待に押しつぶされそうになったりする。「女性はひとりの人間としてではなく、男性や子どもとの関係によってのみ評価される」という社会の構造に苦しまされているのは、どちらも同じなのかもしれません。そんな中で、女性のさまざまな生き方、家族のさまざまな形をオープンに語るこのような本には、大きな価値があるように思われます。

スティーグ・ラーソン
『ミレニアム』三部作
『ドラゴン・タトゥーの女』『火と戯れる女』『眠れる女と狂卓の騎士』
翻訳:岩澤雅利・山田美明・ヘレンハルメ美穂
(早川書房)
世界中で大人気となったミステリ三部作。これはもう、まずはなにも考えずに読んで楽しんでほしい、エンターテインメントとしてほんとうによくできた作品なのですが、 読み終わったあとにちらりと考えてみてほしいのは、第一部『ドラゴン・タトゥーの女』の原題が「女を憎む男たち」であるということ。つまり、女性への暴力や差別の問題が、三部作を貫くテーマのひとつになっている、ということです。
主人公のひとりリスベットはずば抜けて優れた頭脳の持ち主ですが、とある理由で、成人として自らさまざまな決断を下すことができない「無能力者」の烙印を押され、後見人がついています。その立場の弱さにつけこまれて、性暴力の被害を受けもします。が、彼女は黙って耐える女性ではありません。彼女なりの方法で闘い、ささやかながらも自立を勝ち取って生きています。とはいえ、彼女を取りかこむ悪は巨大で、たったひとりでの闘いには限界がありました。第一部『ドラゴン・タトゥーの女』は、そんな彼女が、もうひとりの主人公、ジャーナリストのミカエルを手伝って、殺人事件の調査をする物語です。ミカエルは徐々に彼女の貴重な理解者となり、第二部『火と戯れる女』で彼女を取りかこむ巨悪の存在を知って、ともに闘うようになります。つまりこの三部作は、精神と身体の自立と尊厳を奪われていたリスベットが、周囲との連帯によって権利を取り戻そうとする物語でもあるのです。
リスベットは作中で、児童文学作家アストリッド・リンドグレーンの代表作『長くつ下のピッピ』の主人公、ピッピになぞらえられています。社会通念を超越したところにいる、自立した強い女性。リスベットと連帯するほかの女性たちもそれぞれに個性豊かで、彼女たちの姿を見ていると、私たちもこんなに強く、自由になっていいんだ、と思えてきます。
ですが、その陰で、彼女たちほど強くない、犠牲者となってつぶされていく女性たちの姿も、この三部作にはしっかりと描かれているのです。みんながみんな、リスベットのように強くなれるわけではないかもしれない。それでも私たちは寄り添えるし、それぞれの個性をもって連帯すれば、もっと自由になれるはず。読んでいると、そんな希望が湧いてきます。
第三部の後半を彩る法廷シーン、そこで女性弁護士アニカがとった戦略と、彼女の弁論は、その意味で名場面としか言いようがありません。すでに声をあげている女性たちにも、声をあげたいと思いながらためらっている女性たちにも、これからの闘い方を教え、勇気を与えてくれる場面だと思うのです。
早川書房
ヘレンハルメ美穂/Miho Hellén-Halme
スウェーデン語翻訳者。S・ラーソン『ミレニアム』三部作、A・ルースルンド&S・トゥンベリ『熊と踊れ』など、訳書多数。2006年よりスウェーデン・マルメ在住。
https://mihohh.tumblr.com
https://twitter.com/miho_hh