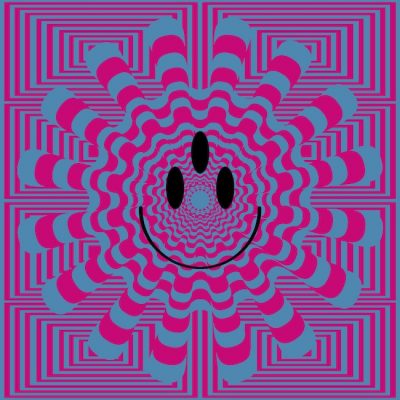日本のみならず海外でも熱狂的な人気を誇る三池崇史監督の最新作『初恋』が、2月28日に全国公開される。アメリカ・フランス・イギリスで先行公開され、すでに世界中のファンを騒がせている本作の主人公は、余命わずかなボクサー・葛城レオ(窪田正孝)。ヤクザに追われる少女・モニカ(小西桜子)を助けたことで、黒社会の抗争に巻き込まれていく彼が過ごした、クレイジーな一夜の物語が描かれている。本作は監督史上初のラブストーリーとしても話題だが、シンプルなタイトルからは想像がつかないほどのカオスと興奮が盛り込まれた、究極のエンターテインメントだ。内野聖陽、大森南朋、染谷将太、ベッキー、村上淳ら、脇を固める個性派たちの演技も見逃せない。ここでは実に100本以上の作品を生み出してきた三池監督に、『初恋』に込めた思いや映画製作についてうかがった。
——『初恋』は“三池監督がやりたいことをすべて叶えるための企画”としてスタートしたそうですね。
三池崇史監督「“やりたいこと”というよりも、“昔はあったのに、今は見かけなくなってしまったもの”です。それは考え方によっては“求められなくなった”ということなんだけど、中には楽しんでくれる人もいるんじゃないか、と。プロデューサーも僕らもこういったジャンルを作りたいわけだしね。それは、自分の居場所を広げるというよりも、狭めないようにするためにも、機会を与えてもらった以上は、知恵を出して楽しんでやる、ということですね」
——『初恋』というタイトルと“監督初のラブストーリー”という前情報からは想像もつかない展開で、夢中になって拝見しました。ものすごくカオスな状況の中で、この上なく純粋なラブストーリーが語られていますね。
三池崇史監督「そうなんですよね。カオスなだけに、そこにはスタッフや役者や僕らが普段抱いている思いが明らかに反映されているというか。たとえば自分であれば、Vシネマの現場が好きで、撮っていて面白かったし、それがあったからこそ結果的に映画も撮るようになった。やっぱり自分の根っこはそこにあるんです。そういう時代がたまたま自分の世代と重なった幸運があって、哀川翔さん、竹内力さんとか白竜さんとか、いろんな人たちと夢中になってやりながらも、世の中が思っているものより、もっと面白いものが作れる、何か生み出すことができるんじゃないかと思っていました。そういうフラストレーションというか感情は今も役者も含めて、みんなどこかに持っている。自分らしく行けるといいなと思っていながら、でも、自分たちはそれだけじゃないんだ、という。今回で言えば、ああいうどうしようもない登場人物たちが好き勝手にそれでも必死に生きて、どこに向かうのか?それが、最後に純粋な2人の出会いに結びついていく、という物語がいいなと思ったんです」

——なるほど。Vシネマから海外の映画祭という流れをどんな風に感じてらっしゃいますか?
三池崇史監督「映画祭に行くと、自分たちが知らないところで何かが起きているというのを実際に感じることができるんです。Vシネマなのに映画として初めてトロント(国際映画祭)に行けて、この作品でまたトロントに行けたのは嬉しかったですし、上映が夜中の12時からなのに1200人の会場がいっぱいなんです。幸いなことに、お客さんもものすごく楽しんでくれて、映画を盛り上げてくれて。劇場で上映してお客さんがいる中で映画が完成することを改めて体感できました。Vシネマの頃もそうですけど、そんなところに行くという想像はつかないわけですよね。Vシネマはビデオレンタル屋さんの棚を埋めていくものだったので、ある制約だけを守れば好きなことができた。それを楽しんでいたし、そこにはある種の自由があったんですよ。その中でいろんな人が出てきたり消えたりしてきた。僕自身、別に流れに逆らって泳ごうという気は毛頭ないんですけど、同じ業界の人を見てきていると、その流れに逆らうことに美徳を感じている人たちもいたんです。客観的に見ると、流れに逆らって漕いでいるから、ほぼ止まっているか、ちょっとゆっくり流されているんです。それであれば、流れの方向に思いっきり漕げばいいんですよね。どうせ流されるんですから(笑)。そっちに向かって漕いで行くと、自分も思わぬところに行くかもわからないし、何が起こるかわからない。それは俳優たちも同じで“こんな役をやりたいけど、一向にそんな役が来ない”とか、そういう不安と不満を抱えていて、要はカオスなわけですよ(笑)。そういった状況も、この『初恋』という物語のベースにはあると思うんです」
——本作はトロント国際映画祭以外にも、カンヌ国際映画祭やテキサス州オースティンのファンタスティック映画祭などに出品されたほか、日本より先にアメリカで劇場公開されたそうですね。海外のオーディエンスの反応で印象に残ったことはありますか?
三池崇史監督「印象に残るというより、作品に感謝をするということだと思う。そこの人たちに楽しんでもらおうという余裕があって作っているわけではないですからね。心のどこかには“届くといいな”というくらいで、いっぱいいっぱいなんです。台本を作ってクランクインしたら、あとはアップまでどうやって漕ぎつけるか。スタッフの睡眠を確保しつつ、会社が潰れない程度に予算を少々オーバーして(笑)、精一杯なんです。ただ、いろんなスタッフやキャストの力をあわせて無我夢中になって作った作品が、結果的に映画祭のディレクターの目に留まって、僕らをそこに連れて行ってくれることがある。歌舞伎町の裏で、わーっと作ったものがどこかにつながっていく。そこがやっぱり映画って面白い、不思議だな、と。そうして1人でも2人でもいいから、本当に“うわー、すげえな”と思って、僕らの作った映画を好きだと言ってくれる人がいると、本当にうれしいじゃないですか。映画を作るという志というより、作るという行為そのものに感謝するというか、そういうところはあります」
——最近はコンプライアンスの厳しさから、表現の自由が狭まれていく印象を受けます。このような時代に映画を撮るにあたって、変わったことや変わらざるを得ないことはありますか?
三池崇史監督「僕らが今“うーん、これはどうなんだ?”と思うのは、むしろコンプライアンスよりも働き方改革の方です。コンプライアンスは色々な解釈のしかたがあって、血がドバーッと出るシーンにしても、アート的に飛ばすこともできるわけで。“これはアートです”みたいな感じで(笑)。映像の美しさにしても、何をもって美しいかというのは人によって違うし、どれがいいか悪いかというのは中身の問題なんです。その中身を作る以前に、作る作業そのものも変わっていってしまう。もちろんギャラをきちんと確保して、できれば労働時間は少ない方がいいんです。でもそうはいかないので、人数を増やして解決するのか、もしくは少し撮影期間が延びてしまうことになる。Vシネマがなんであれだけ混沌としながらも熱いものが感じられるかというと、やっぱり2週間でなかなか寝れずに作っているという熱なんですよね。2週間だったら、わーってお祭りみたいにやれるけど、撮影期間が長くなれば体調を管理していかなきゃいけないですから、そうはいかない。毎回現場で熱を何かしらであげなくてはいけないし、熱があるように演じなきゃいけないんです。毎朝、熱を無理矢理起こすわけです。それは現場が楽しいという、その方法しか多分ないと思うんですけど、そういう労働条件というルールがいずれ常識になっていくので、どのようにこの業界や現場を維持していくんだろう? それで作る映画って面白いのかな? という、なんとなくの不安はあります。もちろん、そうあるべきだとは思うんですけど、急には変えられないし、何かを失くしちゃうような感じがして。やりたいんだからやる自由くらいあっていいんじゃないの、という。やっぱり真剣になれば、もっと撮りたくなりますからね」
——難しい問題ですね。
三池崇史監督「たとえばアメリカはすごいシステマチックに動いていて、助監督は助監督で監督にならない。自分のやることが決まっていて、台本がなくてもできる仕事の人には台本も渡さない。で、どんどんふるいにかけて、条件に合わない人は1週間でクビです。ウィークリー契約なんで。その代わり勝ち取った1週間っていうのは、当然日本よりギャランティはたくさん支払われるんです。たくさんの人が来て、どんどん入れ替わっていく中で、一つの作品を作っている。まあ今でいうと、ワールドカップの日本のラグビーみたいな仕事はできないわけですよね(笑)。ボール出た、はい、僕らフォワードはちょっと後からついていきます、バックスに参加しません、押すのはあなたたちです、みたいな感じですよね(笑)」
——完全分業制というわけですね。
三池崇史監督「分業で、しかも“練習はこんなにはできません”ということでしょう? 彼らに今でいう働き方改革を当てはめたら、あんなに人が感動するような試合とかチームになれたのか、という謎は一つありますよね」

——監督はキャリアを通して100本以上の作品を撮られていますが、作品毎に驚かされます。その新鮮さや情熱はどのように保っているのですか?
三池崇史監督「成長してないんじゃないでしょうか?(笑)。あえて言うなら、成長しなければいいんじゃないかと(笑)。もともとVシネマを作っていて、Vシネマの役割は誰かの期待に応えるというよりも、棚から手に取る気になるかどうかということだから。ジャンルやタイトルや主演俳優とか一見制約があって不自由なように見えるんですが、実はそこさえ守ればすごく自由がある。いつも現場でどういう風に面白くしようかと考えて作業するのが好きなんです。それに“これをきっかけにすごい監督になるんだ”っていう野心というか欲がなかった。“現場に居られるだけでもめっけもんだよね”みたいなことで、それは今でもまったく変わりません。僕らより少し上の世代の監督は、“俺はこういう監督になる、故にこういう作品を撮る”という主張みたいなものがあって、この台詞は言わない、この展開はない、この予算では撮れない、という人が多かった。それは多分、“なりたい監督像”と同時に、“その作品を撮る監督としての生き方”というものに自分の求めるものがあって、それを追求していたんだと思います」
——なるほど。
三池崇史監督「それはそれですごくいいことだと思うんです。ただ冷静に考えると、“そうなりたい”と思う根っこには、“そういう人間ではない”ということがある。そういう人間であれば、何も願わなくてもいいわけです。だから、持っていない才能がきっと眠っているんだと信じて、精進して作り上げていったり、何年か経って、“あ、ねえかな?”と思い始めたときに、あるように人に思わせるということが起こる。そうすると映画が“自分というものを大事にするための道具”になってしまって、スタッフや役者に“俺はこんな人間だよ”と主張しなきゃいけない。それで作り上がるのは、面白い映画よりも自分が思われたい自分のイメージでしょう? そんなものは捨てちゃって、とりあえず脚本の奴隷になって(笑)、作ればいいと思ったんです。スタッフの時間は現場や役者のために使った方がいい。自分にとってはそれが現場だし、今も変わらないですよね。100本も撮っていると、俺にどうなれと言ったところで俺は俺であって、何か期待されてもどうしようもないしね(笑)。ごまめみたいに“置いとけ”って。鬼ごっこやってもタッチされない、ちっちゃい子どもみたいな感じで(笑)」
——子どもと言えば、監督はテレビの子ども番組も手がけられているんですよね?
三池崇史監督「子ども番組は面白いですよ。見る人数が限られているのだけど、すごく楽しんでくれている子どもたちがいて。彼ら彼女らに楽しんでもらうにはどうすればいいのか?未知のチャレンジが面白い。しかも、それは完全に非暴力ですからね(笑)」
——『初恋』は名優が勢ぞろいでしたが、特に主人公の葛城レオを演じた窪田正孝さんが素晴らしかったです。監督の作品に触れたことのない人も観に行くのではないかと思いますが、本作での窪田さんのどんなところに一番注目してほしいですか?
三池崇史監督「出会ってから10年間、いろんなものを積み上げてきたんだなとすごく感じました。いろんな縁を掴んで、いろんな作品に出演して、あくまでも役者として生きてきた。なかなかいそうでいないタイプですよね。彼には“自分がよく見られるためにこの作品をがんばろう”というのではなく、“この作品が面白くなれば”というところがあるんです。芝居が上手いんだけど、“芝居が上手いな”と見せるよりも、存在としてそこにいる。むしろ周りを引き立たせる、要はものを言わないコンダクターみたいな感じ。みんなを引き立たせているという、そういう彼が見られるんじゃないかな。なおかつ今回は巻き込まれる役ですからね。引いて考えると、あんまり何もしていないんだよね(笑)。ボクシングで倒されて、病院に行ったら“病気です”って言われて、“ちょっとがんばっちゃおうかな”っていう」
——劇中の葛城レオを観ていると、人って自分の死が迫ってくるのを感じるとすごいことができちゃうんだな、と思いました。いつ死ぬかわからないと思って生きていよう、というか。
三池崇史監督「そう、何があるかはわからないです。でも、“がんばっちゃおうかな”というのは、自分のためにがんばるのではなくて、なんだかわかんないけどがんばってみる。そうすると、大きな成功や幸せとかではないけれど、寝るときに“ああ、今日は楽しかった!”とか、起きたときに“ちょっとがんばろうかな”とか、普段は幸せに感じるかどうかわからない“かけがえのない瞬間”が、手に入るかもわからないですよね」

photography Shuya Nakano
text Nao Machida
edit Ryoko Kuwahara
『初恋』
2月28日全国公開
hatsukoi-movie.jp
―最期に出会った、最初の恋―
舞台は、さまざまな事情を抱えた人間たちが流れ込む欲望の街・新宿歌舞伎町。天涯孤独ながら希有な才能を持つプロボクサーの葛城レオ(窪田正孝)が、負けるはずのない相手との試合でKO負けを喫し、試合後の診察で余命いくばくも無い病に侵されていることを知る。自暴自棄になったレオが、気もそぞろに繁華街を歩いていると、男に追われる少女に出くわす。ただ事ではない様子を察したレオは条件反射的に男をKO。気を失った男のポケットにあった、警察手帳をとっさに懐へとしまうと、少女の後を追った。少女はモニカ(小西桜子)と名乗り、親の虐待から逃れるように街へ流れついて、ヤクザに囚われていたことを明かす。KOされた男は悪徳刑事・大伴(大森南朋)でヤクザの策士・加瀬(染谷将太)と裏で手を組み、ヤクザの資金源となる“ブツ”を横取りしようと画策、モニカを見張っていたのだ。ヤクザと大伴から追われる身となったレオだが、モニカと自らの境遇が重なる部分もあり、どうせ短い命ならと半ばやけくそで彼女を救おうと決意する。一方で、モニカと共に資金源となる“ブツ”が消えさらにヤクザの一員・ヤス(三浦貴大)が殺されたことを彼女のジュリ(ベッキー)から知らされる組員一同は、組長代行(塩見三省)の基で今にも一触即発の様相を呈している。一連の事件をチャイニーズマフィアの仕業だと踏んだ組随一の武闘派・権藤(内野聖陽)が組の核弾頭・市川(村上淳)と共に復讐を決意し、ジュリも後を追った。ヤクザとチャイニーズマフィアに悪徳刑事。ならず者たちの争いに巻き込まれた孤独なレオとモニカが行きつく先に待ち受けるものとは……。欲望渦巻く繁華街で出会った孤独な二人が過ごした、人生で最も濃密な一夜の結末や如何に。
窪田正孝 大森南朋 染谷将太 小西桜子 ベッキー
三浦貴大 藤岡麻美 顏正國 段鈞豪 矢島舞美 出合正幸
村上 淳 滝藤賢一 ベンガル 塩見三省 ・ 内野聖陽
監督:三池崇史 脚本:中村雅 音楽:遠藤浩二
企画・プロデュース:紀伊宗之 プロデューサー:ジェレミー・トーマス 坂美佐子 前田茂司 伊藤秀裕 小杉宝
共同プロデューサー:飯田雅裕 ラインプロデューサー:今井朝幸 青木智紀 キャスティングプロデューサー:山口正志
撮影:北信康(J.S.C.) 照明:渡部嘉 美術:清水剛 録音:中村淳 装飾:岩井健志 編集:神谷朗
VFXスーパーバイザー:太田垣香織 キャラクタースーパーバイザー:前田勇弥 ヘアメイク:石部順子
画コンテ:相馬宏充 スーパーヴァイジングサウンドエディター:勝俣まさとし
スタントコーディネーター:辻井啓伺 カースタント:雨宮正信 野呂真治 俳優担当:平出千尋
助監督:山口将幸 制作担当:鈴木勇 音楽プロデューサー:杉田寿宏
製作:「初恋」製作委員会 制作プロダクション:OLM 制作協力:楽映舎
配給:東映
(C)2020「初恋」製作委員会
PG12
Twitter:@hatsukoi2020