
ビーバドゥービーやリナ・サワヤマを送り出した〈Dirty Hit〉に所属し、デビュー・アルバム『Good at Falling』(2019年)が高い評価を得たザ・ジャパニーズ・ハウスことアンバー・ベイン。完成した2作目『In the End It Always Does』は、前作に続きThe 1975のジョージ・ダニエルのほか、同じくThe 1975のマシュー・ヒーリーやジャスティン・ヴァーノン(ボン・イヴェール)が制作をサポート。さらに、チャーリーXCXやムナのケイティ・ギャヴィンなど女性やクィアのアーティストが多く参加しているのも今作の特徴だ。パンデミックもあったこの4年の間には、私生活の上で多くのドラマチックな出来事を経験したというベイン。そうして辿った心の揺らぎと変化が、エレクトロニックとアコースティック楽器が織りなすやわらかなサウンドと、輪郭を増したベインのヴォーカルによって鮮やかに表現されている。「内容が正直でオープンなものであれば、恥ずかしがることは何もないということを実感できているから」。そう自身の“成長”について語るベインに、今作が生まれた背景について聞いてみた。
―“Sad to Breathe”のライブビデオを拝見して、サウンドや演奏全体の様子がかもし出すウォームな空気感が心に残りました。“Cause it’s sad to breathe the air when you’re not there(あなたがそこにいないと、息をするのも悲しいから)”という歌詞はとても印象的なラインですが、この曲はあなたにとってどんな意味を持つ曲だと言えますか。
アンバー「この曲は、昔別れを経験した時のことを歌ったもので、自分の人生が完全に終わったと思ったり、憧れの人が側にいないままこの先生活していくなんて想像できないという気持ちを歌っている。でも今振り返ると、そんなふうに考えていた自分をスウィートだなって思えるんだよね。自分がもうそういう状況にない状態で当時を振り返ると、ある意味そこまで傷ついていた自分を愛おしく感じるというか。今の自分は、それが良くなったことを感じているから。その歌詞はすごくドラマチックだし、ティーンエイジャーが失恋したときに言いそうなこと。でもこの曲は、その気持ちを愛おしいと思える状態になった私がそれを振り返っている曲なんだ。昔感じていた苦痛のなかに、幸せや可愛らしさを見つけたような、そんな感じかな」
―前作『Good at Falling』と今回のアルバム『In the End It Always Does』の間のあなたの人生は、激しくドラマチックな出来事の連続だったと聞きます。この間の時間を思い返すとき、最も強くあなたの心に刻まれているのはどんな瞬間で、どんな光景で、どんな感情でしょうか。
アンバー「いろいろあったけど、私にとって大きかったのは、何年もツアーを続けていた生活が突然止まってしまったこと。私はそれまであまり家庭的ではない生活を送っていた。毎日違う街にいて、スタジオを出たり入ったりして、ずっとツアーに出て。それが突然、パートナーと一緒に一つの街で暮らすことになって、毎日家にいるという日常が始まった。そのルーティンワークにすごく苦労していたんだよね。私は毎日違うことをするのが好きなタイプだから。その生活で、パートナーとの関係も一夫一婦制みたいな関係になったんだけど、それも大きな変化だったし、素晴らしい部分もあれば大変な部分もあった。あと、犬も飼い始めたんだ。ジョニーという名前で、あの子は私の人生の光みたいな存在になっている(笑)。それ以外は、海辺の家に引っ越したという変化もあった。そんな感じでいろいろなことがあったんだけど、その変化を通して成長できたと思う」
―そのさまざまな出来事のなかで得た、人生の教訓を挙げるとするなら?
アンバー「あまり感情的になって勢いで行動するのではなく、もう少し選択的になることを学んだかな。自分のメンタルヘルスについても多くを学んだし、ポジティブであることが自分自身にとってすごく重要だってことにも気づいた。だから、音楽に関しても意識的にそうしようと努力するようになったと思う。曲作りやレコードを作ることに対して、あまり気取らなくなったし、コラボレーションに対してもオープンになった。私にとってのベストではなく、曲にとって何がベストかを考えられるようになったかな。曲にとってベストなものって、いろいろな人たちといろいろなアイデアを試すことで生まれると思う。それは間違いなくここ数年の経験から学んだこと。真面目になる時と少し気を抜く時のバランスがとれるようになってきたのも感じるしね」
―“Sad to Breathe”のライブビデオでも印象的でしたが、今回のアルバムではこれまでの作品と異なり、生楽器やアコースティック楽器が多く使用されているのが大きな特徴です。それはどういった理由で、どんなアイデアから生まれた変化だったのでしょうか。
アンバー「もう10年近くエレクトロニック・ベッドルーム・ポップみたいなものをやってきたし、そういう音楽ももちろん大好きなんだけど、今回はもう少し自分にとってチャレンジングなことをやってみたいなと思うようになって。楽器を演奏するのは私にとってすごく難しいことで、上手く演奏するなんてもっと大変。それで、私はピアノが弾けないから、ロックダウンの間にもっとピアノをうまく弾けるように練習しようと思ったんだ。で、ピアノの調律の仕方や、実際の弾き方を練習しているうちに、ギターも前より上手く弾けるようになって、本物の楽器を演奏することの楽しさと素晴らしさを知ったんだよね。サンプルを使えば、ベストなサウンドを常に簡単に手に入れることができる。でも、AIが全部やってくれるなんてちょっとつまらないなって思うようになった。自分で演奏して、そのなかでおかしたミスやハッピーアクシデントのようなものがあったほうが特別なものができるし、異なるサウンドやリアルなサウンドを生み出すことができるってね」
―そうしたサウンド面の変化には、この間にあなたのなかで芽生えた心情面の変化、感覚的な部分での変化も反映されていると言えますか。前作とは、曲作りのインスピレーションが全く変わった?
アンバー「インスレピーションは曲ごとに違う。この曲のこの部分にはどんなサウンドが一番いいかっていうのを考えながらサウンドを構築していったんだ。あと、周りにたくさん素晴らしいミュージシャンたちがいたから、ベストなサウンドのために彼らを起用するのは自然なことだった。一緒に仕事をしているクロエ・クレイマー(リナ・サワヤマ、レックス・オレンジ・カウンティ)は素晴らしいミュージシャンでバイオリニスト。そしてフレディ・シード(エリー・ゴールディング)とジョージ・ダニエルも最高のドラマーだし、私とマッティはギターが得意で、私はピアノも弾けるようになった。それにサックスが上手な友達もいたから、彼らの素晴らしいサウンドを取り入れないことのほうが不自然だったんだよね。そういう意味で、自分の状況の変化っていうのは音楽に影響を与えるのかも」
―ええ。
アンバー「サウンドが変化するのは良い兆候だと思う。年を重ねると、その成長が音に出てくると思うし。私のなかで個人的に成長したなと思うのは、前より自信がついたこと。それは作る音にもあらわれているしね。例えば、“One for sorrow, two for Joni Jones”なんかは、ヴォーカルがすごく直球で前面にでてる。ああいうヴォーカルは最初の頃のEPでは絶対にできなかったと思う。前は、もっと曲に隠れようとしていたけど、今はその必要がないんだ。まあ、前からラウドなボーカルは好きだったから、トラックのなかにボーカルをあえて隠そうとまではしてなかったけど、前はもっとハーモニーをメインにしていたと思う。それが変わった理由は、内容が正直でオープンなものであれば、恥ずかしがることは何もないと実感できているから。クロエやジョージ、マッティのような人たちと一緒に仕事をするようになって、一線を越えるということが恥ずかしくなくなった。そのおかげで、より自分をさらけ出した、ストレートな作品を作ることができるようになったんだと思う」
―いままさに話してくれたように、今作では、より自然体で親密なムードをたたえたあなたのヴォーカルも印象的です。ちなみに、あなたの好きな、あるいは直接的ではないけれど間接的に今作に影響を与えたかもしれないヴォーカル・アルバム、またはフォーク・ミュージックの作品があったら教えてください。個人的には、ジョニ・ミッチェルの『Blue』やブライアン・イーノの『Before and After Science』を連想したところがあったのですが。
アンバー「特にないけど、無意識のうちに影響はされているかもしれない。でも、私が好きなヴォーカリストって本当に幅広いんだよね。例えば、スティーヴィー・ニックスのようなシンガーは大好きだし、ケイト・ブッシュもチャーリー・プースも好き。あとビヨンセも大好き。でも、彼らの真似をしようとしたことはない。私は、自分の声がすごく独創的だと思ってるんだ。中性的で、他に同じような声を持っている人はあまりいないんじゃないかな。まだ若いときは、いろんな人の声をだそうともしてたけど(笑)。エリオット・サムナーとか、ビーチ・ハウスの声とか(笑)。でもそれは、彼女たちの声が低音だから。今は、もう自分らしく歌うことに落ち着いていると思う」
―先ほども話してくれたように、今作にはさまざまなミュージシャンが参加していて、前作から引き続きThe 1975のジョージ、さらにはマシューも制作をサポートしています。かれらとのフレンドシップは長く続いていますが、その関係性は前作から今作にかけてどのように変化してきたと言えますか。
アンバー「もう彼らとは11年の付き合いになるから、これ以上素晴らしくて快適な関係になることはないんじゃないかな。強い絆で結ばれていると思う。特にジョージとはよく会うんだ。私たち近所に住んでいるから。もちろんお互い仕事で家を離れていることが多いけど、会えるときは出来るだけ会うようにしている。私たちの深い友情は変わってないし、これからも変わらないはずだよ」
―今作を制作する上で、ふたりからどんなアドバイスを受けましたか。
アンバー「アドバイスまではもらってないかな。かれらはすごく協力的で、私のことを心から応援してくれている。だから、私に指示をしたり、助言を与えようとはしないんだ。あと、ジョージとマッティについて語るなら、クロエ・クレイマーの話もはずせない。彼女はこのレコーディング・プロセスにおいて一番活躍してくれたひとりだし、かれらと私は、チームとして本当に素晴らしいものを作り上げたと思う。お互いが異なる空間を埋めていって、曲を作るのに素晴らしい環境を作っていった感じかな。例えば、私はアイデアはもっていても、それを形にして完成させるのが苦手なんだけど、クロエやジョージは実際にそれをやり遂げる集中力をもっている。もう、今後かれらと一緒じゃないとレコードを作りたくないくらい、かれらには助けてもらっているんだよね」
― 一方、今作にはそのクロエ・クレイマーをはじめ、チャーリーXCXやムナのケイティなど、女性やクィアのミュージシャンやスタッフが制作に多く参加しています。今まで女性やクィアと一緒に仕事をしたことがなかったと聞きましたが、今回の経験はどんな気づきや学びをあなたに与えてくれましたか。
アンバー「これまでも、女性とクィアのプロデューサーやアーティストと仕事をしたことはあるよ。でも、ケイティはアルバム制作のなかでも大きな部分を担ってくれていて、彼女からは大きな影響を受けた。特に、“One for Sorrow, Two for Joni Jones”のレコーディングは、これまでに経験しことのない素晴らしい経験になったと思う。ケイティと一緒に仕事をしたとき、本当に特別な感じがしたんだよね。作業をしていて、その部屋にクィアの女性だけっていうのは初めてだった。それってすごくレアなことで、ケイティとはこれまでも他のプロジェクトで一緒に仕事はしてきたけど、今回のアルバム制作では、自分たちだけというその瞬間がかなり特別なことなんだということに気がついたんだ。自分を反映してくれるような人たちと一緒に仕事ができるのは嬉しいし、レアじゃなく、もっと当たり前になるといいなと思った。今回、その空間の特別さを感じるまで、男性ばかりと仕事をしていることに気がつきもしてなかったんだよね。もちろん、ジョージと一緒に仕事をするのは大好きだし、彼と一緒にいるとすごく落ち着く。これまで一緒に仕事をしてきた男性たちが素敵な人たちばかりで、私はきっとラッキーだったんじゃないかな。でもやっぱり普通は、クィアな女性としての私の気持ちが書かれた曲を、男性が完全に理解するのはむずかしいことだと思う。それを理解できる人と一緒に仕事をすることって重要だよね。音楽業界には、年配の白人男性がたくさんいて、レコードを作っていたらそれに上から口出ししてくる人も結構いたりする。でも、チームとして一緒に感動したり、共感してくれる人たちと一緒に仕事をするのはやっぱりいいよね」

―4年前に来日された際に伺ったインタヴューでは、自身のセクシュアリティーのことや音楽業界におけるミソジニーの問題に触れながら、「昔は女性に対して差別的だった人が、今は人間的に成長して考えを改めたってケースもあるから、期待している部分もある」と話されていたのが印象的でした。今のあなたの目から見て、そうしたポジティヴな変化は感じられますか。また今作の制作を通じて、女性やクィア同士が繋がることの大事さ、その意義を再認識したところもあったのでしょうか。
アンバー「私そんなこと言ったんだ(笑)。覚えてないな(笑)。4年前の私は自分が差別されていることに気付けてなかった部分があったと思う。例えば、『女の子なのにプロデュースできるなんてすごいね』って褒められたんだけど、当時の私はそれを聞いて本当に嬉しいと思ったんだよね。褒められたと思ったんだけど、今思えば、『え? 何言ってるの?』って感じじゃない?(笑)。女子だからノートパソコンが使えないはずって考えがあるから出てくる発言であって、それはやっぱりおかしいと思う。でも、以前よりもこの問題について語られるようになってきていることも事実だし、良くなってきているのか変わってないのか、ちょっと微妙なところかな。レディング・フェスティバルのラインナップなんかはまだまだ男性アーティストがほとんどだし、いまだにちょっと退屈な部分も残っている。だから、ジャッジするのはちょっと難しいんだよね」
―ムナといえば、その前回のインタヴューで「アメリカのバンドだけどめちゃくちゃ仲良くて、アルバムをよく聴いている」と話してくれたのを思い出しました。今作の制作中、ケイティや、あるいはチャーリーとどんなコミュニケーションがあったのか、そのあたりのエピソードを教えて欲しいです。
アンバー「チャーリーは私の友人と付き合っていて、それでスタジオに来る機会があったんだけど、その時に作業をちょっと手伝ってくれたんだ。私は仕事以外で彼女を知っているけど、チャーリーは本当に素敵で良い人で大好き。ケイティとはもう何年も前から一緒に作業していて、クロエも同じなんだけど、私たちは大抵5時間くらい座って、セラピーみたいなことをするんだ。たくさん話して、泣いたり笑ったりした後に、『よし、じゃあボーカルをレコーディングしようか』って言ってレコーディングを始めるという流れ(笑)。すごく自由で、あまり構成なんかを前もって考えることはないんだよね。自然の流れに任せる感じ。『このサウンドの上に何かのせてみる?』とか、『こういう歌い方試してみる?』とか。“Morning Pages”では、ケイティは流れで歌詞も書いてくれたし。それができる素晴らしいミュージシャンたちと一緒に仕事が出来ているなんて、本当にラッキーだと思う」
―最近受けたES MAGAZINEのインタビューで、「自分の曲は聴き直さない。リリースしたらすぐに自分の人生の文脈から外してしまうから」と話していましたね。今作の曲についてもそうだと思いますか。
アンバー「まったく聴かないわけじゃないよ。リリースする前は何度もリピートで聴くんだけど、一度リリースするとそこまでは聴かないという意味で言ったんだと思う。あと、リリースすると初めて聴いたような感覚にもなるんだよね。リリースして他の人々に向けて音楽をプレイすると、違う視点からその曲を見ているような気がして。聴いている人たちと同じ視点、自分にとって新しい視点で曲を聴いているような感覚になるんだ。今は、一歩下がってリスナーの視点から改めてアルバムを聴いているところ。それって素晴らしいことだし、私は自分がこうしてアルバムを楽しめていることが本当に嬉しい。何も変えられないし、変えなくていいし、本当に心地よく作品を聴くことができている。そして、純粋に自分が本当に好きなものを作っている時の気持ちのように、聴いていてすごく自由な気持ちになれるんだよね」
―最後に、今回のアルバムのなかで個人的に一番好きな曲、あるいは誇りに思える曲を教えてください。
アンバー「“Morning Pages”かな。3/4拍子で曲を書くのが大好きだから。その制限のなかでキャッチーなものを作るのって、実はとても難しい。そんな曲を作ったのが久しぶりだったし、ケイティの歌詞が大好きだから、私のお気に入りはその曲。私たちふたりが一緒に曲を作ったっていう事実自体が本当に素敵なことだしね。しかも、あの曲は本当にあった話。ある日、私は実際にその女の子を駅まで送っていったんだ」
text Junnosuke Amai( TW )
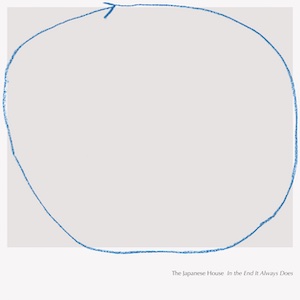
The Japanese House (ザ・ジャパニーズ・ハウス)
『In the End It Always Does(イン・ジ・エンド・イット・オールウェイズ・ダズ)』
国内盤発売日:2023年6月30日(金) 世界同時発売
(Dirty Hit )
<トラックリスト>
1. Spot Dog
2. Touching Yourself
3. Sad to Breathe
4. Over There
5. Morning Pages
6. Boyhood
7. Indexical reminder of a morning well spent
8. Friends
9. Sunshine Baby
10. Baby goes again
11. You always get what you want
12. One for sorrow, two for Joni Jones
13. Super Trouper (ABBAのカヴァー / 日本盤ボーナストラック)
日本盤はボーナストラック1曲、解説、歌詞対訳付(予定)
ストリーミングリンク : https://lnkfi.re/BCwl0p7v
日本オフィシャルHP : https://www.virginmusic.jp/the-japanese-house/
THE JAPANESE HOUSE、4年振りの発売となるニュー・アルバム『In the End It Always Does』を引っ提げた来日公演の開催決定。
【大阪】1月15日(月) 梅田クラブクアトロ
【東京】1月17日(水) 渋谷クラブクアトロ
【東京】1月18日(木) 渋谷クラブクアトロ
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKET オールスタンディング¥6,500(税込/別途 1 ドリンク)※未就学児入場不可
●クリエイティブマン会員先行 : 7/1(土) 3A→15:00/モバイル→18:00 ~ 7/5(水)18:00
◎プレイガイド先行:7月6日(木)~
◎一般発売日:7月29日(土)~
〈問〉 【東京公演】クリエイティブマン 03-3499-6669 【大阪公演】梅田クラブクアトロ 06-6311-8111
制作・招聘:クリエイティブマン
ザ・ジャパニーズ・ハウスことイギリス出身のシンガーソングライター、アンバー・べイン。The 1975やリナ・サワヤマ、ビーバドゥービー等が所属するUK気鋭レーベル、Dirty Hitと契約し、2015年にEP「Pools to Bathe In」を発表。その後も「Clean」 (2015)、「Swim Against the Tide」(2016)、「Saw You in a Dream」(2017)と次々とEPを発表。活躍が期待される新人アーティストを選出するBBCの名物企画


























