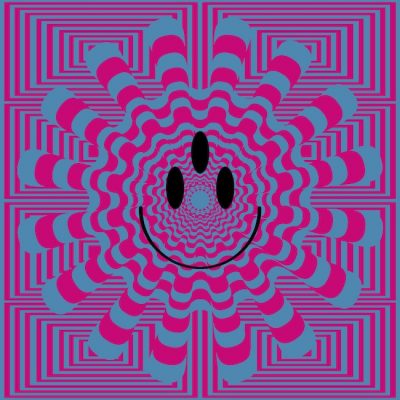R&Bからダンスミュージックを横断するエッジなサウンドと艶やかなヴォーカルで人々を魅了するKelela。2019年より活動を休止していた彼女が、2022年に新曲“Washed Away”を手にシーンに戻ってきた。今年2月には最新アルバム『Raven』をリリースし、9月には5年ぶりとなる来日公演を行ったKelelaに、復帰後の心境について、新作について、そして活動の核となるプラットフォーム作りについて話を聞いた。
―昨日のライブは5年ぶりの来日でしたね。とても素晴らしいステージでした。
Kelela「来てくれてありがとう! 私もとても楽しかったし、そう言ってもらえるのは私にとって大切なことなんです」
―今年はライブ自体が久しぶりですよね。2019年の秋ぶりのツアーだと思いますが、数年ぶりに世界を回ってみて人前で歌うのはどんな気分ですか。
Kelela「私の周りの友達にはここまで長いブレイクを取る人はあまりいないし、そういうのを恐れる人が多いと思います。だから、休む時間が必要だと認めるのにはすごく勇気が必要でした。とても長いブランクの後だったし、その間は歌の練習もあまりしていなかったので、ライブができるかどうか不安でした。ですが、リハーサルを始めると意外と歌えたんですよね。レコーディングは続けていたので、それが練習やエクササイズの代わりになったのかもしれません。むしろそのおかげで、以前よりも強く自信を持って歌えるようになったと思います。レコーディングのときも『これトラック流してる?』って自分で思うくらい声が出ていてびっくりしたんです(笑)」
―レコーディングを続けたことがライブで役立ったんですね。
Kelela「そしてもうひとつ、前回のツアーはステージ上にダンサーやバックボーカルなどの自分以外の人がステージ上に結構たくさんいたんですけど、今回のツアーはこのレコードのメッセージ的にも、自分が今現在立っている場所的にも、ステージには自分と照明しかない状態を作りたかったんです。そういうことをしている人も周りにいないから、踏み出すのが怖かったし勇気が必要でした。今の音楽業界では、常に次の作品がより大きな成功を収めることが期待されます。前より派手で売れるものが求められ続ける。でもそれは私の気持ちとはあまり一致していませんでした。自分のありのままの姿でステージに出ることが、今の私にはマッチしている。そしていざ自分がステージに立ってみると、周りの人たちは私がたったひとりでステージに立っている話ばっかりするんです。確かにその決断には勇気がとても必要でしたが、それがパフォーマンスの強さに繋がったと思います。怖かったけれど、やり遂げることができてとても幸せです」
―ライブでの衣装には胸のあたりに鏡があって、それがとても印象的だったんですが、あれは何だったんでしょうか?
Kelela「あの鏡には色々な解釈の仕方があります。今年の2月に私のファンだという、とあるクリエイティブディレクターのファッションショーに誘ってもらったんです。その時の彼のコレクションには、お腹か胸のところに丸い鏡みたいなのが入っていました。それを着けたモデルが歩くと、目が見えなくなるほどの明るさの照明の光が私たちに向かって反射してくる。それがカッコ良すぎて、ショーが終わった後にバックステージで彼に『あなたのショーピースを私のショーに借りてもいい?』って聞きに行ったんです。そしたら『いいよ、好きなものを持っていって』と言ってくれました。
これには私のハートからあなたのハートへ、という意味もあると思っています。全公演で着けているわけではないんですけど、着けたときはマジカルな感じがします。とてもシンプルなコンセプトなんだけど、ちょっと説明するのが難しい。特にこれは身近なもので作った視覚的アイデアの中では最も印象的なものでした」
―その想いはフロアにちゃんと届いていたと思います。
Kelela「ありがとう。ファッションショーで感動するのは変なことのような気もしますが、とても感動したんです」

―ライブではほとんどがリミックスされたビートを使っていましたよね。特に“Enemy”でドリルビートが使われていたのにびっくりしました。“Sorbet”のトランシーなリミックスも最高でした。今回の『Raven』でもリミックスバージョンが出るとおっしゃっていましたが、どういう作品になりそうですか?
Kelela「今ちょうど『Raven』のリミックス版を作っています。しばらく日本に残ってそのプロジェクト用のビジュアルを東京で撮影してから帰ろうと思っていて、帰国したらその作業に没頭するつもりです。すごく楽しみだし、このリミックスのビジュアルは東京しかありえないと思っているんです。“Washed Away”と“Enough For Love”のMVを監督してくれたYasser Abubekerも日本に来てくれています」
―あと、ライブではアルバムの各楽曲がシームレスでつながっていて……。
Kelela「あ、ドリルビートについてまだ答えてなかった! 大事なことなので話しますね。私は自分のことを編集クイーンだと思っています(笑)。とにかくリミックスが大好き。オリジナルの作品に様々なアレンジを加えるのはいくらやっても足りないくらい楽しめる。特にボーカリストってリミックスに関わったりこだわったりすることがあまりなくて、歌を録ってあとはもう丸投げって感じの人が多いと思うんですけど、むしろ私のアーティストとしてのアイデンティティはリミックスにあります。DJカルチャーの中で育ってきて音楽をやってきているので、リミックスはとても大事なことなんです。むしろリミックスのためにレコーディングをしていると言えるかもしれません。後に色々な作品に使うことになるので、アカペラのレコーディングは完璧じゃないといけない。それにリミックスを作ることによって、自分がいろんな世界で存在できるような気持ちになります。
『Raven』で5曲プロデュースしてくれたLSDXOXOがリミックスを送ってきた時も、彼はそれを作ろうと思って送ってきたんじゃなくて、何なのかよくわからないけどこんなのができたよ、みたいな感じで送られてきて。友達と外に行って、みんなで聴いたときの衝撃は凄かった。なんていうか、『ムキムキ、ボンデージ、etc…』みたいな感じの世界観のビートでした(笑)」

―今回のアルバムのクレジットを見て気になったのが、DJ/プロデューサーのbambiiの参加です。bambiiはカナダ出身ですが、どのようにして知り合ったのでしょうか?
Kelela「bambiiは2017年末のトロント公演のサポートをしてくれたんです。私は全く覚えてなかったんですけど、彼女曰く、初めて会ったのはステージ裏でショーに出る準備をしているときでした。私は彼女に『背中のチャックを上げてイヤモニのケーブルの中に入れて』って頼んだらしいんですよ。彼女は私のファンだったらしいですが、そのときは『え! 私がやるの!?』 って思ったみたいです(笑)。それから数年経って、コロナの期間に距離が近づいて。その時には『Raven』の曲もほぼ全てできていたんですけど、全曲何かがちょっとずつ足りないと感じていました。1曲1曲が締まっていないように思ったんです。それで私はbambiiに2週間だけニューヨークに来て一緒に作業してくれない?と頼みました。彼女がこの曲を締めるための鍵を持っていると思ったからです。でも彼女には、光栄だしやりたいけど私にはスキルが足りないから出来ないと言って断りました。それで私は、あなたにそのスキルがあると思うし、そうじゃなかったら声なんてかけないからと彼女を説得して、無理やりニューヨークに来てもらいました。彼女は不安がっていたけど、私は100%大丈夫だと思っていました。結局彼女は2週間ほどいてくれて、15曲中11曲は彼女のおかげで完成しました。だから『Raven』は彼女のおかげでできたアルバムなんです」
―bambiiは“サポートプロデューサー”や“アディショナルプロデューサー”としてクレジットされていますが、そういうことだったんですね。
Kelela「女性として、特に音楽界の黒人女性として私たちはめったにチャンスが与えられません。私たちは自分で道を切り拓かないといけない。でも自分の足で登っていこうとするのも難しい。人生の中でマイナスの要素や経験が多すぎるので、やる前からできないっていうマインドになりやすいんです。私自身もそういう経験がたくさんあるから、bambiiが『私にはできない』って思ってしまう気持ちも理解できました。だからこそ無理やりにでもニューヨークに連れてきたんです。彼女は私の家に着いたときは気が狂いそうだったと言っていました。でも実際、作業を始めるとすぐ彼女からアイデアが溢れ出てきていました。しかもその全てが私は気に入ったんです。
自分のプロジェクトやアーティストとしてのキャリアにおいて私が大切にしているのは、不当に軽視されている人たちのプロジェクトをサポートすることです。それが私のポリシー。今回のアルバムはbambiiの才能を貸してもらって出来上がりました。そうすることで私のレコードが彼女を世界に知らしめるプラットフォームにもなります。そういう形でお互いを支え合うことが私にとって重要なんです。それはリミックスアルバムについても同様です。前回のプロジェクト(『TAKE ME A_PART, THE REMIXES』)は20曲という巨大なものでしたが、そのうち19曲は黒人のプロデューサーでした。私たちの友情は、同じような考えや感情を共有することから生まれます。同じ思いを語り合ってきている仲間達のプラットフォームをお互いに作り合うことは大事なことだと思ってやっています。
私はかっこいい曲をただ作りたいわけじゃないんです。そんなことは誰でもできる。私はあまり名を知られてないけど素晴らしい実力を持ったアーティストのプラットフォームをちゃんと作ってあげたい。世の中の仕組みはそういう人たちに中々光を当ててはくれないから、新しいリミックス版で、またどんどんそういうことをやっていきたい。ちなみbambiiは『INFINITY CLUB』っていうEPをリリースしたから、みんな聴いてね!」

―最後の質問です。作品というのは、作家の意図を超えてオーディエンスに伝わるものだと思います。今回のアルバムをリリースしてみて、オーディエンスの反応を見てどう思いましたか?
Kelela「友人のアーティストのたちもそうなんですけど、作った曲をリスナーに届けたときに、全然違う解釈が返ってくることはよくあります。でも今回の『Raven』に関しては、自分が伝えたいことがそのまま伝わっているように感じています。パンデミック中にSNSをリアルタイムで見ていてわかったのは、私のファンコミュニティの誰もが、自分のありのままの姿や優しさを表現することを求めているということでした。どこにいても、危険じゃない世界、ありのままの自分でいることが怖くない、危険じゃない世界で暮らしたいと願っている人達ばかりです。
音楽をやっている友達の話を聞くと、作品を出した時に返ってくる反応がそれぞれで、それこそライブやった時に自分のファンベースのはずなのに失礼な人もいるし、それに腹を立てる人はそれなりにいます。でも私はそういうのが全くないんです。自分が作品を出した時にそのまま伝わっていると感じるし、それが愛情深いKelelaファンのカルチャーだと思います。
例えばインターネットで毎日何かを発信してれば、そこに対してのレスポンスが必ず返ってきます。でも、私みたいにネットから身を引いて新作もPRも何も発信しなくなっても、私の曲を聴き続けてくれている。それは、その曲が彼らの人生の一部になっているということだと思います。
私が9月にインターネットに復帰したとき、その期間中に私のファンの人々が作成したツイートやミームのコラージュを作りました。その中には、『最も必要なときにKelelaが姿を消した』という面白いツイートがたくさんありました。他にも色々書いてあったんですが、それらのツイートの共通点は、率直で心を開いていて、同時に非常に賢明であるということでした。その上で、政治的な意識も高く、繊細で優しくて、周りのこともちゃんと理解している。このことに気付いた私は、作品を通して伝えたかったことが私が守りたいと思っている人々にとって実際に効いているのだと感じることができました。私の音楽を楽しんでくれるのはこういう人々なのだと分かったんです。それは素晴らしい気付きでした。あなたも、愛情を感じる質問をありがとう」

photography Marisa Suda(https://www.instagram.com/marisatakesokphotos/)
text mocomi(https://twitter.com/mocomi__)

Kelela
『Raven』
Now On Sale
(Warp Records / Beat Records)
・国内盤特典:歌詞対訳 & 解説冊子封入
詳細はこちら:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13151