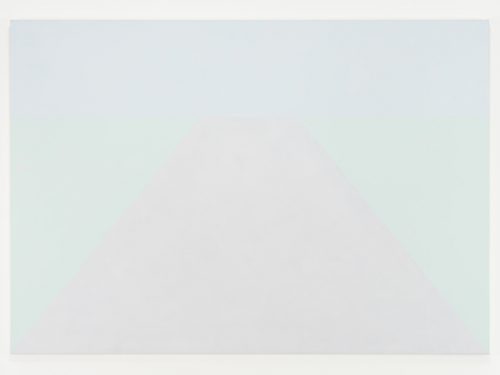ハイブリッドな音楽性やプロダクションの面白さが耳を引いたデビュー作『925』に対して、メロディの魅力やオーガニックな楽器の音色が際立つソーリーの2nd『Anywhere but Here』。ランディ・ニューマンやニーナ・シモンのレコードにインスパイアされ、ライヴのフィーリングを取り入れることでまとまりと温かみを増したサウンドは、リーダー役のルイス・オブライエンいわく、バンドがより「コミューナル(共同体的)」になれた証であるという。ロックダウンが明けてツアーが行えるようになり、メンバーが揃って一緒に演奏する楽しさを再認識できたこと。あるいは、最近のイギリスの若い世代の間でフォーク・ミュージックが見直されていること、そして各地で都市の再開発が進み失われつつある「コミュニティ」の価値が問い直されていることも、以下のインタビューで語られているとおり今作の背景には窺える。「ただ人々が集まって音楽を演奏することは、個人的な意味を超えて、もっと重要なことなんだ」(キャンベル・バウム)――10月初めに一夜限りの初来日公演を行なったソーリーのメンバー全員に、今のかれらを取り巻くさまざまなトピックについて話を聞いてみた。
―2ndの『Anywhere but Here』がリリースされて1年がたちます。前作の『925』がリリースされたのはパンデミックの真っ只中でしたが、この1年はどんな1年でしたか。
ルイス「とにかくたくさんのショーをこなしてきた感じかな。2ndがリリースされた当時のイギリスはコロナが始まった頃のような制限が厳しい状況ではなかったので、普通の活動が少しだけ許された状況だったというか。だから、1stの時にはできなかったこと――イギリス国内だけでなく、ヨーロッパやアメリカでもライヴができたし、そうした普通のことを体験できた1年だったね。今年の夏には初めてフェスティヴァルに出演することもできたし、とても楽しかったよ」
リンカーン「実はアメリカのツアー中にみんな体調を崩してしまってね。病気にならないようにってあんなに気をつけていたのに(笑)」
―サウンド的にも1stと2ndの間には違いや変化が見られますよね。
アーシャ「(曲作りの)作業自体もかなり違っていたと思う。1stはもっとプロダクションの比重が多い感じで、“プロダクショナリー”な作品だった。それにライヴのフィーリングも薄かったし。だから今回の2ndでは、より発展的で、エモーショナルで、もっとライヴのエネルギーが感じられるものにしたかった。かつ、インストゥルメンタルの部分でもう少し統一感を持たせて、それぞれの曲で使うサウンドも少なめにして――コラージュみたいな感じだった1stと比べて生々しくミニマルな感じにしたくて。1stとは逆方向からのアプローチだったというか、そのためのさまざまな方法やテクニックを学ぶことができたと思う。使われているサンプルも実際にライヴで演奏したものが含まれていて。今回はレコーディングに1ヶ月と少し、さらにその後に2、3ヶ月かけて完成させたんだったかな。なので1stを作った時と比べるともっと長い時間をかけて、いろいろなものが加わっている」
―たくさんのライヴをこなすなかで発見は何かありましたか。
マルコ「サンプリングが多かった古い曲と新しい曲を隣合せで一緒に演奏することで、ライヴとプロデュースされた曲の違いや、自分たちがどちらのサウンドが好きなのか、自分たちが次に進むべき方向性に気付かされたところはあったかもしれないね」
―その「次に進むべき方向性」という話とも関わってくると思うんですけど、先日、2ndに収録された“Screaming In The Rain”を新しく再レコーディングした“Screaming In The Rain Again”をリリースされましたよね。2ndのスタイル、ライヴ感覚をより推し進めたヴァージョンのように感じたのですが。
アーシャ「あの曲をもっとポップな曲として聴きたかったんです。それに、元々のヴァージョンはちょっとスロウな感じがしていて。あの曲はエモーショナルで、それはそれでアルバムの雰囲気やモードにフィットしたものだったと思う。だからもっと楽しい感じにしたくて、ポップ・ヴァージョンを作った感じというか。ライヴで演奏していて楽しくなるような」
―他にも曲があるなかであの曲を選んだのはどうして?
ルイス「最初にあの曲を書いたときは、実はアルバムに収録されたヴァージョンとはかなり違っていたんだ。それで、あの曲にはいろいろなヴァージョンがあるような気がして、そのアイデアをちょっと探ってみたかったというのもある。あの曲を(アルバム用に)レコーディングした時にありえたかもしれないさまざまなアプローチを試してみたかったというか。だからその最初の時点に戻ってみて、違うヴァージョンを作ってみようとトライしたのがあの曲(“Screaming In The Rain Again”)だった」
マルコ「あの曲は『925』のツアーの時から演奏していた曲で、新しい曲のなかで一番長く演奏している曲のひとつなんだ。実際、ライヴで演奏するなかで3つか4つのヴァージョンに変化を遂げてきた曲なんだよね」
ルイス「あの曲に取り憑かれてしまったんだ(笑)」
リンカーン「ライヴで演奏すると、観客の反応がエネルギーになってどんどん早くなるんだよね(笑)。その感じを新しくレコーディングされたヴァージョンでは体験してほしいね」
マルコ「あの曲はクラシックなギター・ソングにインスパイアされた曲で、だからアルバムの文脈ではスロウ・ヴァージョンのほうがよりしっくりくる。ただ同時に、多くの可能性を秘めた曲でもあるんだよ」

―「クラシックなギター・ソングにインスパイアされた」という話ですが、2ndの制作中はカーリー・サイモンやニック・ドレイク、エリオット・スミスなどのレコードよく聴いていたそうですね。それはどういうモードだったのでしょうか。
アーシャ「今挙げてくれたものは確かに制作中によく聴いていたものだけど、でも私たちは昔からそういうクラシックな音楽が大好きでよく聴いてきたし、つねにインスパイアされてきた。ただ、1stを作った時もそういう(クラシックなギター・ソングの要素を取り入れる)アイデアはあったんだけど、自分たちのソングライティングの技量的にそこまでではなかったというか、形にしようとしても満足のいくものができなかった。だから今回のレコードでは、そうした方向性に向かって自分たちの音楽を発展させたかったんだと思う。私たちは古いレコードが好きだし、そこには温かみを感じることができる。それで自分たちの音楽も、1stよりももっと温かみが感じられるようにしたかった」
ルイス「1stは、ちょっとポップで“pasty”だったから。このアルバムでは、アーシャも言ったように、ソングライティングに磨きをかけたかったんだ。たとえば1stや以前の僕たちの曲は、今君が挙げてくれたアーティストのようには聴こえなかった。ただ、僕たちはあの時代の音楽をこれまでもリスペクトしていたんだ。ソングライティングこそが最も重要だった時代の音楽をね。興味深いメロディとか、熟慮された構成とか、そういったものに僕たちは惹かれ続けてきた。だから今回、新しいアルバムで僕たちはそうした関心を反映させようとしたんだ。ただしそれでいて、自分たちのスタイルをあまり逸脱し過ぎないようにね。そのギリギリのラインを巡って試行錯誤しながら作った感じだったね」
リンカーン「それと1stから2ndへの大きな変化は、マルコがバンドに加わったことでライヴでのサンプルの使い方をもっと探求できるようになったことだった。マルコがどのように実験するのかを見て、一緒にリハーサルをすることで、バンド全体でそのような実験ができるようになったんだと思う。その成果が曲作りにフィードバックされていると思うよ」
―なるほど。
マルコ「最初のレコードはとてもプロダクション・ベースで、サンプルを使ったヒップホップの影響を受けていた。でもライヴをやるようになって、ライヴ・バンドになることで、サンプルやエレクトロニクスをライヴで使うようになった。今作ではそのギャップを埋めようとしたんだ。だから、曲作りに関してはすべてがコンピューターのなかにあるわけじゃない。つまり、(1stと)同じ方法論と哲学をライヴで使うようになったことが大きいね」
リンカーン「エレクトロニック・ミュージックを曲作りのプロセスに取り入れると、リズム・セクションにその影響は表れる。逆にエレクトロニック・ミュージックの影響がなくなると、演奏に対してより緻密に厳格な姿勢で臨むようになる。そうした変化や効果が曲作りのプロセスでは役に立つんだと思う」
―キャンベルはどうですか?
キャンベル「えーっと、質問はなんだっけ?(笑)。思うに、僕らの場合、曲の基礎となるものはアーシャとルイスがほとんど出来上がったものを持ってくることが多いんだ。でも今回は、みんなが一緒の部屋に集まって曲を発展させていくような場面が増えたと思う」
ルイス「1stの時よりもライヴをする機会が増えて、一緒に演奏することが増えた。それにキャンベルが作ってくれるベース・ラインのおかげで、僕とアーシャのアイデアだけでは思いもしなかった曲になることがある。だから、僕たちは一緒に演奏したり曲を作るようになってさまざまなインプットをすることで、このアルバムの曲の幅を広げることができたんだと思うよ」
―今回の「クラシックなギター・ソングにインスパイアされたソングライティング」という話に関連して、キャンベルが立ち上げに関わったフォーク・プロジェクトのブロードサイド・ハックスについてもぜひ聞きたいんですけど――。
ルイス「いいね!(手を叩いてガッツポーズ)」
キャンベル「アーシャも参加していて……」
アーシャ「いやいや、私はぜんぜん大したことしてないよ(笑)。でも大好き」
リンカーン「僕も1ヶ月ほどいたけど、追い出されたんだ(笑)」
マルコ「僕は呼ばれたこともないよ(笑)」
キャンベル「(笑)あれはパンデミックの時にコンピレーションを制作するために始めたプロジェクトで、そのアイデアは、多くの人に古いトラディショナル・ソングをアレンジしてもらうことだった。アーシャもそのひとりで、ある人は演奏で協力してくれたり、ある人は歌ってくれたり、そういうふうにみんなが少しずつ参加してくれたんだよ」
―最近のイギリスでは、若い世代の間でフォーク・ミュージックを新たに捉え直す動きがあると聞きます。実際にそうした気運は感じますか。
キャンベル「そうだね。ロックダウンが始まって閉塞感が広がる状況のなかで、それを破るように新しい世界を覗いてみたいという欲求からそうした音楽を探し始めたところは大きかったと思う。それで自然とそういう方向にみんなが進んで行ったんじゃないかな」
リンカーン「あと自分が思うに、コロナの前って、若いアーティストは毎晩のようにギグをやっていて、実は他のバンドのギグを観ることがなかったり、交流する機会が意外となかったんだよね。それで『みんなで一緒になんかやりたいよね』っていうので、ああいうコンピレーションに繋がった部分もあるんじゃないかな。それと同時に、ああした音楽は、多くの人が同時に一緒になってライヴをすることができるというのも大きかったと思う。コロナでみんなが顔を合わせられないという奇妙な状況から、共同体のように多くの人たちが集まって、アコースティック・ライヴみたいに演奏するという必要性を切実に感じていたところがあったと思うんだ。それはどこでだって、特別な用意がなくてもできることだったわけだしね。フォークが好きな人たちが集まりさえすればさ」
アーシャ「キャンベル・バウムは“フォークの王様”なんだよ」
キャンベル「みんながいろいろな角度から(フォーク・ミュージックに)アプローチしているのが興味深い。そしてパンデミック以降、こうした大規模なアンサンブルをさまざまな場所で目にするようになった。そこには、フォーク・ミュージックの“コミュニティ精神”というものが明白に現れていたと思う。そのことはとても重要で、それが今のイギリスで一種のムーヴメントが起きている理由だろうね。ただ人々が集まって音楽を演奏することは、個人的な意味を超えて、もっと重要なことなんだ。そのとき、音楽は誰のものでもないから。だから、音楽に対するアプローチの仕方がまったく違うんだ。個人的ではないものを、個人としてではなく演奏することで、グループとしてまとまり、ひとつに団結しやすくなるんだよ」

―今話してくれたようなことと、今回ソーリーのアルバムがフォーク的なアプローチに向かっていたこととの間には関係があると思いますか。
アーシャ「あると思う。ただ、2ndの曲を書き始めた時はまだ(ブロードサイド・ハックスは)始まってなかったからね。キャンベルがいくつかのフォーク・ソングをインスパイアしてくれたというのはあると思う。彼は私たちのためにいい曲を見つけてきてくれるし、私たちは彼の“人生”を楽しんでいて」
ルイス「僕たちは今回のアルバムで、グループとしてより“コミューナル”になったんだと思う。だからそこには共通点があるかもしれないね」
マルコ「ブロードサイド・ハックスに関していうと、多くのミュージシャンを一つのスペースに集めるのに最高の場所なんだよ」
ルイス「それも、僕らよりもずっと才能のあるミュージシャンが集まってくる(笑)」
―ちなみに、前にスクイッドのメンバーにインタビューをしたら、最近のマンチェスターでは週末なのにフォークやアコースティック系のイベントが多く行われていて驚いたと話していました。
リンカーン「クリックルウッド(北ロンドン)にはアイルランド人のコミュニティがあって、アイリッシュ・ミュージックのナイト・イベントがよく開かれているね。あと、東ロンドンにMOTH Clubという最高のヴェニューがあって、そこは元々フォーク・ミュージックのイベントから始まったようなところで、そこではそういうイベントが今でもよく行われているよ」
キャンベル「MOTH Clubはブロードサイド・ハックスのホームでもあるんだよ」

―まさにそうしたコミュニティやヴェニューを中心とした“シーン”に関わる話だと思いますが、最近のイギリスの若いミュージシャンにインタビューをすると、ジェントリフィケーションの話題になることが少なくありません。みなさんの地元はどうですか。
ルイス「ああ、まったくね。ロンドンはこの5年間で状況がかなり悪化している。政府を見ていても、芸術の価値や、カムデンのような場所を存続させることにあまり関心がないように感じる。僕たちがティーンエイジャーだった頃と比べて、あの場所はまったくの別物に作り替えられてしまった。以前は4つほどあったヴェニューも今はすべてなくなってしまった。そして、The Windmillのように残すべきものでさえも、資金調達のために策を講じなければいけなかったわけで」
リンカーン「Kickstarterのようなサイトを使って資金集めのためにね。まったく政府は馬鹿げてるよ。バーがどうなろうとどうでもいい。彼らが興味あるのは、グレイソン・ペリーやダミアン・ハーストのような一部の画家やアーティストだけ。お金にならないものは優先されない。つまり、金、金、金。それも巨大な金。だからたとえば、音楽産業がもたらす金額が農業がもたらす金額よりも経済的な助けになることを理解していない。それが今起きていることの真実なんだよ」
アーシャ「私の場合はロンドンが地元で、それは運が良かったんだと思う。でもキャンベルのようにオックスフォードから引っ越してきたり、外から来る人にとってロンドンで生きていくことは大変だと思う。とにかく物価が高いから。ロンドンで成功する人には、ある特定のパターンみたいなものがあって。それは生活ができるだけのお金があって、とても野心家で、クリエイティヴな人で。逆にそうではない人、繊細な人はかなり難しいし、苦労するかもしれない。だから、ロンドンではヴェニューがないだけでなく、それに従事する人材も不足している。それも問題だと思う。クリエイティヴな仕事をしている人たちや、イギリスのさまざまな地域に移り住んでいる人たちにとって、ロンドンはもはやハブではないんだと思う。だから、ダメな芸術やダメな音楽云々という話ではなく、そもそも何か新しいものを生み出したり、将来的にアーティストになりうる人々が不足しているということなんだと思う」
リンカーン「ロンドンは常にサヴァイヴを続け、変化している。おかしなことに、それは1980年代から起こっていることだと思う。ある地域が高級化し、貧しい地域に小さな会場ができ、いろいろなものがオープンしたりして移り変わっていく。それがこの先どうなっていくのか、少し興味はあるけどね。まあ、今がどん底の時期だとは思うけど(笑)。でも、ロンドンの歴史が興味深いのは、そうやって戦い続けて培われてきたところだと思う」
キャンベル「小さなコミュニティやヴェニューが、そうした(再開発された)場所の外に出現するんだ。だからひとつのヴェニューが閉鎖されても、少し離れた別の場所に新たなヴェニューがオープンしたりするんだよ」
ルイス「状況はよりハードだけど、それでもロンドンに移住する人が今もいるのは、ここがクリエイティブな場所であることに変わりがないからだと思う」
アーシャ「ロンドンに移住する人はいると思うけど、でもそれは一握りの人たちだと思う。それができるのは特定のタイプの人たちだけで。実際、ロンドンに行くことを本当に恐れている人たちもいると思う」
キャンベル「自分の芸術やビジネスに専念する自由がない。無名のバンドであれば、家賃を払うためにたくさん働かなければならない。だから、人々がただ芸術をすることができるような小さなコミュニティのようなものがなくなってしまう。アートは今、そのせいで苦しんでいるんだと思う」
リンカーン「政府の資金不足もその理由のひとつだ。家賃や住宅の問題も、結局それは国全体の問題であるわけで。だからヴェニューが生き残れない、レストランも潰れてしまう。まったく馬鹿げた話だよ」
Photography Marisa Suda(https://www.instagram.com/marisatakesokphotos/)
Text Junnosuke Amai(https://twitter.com/junnosukeamai/)

Sorry
『Anywhere But Here』
(Domino / Beat Records)
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12896