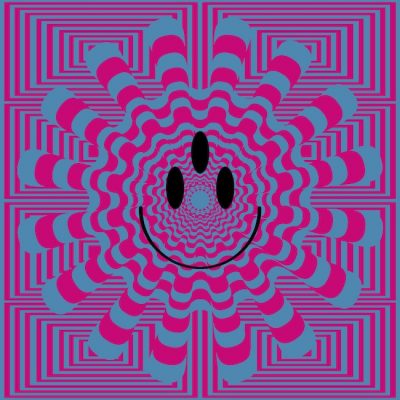11月11日(金)から11月13日(日)にかけて、北千住の『BUoY(ブイ)』と日暮里にある『元映画館』の二会場で開催される、街であがいている人のためのアートフェスティバル、『水平都市 (FLATLINE CITY)』。
アートからクラブ・アンダーグラウンドシーンまで、今東京を一番盛り上げていると言っても過言ではないアーティストやクリエイターたちが一堂に会するこのフェスティバルの特徴は、美術やクラブカルチャー、ストリート的姿勢とアカデミックな視点など、従来交わりあうことのない分野や領域を横断している点だ。
ラインナップも、巷に溢れた「ボーイズクラブ」的なイベントやフェスティバルとは一線を画した、前衛的で想像のつかないプログラミングとなっている。
そして来場者と卓を囲むラウンドテーブルが企画されているなど、参加者を「見る者」と「見られる者」に分けるような大型フェスティバルやクラブイベントともまた違う、双方的で有機的な人と人を結びつける場となるよう構想されている。
開催に向けて、主催の映画監督/アーティストの石原海、フォトグラファーのJun Yokoyama、DJ/イベントオーガナイザーのYiqing Yanに話を聞いた。
――まず、なぜこのフェスをやろうと思った?
海「長い間、一人でクラブとか展覧会とか映画の上映に行って、当たり前だけど一人でアイディアを考えて作品を作り続けてきた。でも、だんだんこれって自分の中の発想しかないから限界があるんじゃないかって思うようになって。例えば全然知らなかったジャンルの話でも、その分野に詳しい人と仲良くなったら必然的にちょっとずつ学んでいったり、考えたりすることがあると思う。だから政治とか色々なことを考えていく上で、クラブも好きで美術も好きで映画も好きな人たちが、有機的に集まって解散していく祭りみたいなことができたらいいなって。
いまでは周りに尊敬できる友達がたくさんいて、いろんな情報源がある。そのおかげで、今の自分の政治的思想とか価値観が形づけられている気がする。だけどコロナ禍で一人でいることが多いと、そっちの方向に行っちゃ駄目だよって人にも言いづらくなっていくし、自分も人に怒ってもらえる機会が少なくなっている気がして。だから、例えば何人かで集まって対話をしていくことで、自分の考えが過激な方向に行かずに済むんじゃないかなって思った。あとは例えば機材の使い方を聞くことができたり、逆にこれから作品を作りたいと思うひとに私が教えてあげられることがあったり、展覧会の感想を真面目に話せる人たちと集まったり、仕事をシェアしあうことができたりする仲間が欲しいなって思って。そんなふうに絶望的なこの社会を生き抜いていくためのプラットフォームを作りたいと思ったことがきっかけで、このフェスティバルをやりたいなと思いはじめた」

北千住「BUoY」https://buoy.or.jp
――イーチンとはなぜ一緒にやることになったの?
海 「イーチンはクラブで遊んでるだけじゃなくて、読書会を開催したり、政治的なことや哲学的なことも考えているところが好き。っていう側面もあるけど、単純にあるタイミングでイーチンのDJを聞いたときに、マジでその年のベストで。DJも好きだし考えてることも好きだから、シンプルに一緒にやりたいなと思った」
イーチン 「あと、私が海ちゃんとJunさんがカバーしきれないような、アングラだけどクリティカルに考えられるようなクラブ周りの人たちを誘って一緒に何かできたらいいかなって。だから水平都市に関わってくれている人たちは、みんながみんな、普段遊んでいるときには必ずしも同じ場所で遊ぶような人たちじゃない」
――こんなに色々なジャンルの人たちが一堂に会する機会はなかなかないよね。Jun Yokoyamaさんはなぜ参加しようと?
Jun Yokoyama「普段は音楽の写真などを撮っているんだけど、クラブで展示をしたりデモのアフターパーティのオーガナイズをしたりもしてた。でも音楽のイベントって、なかなかゆっくり話すための時間がない。だから、最近観た映像や読んだ本や聞いた音楽について喋ることができる場所を作っておかないとみんなバラバラになって、『とりあえず仕事頑張っていればいいか』みたいになっちゃうかなって。個人を集合的な力にするためにもぜひやりたいと思った」

元映画館 https://www.moto-eigakan.com
――みんなのそういった人を結びつけたいという思いは、水平都市のどういった部分に反映されてる?
海 「ラウンドテーブルでは、当日来場した人たちも一緒になって話せるようになってる。あと会場の中に休憩スペースを設けて、来場者の人たちがそこにたまって話したり、メンバーや出演者も誰かしらそこにいてある程度モデレートしながら、会話が生まれる場所にしたいと思ってる」
Jun Yokoyama「美味しいおやつとホットワインやお茶も振る舞います(笑)」
海「ホットワインは個人的にも楽しみ!あと水平都市メーリングリストを作りたいなと思ってて。例えば、『来週展示の搬入があって手伝ってくれませんか』とか『この展示がすごい良かった』とかいった内容で不定期に勝手に送りつけるのをやりたいなと。
インスタとかで、フォロワー数が多い人が『なんか探してます』って言ったらすぐに返信がたくさん返ってくるけど、フォロワー数が少なかったらあんまり返ってこない。そういう全部SNSの人気次第みたいなのってどうなのかなと思ってて。誰しもが平等に、いろんなことを聞いたりお願いできるメーリングリストをやりたい」
――民主主義的で良いアイデアだよね。若い人たちが来やすい施策もある?
海「私が若い頃、とにかくお金がなかったから行けなかったところがいっぱいあった。クラブに行っても、ブラジャーに小さいウイスキーを入れて飲んだり、トイレの水道水を飲んでたりしてたんだよね。だから今回のチケットは、学生とユースはBUoYが1日昼から夜まで出入り自由で1,000円、元映画館は2日両日出入り自由で1,500円と、できる限り安く設定した。いままでこういうところにアクセスできなかった人たちがアクセスできるような場所になればいいなと思ってる」

――クラブのチケットって高いもんね。一日目のオープニング上映の映画『So Pretty』については?
海 「『So Pretty』は、一緒に映画をブッキングした増渕愛子が紹介してくれた。この映画はニューヨークに実在するクィア・ポリアモリーのコミュニティのドキュメンタリー。監督のジェシカ(Jessica Dunn Rovinelli)が考える、社会学的な実践を映画に落とし込んだ、ある意味、映画で運動の実践をしているような、そんな映画。
ジェシカがインタビューで『この映画を作っていたとき、途中で結構興味がなくなってしまったんだけど、この映画をダンス映画として捉えることでまた映画を作りたいという興味が湧いてきて、完成することができた』って言って。実際に映画のなかで、みんなでブルックリンのクラブに行くシーンがあって。クラブで踊るっていう、ある種の人たちにとっては日常の風景が映画の中では特別な感情になっている。それ以外のシーンはみんな喋りまくっているんだけど、クラブのシーンは音がうるさいから会話ができない。その瞬間に、言葉にならない感情が表に出ててすごく良い。
あと、この映画はクラブやアンダーグラウンドカルチャーと、美術や映画や音楽を繋げるという意味で今回にぴったり。連帯することで、この世界で生き抜いていく方法を見つけることができるというメッセージが強く含まれている映画だと思うから、いま日本で生きてる人、特に若い子たちに観てもらいたかった」
――上映の後にラウンドテーブルが予定されてるけどそれはどのように決まったの?
海 「“多様な愛の形について”というテーマで、それぞれがアーティストの、金川晋吾と百瀬彩と斉藤怜司っていう同居するパートナー関係の三人を呼んだ。彼らは、3人の生活を4年ぐらい続けている人たち。モノガミー的な関係じゃない中で、変わりゆく愛の形が制作とどう繋がっていくのか、『So Pretty』と比較しながら、考えていければと思っているラウンドテーブル。
イーチン 「その後にはパフォーマンスもある。オーストラリア人でクィアなパフォーマンスをしているLuke Macaronasと、晩年の土方巽演出の全作品に出演されていた日野昼子さんにストリップショーをやってもらいます。Lukeはクィアな視点と、自分の生まれた国と違う国で活躍しているところが、「この街であがいている人」というテーマに合うかなって思って誘った」
海「日野さんの所属されている解体社を調べたら、一番最近のパフォーマンスが、マーク・フィッシャーの『資本主義の終わりより、世界の終わりを想像するほうがたやすい』という有名な言葉を引用しながら、フィッシャーが晩年にデリダより援用した『憑在論』をキーとして制作された、資本主義リアリズム演劇、と書いてあって。残念ながらその演劇は観にいくことができなかったんだけど、もうこの説明文だけでかなり痺れた。それに、もちろん土方巽もヒーローというか、未だに大きな影響を及ぼし続けている重要な存在だから、日野さんとLukeの組み合わせのパフォーマンスは絶対におもしろいんじゃないかなと」
Jun Yokoyama 「気がつけば自然とジェンダー、セクシュアリティとか、クィアネスに関する演目が多い」
海 「自信を持って言える、おもしろいと思うアーティストたちを無我夢中でブッキングし終わって気づいたのは、出演者のほとんどがシス男性以外だったということ。もちろん、世の中にいっぱいあるボーイズクラブみたいなフェスティバルとは違うことをしたいという最低限の意識はあったけど、絶対にシス男性はいやだとかはまったく思っていなくて、なんだか自然にこうなった。その理由を考えたときに、クィアの人やセクシャルなものを扱ってる人たちって、もちろんある種のマイノリティだから、こう言ってしまっていいのかはわからないけれど、社会にうまく適応できないなと思ってしまう人たちのマイノリティ性が、一瞬だけ、どこかで呼応するところがあるのかなと思った」

Phew
――なるほどね。12日はライブショーケースがいっぱいあるけど人はどうやって選んだ?
海 「ブッキングしていくうちに、ふと気付いたらシス女性が少なくて、クイーンが必要だと思ってPhewさんに声をかけた。クイーンって誰だろうって考えたときに、私の中のクイーンがPhewだったから。音楽だけじゃない領域でやってきた人でもあるし、長い間ずっと作品を作り続けて、変わらずにめっちゃかっこいいって、本当に奇跡のような人だと思う。ここまでずっと一貫してかっこいいクイーンは、Phewさんしかいない」
イーチン 「Aisho Nakajimaは、インスタでずっと気になってたけど、水原希子ちゃんのイベントではじめて会った。それまで抱いていたイメージはギャルだったけど、実際に会ってみたらアイデンティティやセクシャリティとかすごく色々なことを語れる人だった(https://www.neol.jp/culture/94361/)。ちょうどよりアートの分野でパフォーマンスをしてみたいと言ってたので、タイミングもテーマも水平都市にぴったりだと思ってお願いした」
海 「Sapphrie Slowsさんは藝大の音楽環境学科を出ていて美術のバックグラウンドを持っているから、今回のテーマとばっちり合うし、なにより政治的な話とかクラブシーンの問題を積極的に話してる印象もあった。久しぶりにSapphrie Slowsさんのライブを観たいという下心もありつつ、パフォーマンスがいいだけじゃなくて、思想がしっかりしてる人に出演をお願いしたいなと思って」
――12日はラウンドテーブルもいくつか予定されているけど、議題やメンバーはどうやって決まった?
海 「“クラブカルチャーと美術の越境は可能か?”っていうテーマで、私とMESのKANAEちゃんと代々木祭の3人のラウンドテーブルがある。3人ともそれぞれ東京藝大に在籍していたか、今も在籍してて、美術のバックグラウンドだけど、よくパーティに行ったり、パーティーを企画したりしてる。
そもそも美術って、いまだに権威主義とか資本主義とすごい繋がっていて。でもクラブカルチャーっていうのは元々LGBTQコミュニティからアンチ資本主義的に出てきたもの。だから、美術とクラブって持ってる性質が全然違うけど越境は可能なのかどうなのかを考えたいなと思ってる。
もうひとつのラウンドテーブルは、ライターの鈴木みのりさんと、『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』の著者の一人である社会学者のハントンヒョンさんと、エトセトラブックスの松尾さん、聞き手に『me and you』の野村由芽さんの4人を招いてカルチャーとポリティカル・コレクトネスについて語るラウンドテーブル。『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』の本を軸に、出版と運動について、一般の人たちに向けてフラットに話してもらおうという企画」

MIRA SHINDENTO
――自分も何かを作ったり企画するなかで、ポリティカル・コレクトネスについていろいろ考えてきたので、すごく興味のあるトピックです。13日のアーティストやパフォーマーはどうやって決まったの?
イーチン 「“パーソナルな経験の場としてのクラブ”というテーマで2つのオーガナイザーに話を聞く。『SLICK』はセックスポジティブなアウトドアのレイヴ。『デパートメントH』は、お酒と踊りが好きじゃない人たちも楽しめるコミュニケーションの場所。一見近いようだけど、両者のステートメントは真逆だから、組み合わせてみたら面白かなと思ってお願いした。いかに異なるポリシーを掲げる人達が、それぞれの場所でどうやってパーソナルさを表現したり、シェアできるのかを聞いてみたい」
海 「“パーソナルな経験の場としてのクラブ”というラウンドテーブルは、個人的に一番思い入れがある。私自身クラブってめちゃめちゃパーソナルな場所だと捉えていて。いろんなパーティーに行き続けてきた中で、1人で行って1人で帰っても、ここは自分のパーソナルな場所だって思えるパーティーに出会えることができた。パーティーに行ってそう思えるようになったり、そこにいる人たちと出会えるまでにすごい時間がかかったけど。クラブって、コミュニティのように見えて、ランダムな人がたった一人で行くことができるパーソナルな場所にもなりうると思っていて。クラブっていうのは、ある種コミュニティに入れないタイプの人でも、ただそこで踊っているだけでも、もはやただ暗闇で突っ立ってるだけでも、なんだか許されるような場所であるっていういう想いが私はあるから、タイプの違った2つのパーティーオーガナイズしてる人に聞いてみたい」
イーチン 「そのあとのMIRA新伝統には、“体を取り戻す”というテーマでパフォーマンスとトークをしてもらう」
海 「私はこのフェスティバルをやりたいなと考えていた去年の段階から、MIRA新伝統に出てほしいと思ってた。サイバーっぽい雰囲気もありながら、ちゃんとアカデミックな要素も残ってるそのバランス感覚がすごい面白いなと思って。パフォーマンスなんだけど音楽的でもあるし、コンセプトもしっかりしていて、彼らのようなアプローチの人って日本に少ない気がしていて。MIRA新伝統もマーク・フィッシャーが気になってたり、ミーティングしていた時にミシェル・フーコーの話が出てきたりと、私たちが考えていることとMIRA新伝統の実践は、なんとなく深いレベルで繋がってるような気もしている。
そのあとのラウンドテーブルで、MIRAの実践を解きほぐすような存在が必要だなと思っていたときに、ちょうど篠田ミルがマーク・フィッシャーの話を引用しながらBurialの新しいアルバムについて書いているテキストを思い出して(https://turntokyo.com/features/burial-antidawn/)。ミルだったら東大の修士で学んだり、DJとしてクラブにもいるから、アカデミックなあり方とMIRAの考えてることをもっと普遍的なものに繋げてくれるかなと思ってお願いした」
――イーチンが聞き手のラウンドテーブルもあるよね。
イーチン「『IWAKAN』はマガジンとして、真剣だけどユーモアいっぱいにやってる団体。『脱衣所』は、秘密結社みたいに10人ぐらい集まって勉強会とかやってるグループで、オーディエンス的にはちょっと違うんだけど、両者ともにコミュニティの作り方とか、スペースとかメディアとしてのビジョンとかについて話してもらおうと思ってる」
海「それから3日間を通して、いろいろな展示もやってます。パフォーマンスやラウンドテーブルの間も飽きさせないというか、逆にここでなにか交流が生まれたらいいなと。
『loneliness books』はクィアネスや人種に関する本などを扱っている本屋さんだから、出てもらいたいと思って声をかけました。『deepbluesea』は、映画とクラブを横断してる存在。日本におけるダンスミュージックのフライヤーアーカイブの展示と、今回のテーマに沿った本のセレクションで来てもらう」
イーチン「『Evil Spa』はすごいパンクな男の子たちがやってるイベントで、ZINEを出してもらう。あとは服のポップアップもある。新宿の『見た目。』っていうスペースのメンバーの一人の渡辺未来さんが、自分で植物を植えて作った、自然の染料で染めた服とか。普段はオンラインでしか販売してないoh, iconic dogsの古着のポップアップも」

loneliness books
――2日目からは元映画館での映画上映もあるよね。その映画はどうやって選んだの?
海「長編を2本、短編選集で4本、合計6本、すべて多様な手法を使って撮られた一筋縄ではいかないようなドキュメンタリー映画を上映する予定。テーマは「裂け目からの視点」まだ観たことのない世界に注意を向けること、裂け目からの視点をたどることが、あなたと他者をつなぐものになるんじゃないかってアイディアのもと、プログラムした。長編映画にはオープニング上映として先ほど話した『So Pretty』と、もう一本『I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die』の上映もある。『I Love You ~』は、自分で映画祭をするんだったら絶対上映したいって思っていた作品。アメリカのコロラド州で10人で一つの狭い家に住んでいる家族と、その友人のコミュニティの話。かなり破壊的なコミュニティで、例えば、若いお母さんが汚いシンクに産まれたばかりの赤ちゃんをつけて、水でバシャバシャ洗ってるシーンがあったり、見てると痛々しいシーンがすごいある。ここでは言えないようなことがたくさん起こる強烈な映画なんだけど、彼らの姿をヤバい奴らとして描くんじゃなく、彼らの生(なま)の生き様を表すことで、この現実の中に宿る輝きみたいな瞬間を捉えた映画」
――最後に、水平都市に来てくれた人たちに、帰り道どんなことを感じて、考えながら帰ってほしい?
イーチン「めっちゃ感情的に訴えるとしたら、水平都市で話すようなことを考えてるのは自分だけじゃないみたいなことを感じて欲しいかな。あとは、パフォーマンスを見たとして、パフォーマンスはライブでしか見れないとかじゃなく、その文脈だけじゃなくて何かいろんな文脈であり得るってことを感じて持ち帰ってほしい。クィアなことはクィアスペースでしか語れない訳ではない、とかね。自由に有機的な繋がりを感じとってほしい」
海「こんな大変でお金も時間もすごくかかるフェスティバルを開催しようとしてみて、もはや合理性とか持続可能性とかはないかもしれないけど、私は水平都市を継続してやっていきたいと思っていて。例えば今後はフェスティバルって形じゃなくて、小さな食事会とかレイヴとか展覧会とかデモとか、その時々のそれぞれのムードであったことを緩やかに長く続けていきたい。そこにいたりいなかったりする人たちがいて、居場所がない人が流れてきて、なんとなくコミュニティができて、そういうプラットフォームみたいなものになればいいのかなと思ってる。
でも、もし私が10代でこういうイベントに来たら、たぶん誰とも話さずに帰ってくることになったと思う。でも、ひとりで行って帰ってきて、っていうこともすごい重要だと思っていて。いつかあの場所に行った、水平都市に行ったことを、例えば5年後とかにクラブで会った子に話したら、その子も当時行って、それがきっかけでめっちゃ仲良くなるとか、本当にそういうことってあるから。だから今回の一回だけで、何かを受け取って帰ってほしいなんて私はあんまり思っていなくて。ひとりぼっちだったとしても、水平都市に来たこと、ここで観たこと聴いたこと、この場所にいたというその事実が、来てくれた人にとって5年後とか10年後に生きていくような、そんな場所になればいいなって思ってる」
Jun Yokoyama「今回KUMA財団に会場や音響照明機材とかのお金を助成してもらってるけど、予算なんかぶっとばして超えてしまって、いろんな人に出演してもらったり、想定よりたくさんの映像作品を上映したりして持続可能な感じでやってない。どれだけの人が来てくれるかもわからないし、採算性もなんにもない。だから来る人には、またすぐこういうイベントは無いかも、と思って来てほしい。『東京都や◯◯区を盛り上げましょう』とか『オリパラを盛り上げましょう』とかでもなくて。そういう無駄とか余剰みたいな、批判的な時間と場所を作るっていうのは、この超資本主義都市の中ですごい大事なことだと思う。むしろこのイベントに来たらむしろ社会の中で生き辛さの方が多くなるかもしれない。『なんでこの街はこんなんなんだよ…』みたいな。
でも海ちゃんが言ってくれたことって、伝説を作るってことでしょ。5年後とかに誰かが『数年前に水平都市っていうイベントがあってね』『え!私も行ってたんだけど!』みたいな会話があって、それを聞いたさらに若い人が『水平都市かぁ、行きたかったなぁ』みたいに言うわけでしょ」
海 「伝説(笑)。でも確かに、正直もうこの規模ではないと思う。誰かが一千万円とかくれたら、第二回があると思うけど。だから可能性としては、水平都市で出会った人とかと一緒に何か小さくやっていきたいと思う」
Jun Yokoyama「伝説じゃん」
海 「(笑)。持続していくかどうかはわからないけどまた絶対やろうよ。でも確かに、この規模でまたすぐあると思うなよってみんなに言いたい。だから絶対に来た方がいいと思う」

photography Jun Yokoyama(https://www.instagram.com/yokoching/)
text Lisa Tanimura(https://www.instagram.com/_lisatani_/)

長編映画
『So Pretty』 監督: ジェシカ・ダン・ロヴィネッリ (82分 / 2019)
『I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die』 監督: エヴァ・マリー・ロドブロ (76分 / 2019) 短編映像
『Not Just A Bowl of Fruit』 監督: グレタ・グリニュート (3分 / 2022)
『私たちの家族』 監督: 雨夜 (30分 / 2021)
『シグナル8』監督: サイモン・リュー (13分 / 2019)
『Ein Aus Weg』 監督: サイモン・スタインホースト&ハナ・ロッテ・ストラグホルズ (19分 / 2017)
日時
11月11日 (金) 18:00~21:30 北千住BUoY
11月11日 (土) 12:00~21:30 北千住BUoY / 11:00~21:00 元映画館
11月13日 (日) 12:00~21:30 北千住BUoY / 11:00~21:00 元映画館
タイムテーブル https://flatline.city/timetable/
場所
北千住BUoY https://buoy.or.jp/ 〒120-0036 東京都足立区千住仲町49-11
元映画館 https://www.moto-eigakan.com/ 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里3丁目31−18 旭ビル サイト
https://flatline.city/
チケット
北千住BUoY 各日 一般 2,000円 学生&ユース 1,000円
元映画館上映チケット 各日 一般 2,500円 学生&ユース 1,500円
https://flatlinecity.zaiko.io/
お問い合わせ hi@flatline.city
NeoL読者チケットプレゼント
【募集人数】5名様
【締切】11月10日(木)
応募メールはこちらから。氏名/年齢/メールアドレスを送信ください。(←クリック)ご応募お待ちしております。

『変化する多様な愛について』
スピーカー: 百瀬文、斎藤玲児、 金川晋吾
聞き手: もりたみどり
NYのクイア・ポリアモニーコミュニティを題材にしたJessica Dunn Rovinelliの映画『So Pretty』の上映後トークとして、アーティストの百瀬文、斎藤玲児、 金川晋吾の3人を招いたラウンドテーブル。ラディカルな家族の在り方、コミュニティとして機能する家族の可能性について、家族として共に過ごしている3人の生活を軸に展開する。同時に各自の作品紹介を交えながら、アーティストとしての実践と生活がどう接続するのかを考える。聞き手にはトランス女性の妻を持つ(元映画館で上映する映画「私たちの家族」を観てね)、美術家でパーティーオーガナイザーのもりたみどりを呼び、3人の生活について率直に質問を投げかけてもらう。
『Is It So Complicated?: 美術とクラブの越境は可能か?』
スピーカー: KANAE(MES)、石原海、代々木祭
美術史を参照すると、美術というものが権威主義と密接に関わりあって形成されてきたメディアであり、デュシャン以降の現代美術と呼ばれるものですら、やはり権威や資本主義とは切っても切り離せないものであるという現実がある。それに対して、クラブの歴史はかなり短く100年も経っていない。マジョリティや権威へのカウンターとして、階級、人種差別社会のシェルターとして、LGBTQコミュニティから生まれたダンスミュージックを扱うクラブカルチャーと、権威主義的な歴史を持つ美術の越境は可能なのだろうか?東京藝術大学に在籍中/在籍していた美術教育の背景を持ちながら、クラブカルチャーと密接に制作を続けてきた3人のアーティストが越境の参照点となる作家を紹介しながら、自身の作品について語る。
『都市空間における身体表現とメディアの抵抗実践』
スピーカー 脱衣所 Datsuijo、違和感 -IWAKAN
モデレーター Yiqing Yan
それぞれ東京を拠点に活動するプロジェクト・スペース【脱衣所 Datsuijo】と「違和感」を問いかけるペーパーマガジン【IWAKAN】にそれぞれのビジョンや実践の紹介を通じて、アンチキャピタリストなメディア・スペースのあり方を模索する。脱衣所は、〈私〉と〈公〉が入り混じる中間領域をテーマに、パフォーマンス、上映、討論会など、私的且つ政治的な展示やイベントの企画を秘密結社のように着々と進めている。一方、IWAKANは、アートエディトリアルからアカデミックな対話まで網羅し、紙媒体を介して地方でもポップアップを行うなど、LGBTだけではなくジェンダーなど広いテーマにユーモラスかつ真剣に向き合う。
『“Club as Our Personal Space” ー パーソナルな経験の場所としてのクラブ』
ゲストスピーカー: ゴッホ今泉(デパートメントH)、もりたみどり(SLICK)、石原海
モデレーター KANAE (MES)、Yiqing Yan
『パーソナル』の定義から、パーソナルでなくちゃいけいない理由、シェアされるパーソナルさからなる集団的経験、場所づくりにおいてパーソナルさはどうやって守られ、誰によって維持されるのか?騒ぎたがらないキッシュ、スカム、モンドな人たちのための享楽的なコミュニケーションの場を提供する、元キャバレーであった鶯谷キネマ倶楽部で月一行われるFETISHパーティデパートメントHのオーガナイザーのゴッホ今泉と、募金やデモへの呼びかけ、アクティビズム活動やからセックスポジティブをポリシーに掲げる東京屈指のクィアパーティSLICKのオーガナイザーとの対談。
『セルフケアを編み直す ー 身体/セルフケア/儀礼』
スピーカー: MIRA新伝統、篠田ミル
「瞑想、ヨガ、適度なワークアウト、バブルバス、美味しい食事はどうだろう。自分をメンテナンスしてあげよう。生産性を上げるために。#セルフケア」セレブリティからスタートアップの社長やアーティストにいたるまで、セルフケアは現代人にとっての必須のスキルとして喧伝されている。自己の心身を労わることは過ストレスな後期資本主義社会において個人の責務であり、セルフケアとはつまるところ各々が歯車としての自己に油をさしてあげることなのだ。
しかしながら歴史を辿ってみると、セルフケアという概念は1960年代の公民権運動や女性運動の中でコミュニティにおいて心身の健康を培っていくための集合的な実践として企図されていたことがわかる。セルフケアとは、個人に分散された順応の身振りではなく、むしろ集合的な抵抗の実践だったのだ。
我々は #セルフケア として無惨にも離散してしまったセルフケアをどのようにして集合的な抵抗の実践として編み直すことができるだろうか。MIRA新伝統の方法論である”儀礼”や”悲劇”などをヒントに議論していく。
『多声の風を招き入れる—カルチャーとポリティカル・コレクトネス』
スピーカー:鈴木みのり 野村由芽 ハントンヒョン 松尾亜紀子
ポリティカル・コレクトネス(PC)の訳語は「政治的正しさ」や「社会的望ましさ」などさまざまだ。しかし、PCは炎上しないための表現ルールではないのにもかかわらず、PCにポジティブな人であっても、何がPCとして正しいのか、自分の表現は大丈夫だろうか(間違っているのではないだろうか)と疑心暗鬼になったり、試行錯誤している人も多いのではないだろうか。
今秋、出版された書籍『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』を参考に、PCを以下のように定義してみる。「PCとは多様な人々が生きる不均衡・不平等な社会の中で、個人が他者とコミュニケーションするためのルールであり、協働的に社会構造を変えていくための生きた方法である」と。では、PCはカルチャーという能動/受動、私的/公的なものが混じり合う表象の場を、どのようにして多声の方角へと開くのだろうか?
『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』の著者の一人である社会学者のハントンヒョン、フェミニズムにかかわる本の出版や書店活動を行うエトセトラブックス代表の松尾亜紀子、ジェンダー・セクシュアリティ、フェミニズムの視点から文化・文芸批評や文筆をおこなう鈴木みのり、そして聞き手に個人と個人の対話を出発点に社会構造の問題に目を向け、考え、語り合うメディア『me and you』の野村由芽、この4人の対話を通じて、ポリティカル・コレクトネスとカルチャーが拓く、わたしたちの自由の可能性を探る。
参考文献:『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』(清水晶子/ハントンヒョン/飯野由里子、有斐閣、2022)
プロフィール
石原海
アーティスト/映画監督。愛、ジェンダー、個人史と社会を主なテーマに、フィクションとドキュメンタリーを交差し ながら映像を主なメディアに制作している。長編映画『重力の光:祈りの記録篇』が第14回恵比寿映像祭でプレ ミア上映、その後シアター・イメージフォーラム他全国劇場公開。(2022)初長編映画『ガーデンアパート』短編 『忘却の先駆者』がロッテルダム国際映画祭に二作同時選出(2019)また、英BBC/BFIテレビ助成作品『狂気の 管理人』(2019)を監督。第15回資生堂アートエッグ入選(2021) 英国の現代美術賞Bloomberg Contemporary入選(2019)など。
Jun Yokoyama
2015年、ロンドン大学SOAS在学中に写真を始める。マグナム・フォト所属のサイモン・ウィートリーにドキュメン タリー写真を学び、ロンドンのグライムシーンで撮影した写真が高く評価される。Apple “Shot on iPhone on tour”のフォトグラファーに抜擢されるなど東京をベースに各地の音楽シーンで活動中。
Yiqing Yan
イベントオーガナイザー、DJ。人間性豊かな環境を東京のカルチャーシーンの中に取り入れるマルチメディアコ レクティブether、NEON BOOK CLUBのメンバー。Hong Kong Community Radioレジデント。
https://flatline.city
https://linktr.ee/flatlinecity
https://www.instagram.com/flatline_city/