
1990年代から未成年の少女たちの支援・調査に携わってきた上間陽子が、2016年夏、うるま市の元海兵隊員・軍属による殺人事件をきっかけに、沖縄の性暴力について聞き取り調査に参加した女性たちの承諾のもとに書いた『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』(太田出版、2017)は、出版界のみならず社会学の観点から、また福祉や教育の現場からなど大きな反響を呼んだ。そこから3年、2020年10月に上間初のエッセイとなる『海をあげる』(筑摩書房)が刊行された。普天間に住み、100dbの騒音の中で家族と食事を作り、日々の生活を送りながら、変わらず少女たちの調査や支援を行い、同時に辺野古への基地移転に反対しての座り込みに参加するーー丁寧に紡がれる暮らしや人との関係、そことあまりにもつながらない政治。自身を晒しながら少女たち、そして沖縄の人々の生活を覆う国、政治への怒りを描いた『海をあげる』について、イ・ミンギョン『私たちには言葉が必要だ フェミニストは黙らない』(タバブックス)チョ・ナムジュ『彼女の名前は』(筑摩書房)など社会を変えるような韓国文学の名著たちをすんみと共に翻訳してきた小山内園子が聞き手としてインタビューを敢行。翻訳家として、またソーシャルワーカーという女性の支援に携わる一人として、自身の経験を交えながらの誠実で切実な言葉が交わされる取材となった。
◆2冊に描かれる女性、家族、社会◆
――インタビューをさせていただく前に、まずお礼を伝えたくて。私はソーシャルワーカーとして女性の相談や支援も行っているんですが、ときどき、相談を受けるこちら側がたじろいでしまう相談があります。深刻な被害を受けた人にどう向き合えばいいのか。正しく「おろおろ」するにはどうしたらしいのか。そんなとき、上間さんの前作『裸足で逃げる』と出会い、相談員で自主的に勉強会をしたことがありました。特に次の部分に、教えられることが大きくて。美羽さんが、夫から暴力をふるわれた友人のもとへ向かう場面です。
“翼が暴行を受けた日の深夜、アパートに駆けつけた美羽は、「大丈夫?」と翼に問わなかった。それがすさまじい暴力であること、これまでその暴力を一身に受け続けてきた翼が大丈夫でないことなど、美羽には十分わかっていたからなのだろう。(中略)
だが美羽は突然、暴行直後の青あざがくろぐろと残る翼の顔のように、自分の顔にも、なぐられて青あざがあるような化粧をしはじめる。そして、「美羽も、くるされたみたいなかんじでやってきたよ!」と翼に呼びかける。”(「記念写真」『裸足で逃げる』p86~87より)
支える、支えられる、という関係じゃなく、こういう水平に助け合えないか、とみんなで話し合いました。なので、『裸足で逃げる』のことばにとても恩を感じているんです。その『裸足で逃げる』から3年。今回の『海をあげる』は非常にご自身のことを赤裸々に語っている印象が強かったです。
上間「赤裸々というのは、多分「美味しいごはん」ですよね。あれはもう20年も前の話ですが、発表は少し迷いました。書いた理由は本のためというわけではなく、話に出てくる友達に、私はなんとかこの問題を終わらせたというお礼状のようなものとしてです。そうやってまずは友達に向けて書いた「美味しいごはん」ですが、本の冒頭に持ってきたのは、この出来事が、自分の仕事や調査の女性たちとの関係の取り方のベースにある体験という意味があるので、自己紹介のようなつもりです。ずっとこの本の中核のエッセイは、「アリエルの王国」だと思っているのですが、まがまがしい暴力への怒りとそれが無視される現状を書くうえで、まずは私がどういう人なのか、なぜ女性の調査をしているのかという文脈を紹介する土台として必要だと判断したからです。全く違うものを書いたと思われるのですが、自分の生活や歩みは、2作の間であまり変化はありません。女性たちの暮らしのしんどさを作り出している政治にはずっと怒っているし、調査の子の一人の手術の同行日に普天間基地にオスプレイが来たので、私は前日に座り込みに行っていて、地元紙の一面には私が機動隊に引っ張られている写真も出ています。朝になって新聞を見て、青痣だらけのまま手術に同行して、手術が終わって家に帰ってきたら自宅の窓からオスプレイが次々と飛んでくるのを見た。どんなに生活を丁寧に作っていこうが、目の前の人に誠実でいようと思っていようが、国家権力というものはそういう日々を簡単に潰すなあと。そういう怒りは変わっていないけど、政治への怒りを扱うにあたって私は何者なのか、私の日々はどういうものなのかということを言葉として紡ぐことを意識しました。『裸足で逃げる』の時も、沖縄の暴力の根源を書きたいと思っていました。でも、データそのものからは米軍があまり出てこないということもありましたし、かといって米軍の爪痕の刻印があるデータは個人が特定されるということで、国家権力のような話にはならなかったんです。でも今回は、自分の生活そのものを描くことが、むしろ国家権力がなにをしているのかということに焦点をあてられるように思っています」
◆女性たちが「博打を打つ」理由◆
――『裸足で逃げる』は一人一人の女性にグッと迫っていく一方、『海をあげる』にはこの社会全体への怒りを感じました。例えば出産の場面など、前作とつながりのあるエピソードはありますか。
上間「出産や病院同行が多いので、そういった場面が度々出てくるんですが、本に掲載したそれぞれの出産シーンは別の子です。『海をあげる』は七海ですね。この時期、 七海がすごく大変で、最近これがようやくの安定かなという風になってきたんですけど、とにかく色々シビアで、書いたけれどまだ発表できない七海の原稿がいくつかあります。私自身、七海のしんどさにどうやって関わったらいいかがちょっと分からなくなる時期もあって、その時に調査としてとっているデータで原稿を書いて、点にしか見えないような彼女の行動を私なりに意味付けをしたものをまとめて、七海に読んでもらっていました。要するに私にできることは、傍にいて何が起きたのかを見続けて、記録をとることだという覚悟をした時期でもあります。だから『海をあげる』に登場している女の子たちは、『裸足で逃げる』の女の子たちよりももっと手強い、博打打ちと言ったらいいんですかね、そういう子たちのことを書いたと思っています。『裸足で逃げる』の子たちの多くはキャバクラで働いていて、美的資源を持っていて、かつルーティンを作れる子たちでもあるんです。お酒をどれくらい飲むと育児に差し障るか、お客さんと同伴やアフターをすると生活にどういう負荷がかかるのかなどがみえるような女の子たちと会っていた。もちろん、10代で出会ったインタビュー開始時には危うかった子もいます。それでも落ち着いていく。その筋道ができるのは、ほんの数年なんだと体感としても分かったように思います。でも今回書いている事例の場合、長期にわたる虐待があること、それが幼少期の始まり方をしていることもあって、ルーティンを作ることがすごく難しい。だから私から見たら博打にしか見えないような選択をするのです。それで出口が見えないというようなことがあったり、彼女たちにひどいことをした親に対しての怒りもあり、大事に思っているけれど振り回される自分もいて、振り回されながらもう一度、こういう風にしたのはこの子の親だ、親をそうさせたのは社会だ、とぐるりと回って考えるような時間でした。10年近くたってみて、『裸足で逃げる』の子たちは、良い話も多くなってきて、リスクを回避できるようになった子もいるし、家族を作って落ち着いた子もいるし、第二子や第三子ができた子もいます。やっぱり出会った頃とは全く違う。相当危ないと思った子もだいぶ落ち着いているので、『海をあげる』を書きながら『裸足で逃げる』の子たちのことも思い出して、大丈夫、5年経ったらもっと違うところに行くと考えていましたね」
――彼女たちが「博打」という選択肢を取る理由は何なんでしょう。
上間「最初からモデルがないから、博打にならないような選択肢を知らないというのはあると思います。例えば『裸足で逃げる』の京香は、ルイと結婚するにあたってお試し期間を1年間とったんです。私にも会わせたし、友達にも会わせたし、第一子の学校行事にも全部付き合わせて、この人で日常が回るかということをすごく考えていた。しかも、それをコミュニティでやりきった。仲の良いグループだったり、仕事の仲間だったり、私みたいな年上の人だったり、母親だったり父親だったりの検証にかけて、時間をかけて決められるんですよね。そういうコミュニティを持っていなかったり、どういうことがリスク回避になるかという方法を知らないと、問題を清算してくれるのは、ただ唯一、新しい恋人だけとなってしまう。新しい恋人には、家を借りるさいの保証人になってもらえる、新しい家族生活が営める、みんなのように幸せになれる。男性の気持ちはまったくわからない、でもこのまま行っても不利ならば、不利になるかどうかわからないけれども、子どもを産んで賭けてみようというところで博打を打つ。私はそこで、出産や子どもが掛金になるからすごく辛いんです。でも、それを調査として分析的に俯瞰するならば、両者の差異には、コミュニティがあるか、参考になるモデルがいるか、時間をかけられるかどうかというところもあるなと思います」
――見通しを持つような経験をしているかどうか。
上間「そうですね。ある選択の仕方を見ながら育っているのか、選択の仕方を率直にジャッジできる人が数人いて、ある選択についての反応を屈託なく話せるかどうかというのも大きいと思います」
◆<欲望>は作るのが難しい◆
眠るあの子は、以前は「ママ」と言うことができて、泣くこともできる子だった。「病気? 事故?」と少しだけ踏み込んで尋ねてみる。「事故。溺水。家のお風呂で溺れて」と、彼女はその日のことを話しだす。「誰がみつけた?」という問いかけに、「自分」と応えたあとで泣きだしてしまった彼女にかける言葉はたぶんこの世のどこにも本当にない。(「波の音やら海の音」『海をあげる』p114~115)
――相談の現場にいると、自分がどうしたいかをことばで発しない女性たちと多く出会います。とてもとてもしずかな面接だったり。「波の音やら海の音」を読んだ時、そのことを思い出しました。ひょっとしたら「あなたはどう思ってる?」「どうしたい?」という意向を聞かれる場がなかったのかなあと想像することもあります。
上間「欲望って実は作るのが難しいですよね。娘が赤ちゃんのころ、言葉もわからなくて泣くしかできないときに、娘の表出する不快感に名付けをしていくのは、親の側なんだと実感しました。お腹が空いてるのか、気持ちが悪いのか、寂しくなってるのかとか、無数にいろんな手立てや言葉をかけながら、そこにある不快感に名前をつけていく。そうやって分節化されることで、感情や欲望というのは作られていくんだなということを子育てをしていて感じます。同時に、本人は一生懸命発していてもひろわれてないこともありますよね。たとえば、七海と会い始めた最初の頃、七海は何を食べたいか訊いてもその希望を言えないということがスタートなんですよ。ただモスバーガーで朝ご飯を食べるのは、インスタ映えもするし素敵と彼女が思っている節もあって、会い始めたころは2週間に1回くらいのペースで朝ごはんを一緒に食べてたんじゃないかな。それで何かおしゃべりをして、バイト先まで連れて行ってバイバイって帰っていました。いまは、食べたいものを食べたいといい、不快感を説明してくれます。ニーズってうまれながらにないんですよ。ひろってくれる人なくしてニーズはできない。これは支援・介入のときに、必ず考えないといけないと思っています。
「波の音やら海の音」の3人も、おっしゃるように群を抜いて静かなインタビューでした。バービー人形みたいな母親と書いたんですけど、本当にモデルさんみたいな綺麗な子なんです。でもあの日、この子は真っ白な顔をしていて、呼吸器を外すかもなってくらいの危機感が私にはありました。でもみんな彼女のしんどさには目を注いでいなくて、介護している子どもにだけ目が行っているような状態で、その子の結婚相手のお父さんは連絡なしにお家に来て、彼女がうたた寝してたら怒鳴り散らすんです。そういう状態の中でインタビューをしていて、彼女から欲望というものが全然出てこない。子どもの溺水を発見した時から、時間が動いてないという感じでした。インタビューの始まる前に、眠っている子どもにご挨拶をして、さわってもいいか彼女に聞きました。いいといってくれたので、そばでママとお話をしていますよ、と話してからインタビューを始めました。静かなインタビューでゆっくりしか進まない時間でした。レコーダーをとめてから私が言ったのは、子どもが何かあったら母親は自分のせいだと思ってしまうけど、あなたのせいじゃないよということ。仕方なかったんだよって言ったら、泣いたんですよね。その言葉が適切だったとは思っていません。でも、ひととなにかを話して、感情のようなものが出てきた。帰る前にも子どもに挨拶して、その後、彼女の様子は少し変わったように思います。一番大きかったのは、行政の介入もできたということかと思います。
あともう一人の子。私はあの子がいなくなってしまった後に、あの子の母親に会いに行ったんですよね。40代になったばかりのお母さんだったんですけど、すごく欲望が薄い感じ。でも男の人に徹底的に翻弄されていて、シェルターや母子寮に入ったりしている。あの子の育ち自体がそのお母さんに合わせて転々としているような暮らしぶりで、お母さんはいまも恋人と暮らしている。母親の恋人と口論になり、母親の恋人から生意気だといって包丁を突きつけられたとき、彼女はお母さんから庇ってもらってないんです。そういうものに対しての諦めみたいなことも感じたし、会話は途切れるんだけど、それでもインタビューを終わって欲しいわけではなさそうなんです」
――言葉は少ないけど身体ではなにかを発している。一緒にいたり、ルーティンをともに過ごしたり。今のお話でいくと、欲望が薄いのではなく、欲望を名付けられる体験や名付けてくれる存在の不足、ということなんですね。
上間「連綿とケアされていく時間がないと、感情は名付けようがなく、欲望も形としてまとまりにくいと思っています」

◆家族、だけではなく◆
――どちらかというと「虫の目」目線になりがちな支援と違って、調査というのは、「鳥の目」で見つめ続けられるんだな、と思いました。その人の変化も含めて長く見守れる。
上間「そうでもないですよ。私もなるべく長く連絡が取れるように考えてはいるんですが、途切れる方ももちろんいて、インタビュー前後のその都度その都度、裏切らないようにするのが精一杯という感じです」
――彼女たちを見つめ続けるなかで、上間さんがいま真っ先に必要だと思っていることって何でしょう。
上間「難しいですね。でも、希望みたいなものじゃないでしょうか。「三月の子ども」の若い先生がお家に来て、泣いて話をしていて私は黙ってそれを聞いていたんですけど。ひととおり話を聞いたあとに、3月最後のお別れ会をどんな風にしようかと話を振ったら、彼女にはやっぱりプランがあったので、会えない間にその準備がゆっくりできるねという話をしました。その日の夜はフラワーデモがあって、私は家族で行く予定だったので、一緒に行く?と聞いたら行きたいと言うので、チゲ鍋を食べて一緒に行ったんです。そしたら帰りには元気になっていて。「今日、すごくいいものを見た」と、「お別れの日の準備をゆっくりします」と言って帰って行って、実際に思うような形でできたらしいんですよね。やっぱりそういうのは希望なんだと思います。自分の今いる場所で努力できることをちゃんと見つけて、ただそれにとどまるだけではなく、繋がれるようなことをやっている人たちの頑張りを見る。手元と遠くを見せたいと思いますが、まず私は手元にあるその子の頑張りをきちんとみてあげたい。彼女はフラワーデモに行ったのはすごく良かった、本当に切り替わったと言っていて。一年間をふりかえる時間をつくり、転出のあいさつをきちんとして、新しい学校でもやっぱり子どものそばにいるいい先生としてやっています」
――誰かと繋がることは力になる。家族のなか、家庭のなかだけでなく。
上間「家族がエネルギー源になる幸せな人もいますけど、そうならないこともあるし、家族の関係は変容するので、そこだけに求めないようにするというのはすごく大事だと思います。家族の中に分かってくれそうな人がいる子はそれはそれで使って、でも資源はいくつも必要です。あと、さっきの学校の先生をやっている教え子の場合、学校の中に味方を探せないかという話もしていて。あの日、彼女は本当に大きな権力に対して怒っていて、なぜ現場の話を聞かないのかという怒りがありました。そしてもう一つは学校行政がおこなっていることへの怒りですよね。教室に立って歩いてたりする子がいたら、彼女はその子の手を繋いで授業するような先生なんですが、突然、指導主事がやってきて指導されたりすることにも泣きながら怒っていた。でも、とても品のいい穏やかな子なので、憤りを表に出さないで耐えるのです。なにがあっても学級だけは守ると決めてるから、余計な波風を立てないという戦略なんですよ。それを24、5歳の子が言うんですよね。とんでもないなと思いながら聞いているんですけど、私はそういう彼女の頑張りひとつひとつを覚えておこうと思っています。そういう頑張り方や戦略みたいなものは、今、学校現場で働く、子どものそばに居ようと決心した良心的な教師たちは、みんなやってることだと思います」
◆沖縄の伝えられなさ、伝えられ方◆
――私は以前テレビディレクターをしていて、2000年の九州沖縄サミットの際に沖縄でドキュメンタリーの撮影をしたことがありました。普天間基地のすぐそばの小学校の校庭で、頭上を米軍機が飛ぶ騒音のなか遊んでいる子どもたちにカメラを向ける。耳を塞ぐ子どもの姿をカメラに収めることが、その状況の象徴的なカットであると思い込んでいました。ですが実際はそういう子は一人もいなかった。聞くと「いつものことだからそんなことしないよ」と。それが日常であることへの想像力が自分には圧倒的に足りませんでした。上間さんは、これまでの沖縄の伝えられ方や描かれた方について、一番間違っていたメッセージは何だったと思われますか。
上間「今は報道自体がなくなっているので、そこへの危機感がすごく強いです。サミットのときの撮影は、おそらく普天間第二小学校だと思うのですが、日常でいちいち怒ってたりびっくりしてたらもたない。生きるために慣れるんです。私も普天間基地近くに住んでいますが、近所の方はみな、基地について話せないんですよね。映像が沈黙にどう付き合うことができるのかということは、考え続けています。平良いずみさんという沖縄の監督が撮られた『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』は、とても静かで黙り込んでいる、こういってよければ映像映えしない、でもそうした沈黙に付き合うことで沖縄の不条理がはっきり撮られていてすごいと思いました。その映画が主題のひとつにしたような、ひとの暮らしに寄り添いながら語りづらさがそこにある映像が出てきたらいいのにとは思います。もう一つ、これはわかりやすさの批判でもあるんですけど、辺野古に若いNHKのディレクターさんが1年間住んで『辺野古抄』という番組を撮っているんですね。地元の人たちがだんだん諦めさせられていく過程や、苛立ってる感じの不穏さみたいなものがよく撮れてたんですけど、最後は海に土砂を入れるのを遠目で見て、諦めていくような音で終わっていました。確かにそこでそういう音で終わるのが、理不尽の象徴、悲哀というストーリーを作りやすいとは思います。でもそういう映像は、結局沖縄を消費しているだけだという苛立ちもあり、私なら、戦後沖縄の人を励まそうとつくられたヒヤミカチ節などエンディングに置くなぁと思いながらみていました。「七回転んで転びました。エイッと言ってたちあがりましょう」という歌詞の、しゃみせんの速弾きの美しい歌です。同じようなことがらなんですが、たとえば、朝日新聞で私が本の選書をして時代を振り返るという仕事をした時にも、朝日新聞が持ってきた写真は土砂投入の写真でした。それは沖縄の人が国家権力に踏みにじみられ、絶望しているという構図を強調する目的ですね。でも、それは消費でしかない。私が東京のほうに伝えたのは、選挙でデニーが知事となって喜び踊るひとびとの写真にしてくださいと要望しました。私たちはこんな絶望的な状況でも、デニーを知事に選んだ。あなたがたが黙り込み、絶望を決め込みたい間も動いていた。キワキワだけど負けてないというところは、ストーリーとして作りづらいけれども、消費しやすい形にはならないですよね。そこでメディアは踏ん張るべきかなと思ってます。それにもまして報道がないですけどね」
――「キワキワだけど負けていない」。なるほど。希望を持って立ち続けることで、勝手に消費する人に立ち向かう。
上間「そういうところでみんな踏ん張っている気はします。沖縄の人だけじゃなくて、調査の子だけじゃなくて、意外とみんなそうだと思います。本当はそこはね、もっとお互いに発掘しあって手を結べるところだと思うんですよね」
◆絶望を引き受ける、希望◆
――『海をあげる』のあとがきでは、最後に次のようなことばを書かれています。
「この本を読んでくださる方に、私は私の絶望を託しました。(p251)」
読者として、とても重い荷物を渡された気がしました。
上間「子どもを育てていて、娘だけじゃなく娘に繋がる子どもたちをみんなで育ててる感覚があるんですけど、子どもたちにあまりひどいものは渡せない、それは大人の側でなんとかしないと思っています。本土と沖縄だけではなくて、沖縄の内部に対しても私は苛立ちがあるんですよね。それは基地反対とさえ言っていれば、何かを言ったようになってしまっているとか、そういう思いもあります。とはいえ、言ってくれてる人たちには微細に何かを批判するのではなくてただ感謝でいいんじゃないかとかも揺れます。そして、自分に対しても本当はもっと辺野古に行きたいのに行けていないと苛立ちます。でもこういう葛藤自体が”させられている“ことだと思っています。沖縄北部や辺野古の海はきれいです。だから、子どもを連れていってもっと楽しみたい。それなのに、楽しんでいると申し訳ないような気持ちになったり、そういう引き裂かれながらしか生活できないというのを、娘や子どもたちにあげるわけにはいかないと、広く大人の側にたちに呼びかける風にしています。
あの本は、自分では果たし状みたいな感じで書いているんです。「アリエルの王国」が本のど真ん中だと思っていて、「アリエルの王国」をどうやって読んでもらうかという構成を編集の柴山さんと考えました。『海をあげる』というエッセイは、いいかげん、沖縄にこんなことをさせないでくれという気持ちで、最初から最後の章に置くつもりで書きました。だから私自身は、「だからあなたに、海をあげる」といいきったあと、そこで舞台の緞帳をおろすような気持ちで脱稿したんです。でも柴山さんから「あとがきを書いてほしい」という話があって、そりゃそうだよねと。読んでくれるのは、本当に良心的な人たちです。そのひとたち自身もキワにいる。そういう人たちにむけて、「海をあげる」と絶望を手渡すこともまた暴力的だと思いました。それでもう一度あとがきには、なぜ私がこの本を書いたのかという、私の思いを書きました。娘たちにこんな思いはさせられないし、それを大人たちはどう考えるかということを書いて、絶望をこちらで引き取ることができれば、次の世代はまた違う形で生きていくと思うと、そういうことを考えて書きました」
――絶望を引き受けることが、希望になる。
上間「わかるってことは大事ですよね。わからない時の方が傷つきは大きいと言うか、傷つきを抑えこむことができない感じがある。書くことで何に傷ついているのか、何が恐怖なのかとか分節化していって、その対象をわかっていくというのは大事だと思っています。だから書いているときには苦痛じゃないです。調査そのものは、やっぱり生の現場の生々しさに触れるのでしんどいことが多いですよね」
――今後のご予定は。
上間「若年出産女性調査は今年度で76名に聞いていて、データのクリーニングをこれから行います。まあ、かなりむつかしい層をターゲットにした調査としては、まずまずの形になっていると思うので、今年度でこの調査はとりあえずいったん締めます。それ以外に、行政関連の支援介入系の仕事もありますし、仲間とやっている楽しい企画などもあります。成人式に振袖をきせて送り出すという「大人がよってたかってハタチの子を可愛くする成人式」イベントや、子どもの記念日の写真撮影など、若い女の子たちにとっての楽しいことも引き続きやりたいと思っています。メディアは、大変ななか動いてそれを解決する救世主のような存在を求めますよね。私が調査を超えて支援をしていることもそういう風に見られがちなんですけど、頭を抱えていることの方が多いです。ここで起きているのは、だれかひとりが救世主になって解決できるような問題ではありません。だからこそ仲間をつくりながら、いろいろやらないといけない時期なんだと思います。とりあえず、あきらめずにやり続けたいですね」
interview Sonoko Osanai
text&edit Ryoko Kuwahara

上間陽子
『海をあげる』
(筑摩書房)
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480815583/

『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』
(太田出版)
http://www.ohtabooks.com/sp/hadashi/
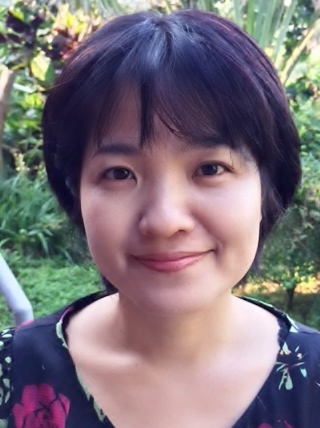
上間陽子(うえま・ようこ)
1972年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学研究科教授。普天間基地の近くに住む。1990年代から2014年にかけて東京で、以降は沖縄で未成年の少女たちの支援・調査に携わる。2016年夏、うるま市の元海兵隊員・軍属による殺人事件をきっかけに沖縄の性暴力について書くことを決め、翌年『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』(太田出版、2017)を刊行。ほかに「若者たちの離家と家族形成」『危機のなかの若者たち 教育とキャリアに関する5年間の追跡調査』(乾彰夫・本田由紀・中村高 康編、東京大学出版会、2017)、「貧困問題と女性」『女性の生きづらさ その痛みを語る』(信田さよ子編、日本評論社、2020)、「排除II――ひとりで生きる」『地元を生きる 沖縄的共同性の社会学』(岸政彦、打越正行、上原健太郎、上間陽子、ナカニシヤ出版、 2020)など。現在は沖縄で、若年出産をした女性の調査を続けている。
小山内園子(おさない・そのこ)
1969年、青森県生まれ。社会福祉士。NHK報道局ディレクターを経て、延世大学などで韓国語を学ぶ。訳書に、ク・ビョンモ『四隣人の食卓』(書肆侃侃房)、キム・ホンビ『女の答えはピッチにある』(白水社)、共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ』(タバブックス、すんみと共訳)、チョ・ナムジュ『彼女の名前は』(筑摩書房、すんみと共訳)などがある。2月中旬には男女の賃金格差に斬り込んだイ・ミンギョン『失われた賃金を求めて』(タバブックス、すんみと共訳)が、また3月には女性を取り巻く暴力構造に真正面から向き合った長編小説、カン・ファギル『別の人』(エトセトラブックス)が刊行予定。





























