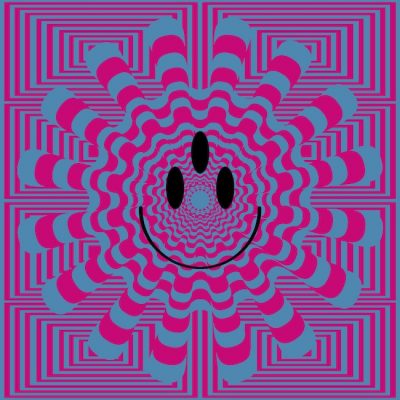シェイムやドリーム・ワイフらと共に、英国ロック・シーンの新世代を印象付けたデビュー・アルバム『Goat Girl』から3年。ゴート・ガールの次なるフェイズを示す2ndアルバム『On All Fours』が完成した。ポスト・パンク・マナーの粗削りなギター・ロックから一転、シンセを前面に取り入れてエレクトロニックに、サイケデリックに大きく色彩感覚を広げたサウンド。加えて、ジャムを繰り返して琢磨された4人の演奏は、クラウトロック的なダンス・フィール溢れるアンサンブルへと大胆な深化を遂げている。前作のリリース後にはベーシストのナイマが脱退。しかし、新たなメンバーを迎えたツアーをきっかけに、インスピレーションを呼び込む「新しい風」が吹いたと彼女たちは語る。いわく、バンド内ではいつにも増してオープンな話し合いが交わされたという今回の制作。昨年12月の中旬、3度目のロックダウンに入る直前のロンドンに電話を繋いでメンバー全員に話を聞いた。(→ in English)
――こうした困難な状況の中、まずはあなた方のニュー・アルバムが完成したこと、そして無事に届けられたことを嬉しく思います。完成にこぎつけるまでには色々あったと思いますが、今の率直な気持ちはいかがですか。
ロージー「レコードが完成して気持ちがいい。新作をレコーディングしたのは一年前なんだけど、未だに新鮮に感じる。それは多分、曲を全然プレイ出来てないからかな。だからまだワクワクしてる。今年は演奏が出来ないぶん、ビデオ撮影にフォーカスを置いたりして、よりアルバムの曲を世の中に広めるための準備ができたから、それが遂にリリースされるのが本当に楽しみ。努力が報われる時が来たって感じだね。すごく興奮してる」
――実際のところ、制作の過程やリリース・スケジュールに関してCOVID-19の影響はありましたか。
ロージー「レコーディングしたのは一年前だから、影響はなかったんだよね」
――では具体的に、今回のアルバムはどんなかたちで制作は進められたのでしょうか。
ロッティ「今回はちょっと変化があった。セカンド・アルバムは、リリースする随分前に作っておこうという心構えがあったから。マネージャーから、ツアーの時は忙しくなるし、余裕を持って制作をするようにアドバイスを受けていたから、早く作らなきゃってちょっとパニックになってたんだ(笑)。だから早めに作ることを意識していたんだけど、ベースのナイマが脱退してホリーが加入したのが、制作をスタートさせる良いきっかけになった。バンドにとって新しい風が吹いたというか。彼女は前回のツアーの途中で入ったから、演奏にもなれていたし、制作作業も自然で、心地が良かった。誰かと一緒に作業をする時は、自分自身をさらけだす。だから信用は欠かせない。そういう点で、彼女が早い段階でバンドに入ってくれて、作業に入る前にお互いを理解できていたのはすごく意味があったと思う」
――曲作りはどのようにして進めていったのでしょうか。皆で同じ部屋で? それとも個々に作業して、それをあとで合わせた?
ホリー「殆ど同じ部屋で一緒に書いた」
ロージー「でも、個々に書く時もあったけどね」
ホリー「みんなでジャムをしながら、もちろんその流れでお互いの人としての理解も深まっていったし、音楽的な理解も深まっていった。私は最初ナイマのポジションを埋めるためにバンドに入ったから、作業を始めたときは、私が入って曲を書くのがうまく行くのか行かないのかわからなかった。だからジャムをして、アイディアを出し合って、お互いを探っていったの。たくさん一緒に作業をして、いろいろな楽器を演奏して、様々なサウンドを試して、長い時間を過ごした。結果、それで皆ハッピーに作業が出来てよかった」
――制作過程で何か印象に残っている出来事はありますか。
ロッティ「ダンの犬がつぶされちゃった時(笑)。私がヴォーカル・テイクをレコーディングしてる時だったと思うんだけど、ダンの奥さんがダンに何か言うためにドアを開けたのね。で、ドアを開けた途端、私たちがレコーディングしてるのに気づいて、扉をサッと閉めようとしたの。そしたら、ダンと奥さんが飼っている小型犬がドアと壁の隙間に挟まっちゃって。レコーディングしてる時だったから、その時の犬の鳴き声を録音したものがまだ残ってて、それにダンがたくさんディレイを加えて曲に使ったの(笑)。あれは面白かった(笑)」
――今話にも出ましたが、今回のアルバムでは前作に続いてダン・キャリーがプロデュースを務めています。あなたたちが彼に置いている信頼の、最大のポイントはどこにあるのでしょうか。
ロージー「ダンは、どのアーティストと作業していても、そのアーティストのベストを引き出すことができるプロデューサーだと思う。彼はルーティンに従う人ではなく、彼との作業はそのアーティストとのコラボレーションみたいな感じ。だから、作業中も自分たちが何をやりたいのか、それを作り出すにはどの方法がベストかについて沢山話すんだ。まずは、こちら側のアイデアを彼に話す。そのアイデアを、知識豊富な彼が形にしてくれる。可能性を最大限に引き出してくれるのがダンなんだよね」
ロッティ「彼は、皆のアイデアに関してすごく包括的でもある。人の考えを否定せず、どんなこともまずやってみる人。それってプロデューサーの中でもクオリティが高いと思う。自分が上位だと思ってるプロデューサーも中にはいて、“そのアイデアはダメだ”って決めつける人もいるけど、ダンは、一緒に新しいことを発掘していけるプロデューサー。すごく良いことだと思う」
――あなたたちと関係が深いブラック・ミディやブラック・カントリー・ニュー・ロード、他にもフォンテインズD.C.といった最近のバンドが多く彼にプロデュースを依頼する理由もそのあたりにあるでしょうか。
ホリー「そうだと思う。あとは、彼が持つエナジーと知識。彼は作りたいサウンドを実現させてくれるし、彼のエンジニアのレックスも素晴らしい。ダンは、誠実で熱意がある。そして、作業していて自分も一緒に興奮できるアーティストやバンドとの仕事を引き受けてる。だから、何かエキサイティングなものを一緒に作り上げているという実感が持てる。それが彼との作業を一番楽しめるポイントの一つだと思う」
エリー「彼のポジティブさも魅力の一つ。そのポジティブさが作業空間に広がるから、レコーディングの雰囲気が自然と良いムードになる。そこにいる全員がいい気分になる。そういう人って誰もが一緒にいたいと思えるでしょ? 他のバンドが彼を選ぶ理由は、そこにもあるんじゃないかな」

――今回のアルバムでは、エレクトロニックな音色、アレンジが大胆に取り入れられていて、全体的にサイケデリックなムードが色濃く、曲によってはドラッギーといってもいいような感覚を受けます。音楽的なコンセプトやアイデアのもとになったものがあれば教えてください。
エリー「個人的には、どんなサウンドにしたいというアイディアは特になかった。皆で一緒の部屋に集まって曲作りをして、いいサウンドが生まれると、そのサウンドに対する互いのリアクションで、全員一致でそれがいいと感じることが出来たから、その流れで今回のサウンドが確立されていった感じ。少なくとも私は、セカンド・アルバムはこんなサウンドにしようっていう青写真はなかった。でも、もっとエレクトロ・サウンドを取り入れたいっていうのは全員思ってたことかな。ただ、ホリーがバンドに入るまで、それをどんなやり方で実現するかは見当もつかなかった。彼女が入ったことで、スイッチが入った(笑)」
ホリー「確かに、これといったコンセプトやアイディアはなかったと思う。皆それぞれに異なるタイプの音楽を聴いていて、それを混ぜていった感じかな」
――じゃあ、意図した変化というより、自然とこういう方向に進んでいった感じですか。
ロージー「自然な変化だったと思う。最初のアルバムでは、どちらかというとレイヤーとしてエレクトロ・サウンドを取り入れたかった。当時も沢山昔のエレクトロニック・ミュージックは聴いてはいたし、そういうサウンドをプレイすることに興味はあったんだけど、まだその腕前を持ち合わせてなかった。でも、EP『Udder Sounds』(2019年)で少しそれを実験することが出来た。だから、その流れで今回のアルバムにエレクトロニック・サウンドが取り入れられたのは自然な進化だったんじゃないかな。新作の曲は、作曲する時点で必ずシンセのパートが作られていたし、それが自然な書き方だった。どうにかシンセで曲を書こうとか、シンセを使おうとしたわけじゃないんだよ。ギターやドラムと同じくらい、シンセが欠かせないものになっていた。今回、シンセは他の楽器と同様に重要な役割を果たしてる」
――たとえば前作を作っていた頃とは、インスパイアされる音楽、あるいは普段よく聴く音楽も変わったのではないでしょうか。同じ音楽を聴くにしても、聴いているポイントが変わったりとか?
ロッティ「私はエレクトロニック・ミュージックを沢山聴いてる。自分のソロ・プロジェクトでもそういう音楽を作っていたから、エレクトロは大きくインスパイアされた音楽の一つだと思う。曲の書き方もエレクトロっぽくなっていったし。ファースト・アルバムの時は、ギターを弾きながら歌って歌詞も一緒に出てくる、みたいな感じだったけど、それはファースト以降殆どなくなった」
エリー「私が知る限りでは、私たち全員がポップ・ミュージックのファン。それがこのアルバムにも反映されていると私は思う。メロディとか、コードの並びとか。今回は、ゆとりのあるサウンドを作ることに対する恐れがなかった。例えば、ファースト・アルバムはサウンドが充実している分詰まりすぎていて耳障りな部分もあった。当時はそういったサウンドにインスパイアされていたから。でも、今回はポップミュージックを素直に楽しむ子供みたいな感じで、自分たちの頭から離れないような中毒性のあるサウンドを作りたいって思うようになった」
――エレクトロニックな部分以外に、サウンドに関して新たにアプローチしたことはどんなことがありますか。
ホリー「部屋の真ん中にパーカッションが沢山入った箱があったんだけど、それを自由に手にとって、何も考えずに曲に合わせてプレイするっていうのを試した。それを5、6人が同時にやるっていう。そこからループを作って曲に使った。あれは、面白くて新しい質感をサウンドにもたらしてくれたんじゃないかな。あとは、モジュラーシンセ。私は使い方を知らなかったんだけど、あれを使ったから、ロボットみたいな奇妙で面白いサウンドを取り込むことが出来たと思う。使ったシンセはKORGのミニローグ。でも、ダンがムーグ・ワンっていう高いシンセを持っていて、それも使わせてもらった」
ロッティ「ファースト・アルバムでは、ロージーのピアノを使って即興をやったりもしてたし、メロトロンも沢山使ってた。他の楽器のライブ演奏をサンプリングして使ったりするんだけど、当時はあれにハマったのよね。今回のアルバムでは、それを沢山使ってる。主にブラスやストリングスのテクスチャーのため。生演奏ももちろんあるけどね。トランペットとか、ビオラとか」
―あと、これは想像ですが、リズムも最初は打ち込みで作って、それを生のドラムで叩き直す、みたいなプロセスもあったりしたのでは?
ロージー「曲がある程度決まってくると、曲に合わせてダンがMPCでドラムループを作ってくれた。それがもしロボットっぽく聞こえたりすると、それをもっとスローにしてみようか、とかそういうことを話し合って、ダンがその方法や使い方を教えてくれたから、それを長い時間をかけて勉強して、自分で編集出来るようになったんだ。で、ライブレコーディングの時に、それを聴きながらドラムを叩いた。そのドラムループの一部は、多分そのまま曲に使ったんじゃないかな。でも、メトロノームのようなリズムは取り入れたくなかったから、そうならないようにベストな方法でそれを取り入れた」
――そうしたアプローチの変化、新たな試みを踏まえた上で、自分たちのアイデア、狙いが一番よくハマった曲をあげるとするならどの曲になりますか。
ロッティ「自分たちが一番誇りに思えるとか、達成感や満足感を一番感じることが出来るのは、多分“Where Do We Go”。でも一つには絞れないな。私は個人的に“Jazz”も好き。あのサウンドは、作ることを夢見てたけど実現ができなかったサウンドだと思うから。そして、あの曲は全てを皆で同じ部屋で一緒に書いた作品でもある。アルバムの中でも、そういう意味でユニークな作品」
ロージー「全曲、自分が作りたいと思うサウンドを実現できた作品だと思う。全ての曲のアプローチが異なるし、作り方も違うから」
ホリー「そうだね。全ての曲それぞれが強い印象を持ってる。どの曲も長いし、互いに劣っている部分、優れている部分が見つからないから。どの曲も素晴らしいと思うな(笑)」
――一方、リリックに関しては、どんなことがテーマなりバックグラウンドのストーリーになっているのでしょうか。そこには、前作からのこの2年間におけるあなたたち自身の変化、あるいは取り巻く世界の変化がどんなかたちで歌詞に反映されていると言えますか。
ロッティ「テーマは本当に様々。今回のアルバムには、本当に様々なことが反映しているの。自分たちが心で思っていることだったり、メンタルヘルスだったり、自己理解だったり、自分を囲む環境だったり、自然だったり、社会だったり。私たちが関心のあること全て」
エリー「ロッティが今話したように、ファースト・アルバムでは取り上げられなかった新しいテーマもいくつかある。でも、ファーストから続いて言及しているのは、人間の運命論。何事にも終わりはくるということよ。私たちのファースト・シングル(“Country Sleaze”“Scum”)でもそれは歌われている。そのテーマは、セカンド・アルバムに受け継がれていると思う。
――なるほど。
ロッティ「エリーが言ったように、ファーストを思わせる感情も今回のアルバムには含まれている。最初のアルバムでは、怒りや世界のめまぐるしい変化の中で自分自身を構築していくということが歌われていた。あの時はそれを吐き出したくて、曲は直感で書かれ、出来上がるスピードも早かった。世の中や周りの環境に対する自分の率直な反応をそのまま曲にした感じ。でも今回のアルバムでは、曲を書いただいぶあとで歌詞を書いた。座って音楽を聴いて、どちらかというと詩を書くように使いたい言葉を選び、言葉のリズムを考えて歌詞を書いていった。だから時間もより長くかかったけど、結果すごく満足しているの。その変化は楽しめると思う」
ーー“The Crack”の「The crack was singing protest songs/The people wouldn’t listen, they didn’t care(亀裂は抗議の歌を歌っていた/人々は耳を傾けなかった/彼らは気にしなかった)」から「Cracks forming, the earth’s back(地球が裂ける時、亀裂は形成され、それは元に戻らない)」と続くラインは、気候危機の問題、さらにはもっと根深い分断や対立について歌われていると感じました。この曲が書かれた背景を教えてください。
エリー「気候変動や地球上で起きている津波やハリケーンといった全ての自然災害について書いた作品。ただもちろん自然だけでなく、人間の行いも含まれている。人類も自然、地球の一部だから。オゾン層も明らかに破壊されつつあるし、この季節に咲かないはずの花が咲いていたり、起こるべきでないことが起こったりしているでしょ?人々は、それをただ無視する。正直、どうしていいかわからないから私自身も無視してる。何をすればいいのかわからないけど、それをどう変えていったらいいんだろうっていう思いを曲にした。私がヴァースの歌詞を書いて、ロッティがサビの歌詞を書いた」
――その“The Crack”もそうですが、“Sad Cowboy”のMVも広大な自然がロケーションとして使われているのが印象的です。
ロッティ「あのロケーションを選んだのは、条件がよかったから(笑)。私たちのアルバムをすごく気に入ってくれたファミリーがいて、彼らが私有地を持っていたから使わせてくれた。その場所には色々なものがあってすごく面白かった。牧場とか、干し草とか、面白い形をした左右対称の木とか。だから、幅広い作品を撮ることが出来た。それに、自分たちのやりたいことが出来たのが良かった。あのビデオの一番のアイディアは馬をフィーチャーすることだったんだけど、あの場所だからこそそれを撮影することが出来たんだ。安全面で、公共の場で馬を放すことはなかなか出来ないから」
――ちなみに、今回の制作中、メンバー間のやり取りや会話の中ではどんなことがトピックになっていましたか。直接アルバムに反映されていないとしても、4人の間に生まれたどんなムードやテンションが今作の背景にあったのか、知りたいです。
ロージー「キモい話しをいっぱいしてた(笑)。説明できないけど、マジで気持ち悪い話(笑)。人間の身体に起こる自然なことについてなんだけど、4人で超オープンになってそれを話してた。身体機能とか色々(笑)。でもちゃんと、知的なことも話してたよ。制作は一年前だったから、結構政治についても沢山話してた。
ロッティ「覚えてるのは、私たちの友人でフォトグラファーのホリー・ウィタカーが来て、『Why I’m No Longer Talking to White People About Race』って本を持ってたんだけど、その本について沢山話したんだ。白人優遇とか、それにまつわる自分たちの経験とか」
ホリー「あとは、お互いの気持ちや様子を話してた。皆自分をさらけだして、素直に気持ちを話して互いを気遣って助け合ってた」
――「On All Fours」というタイトルは、4人の結束感、絆みたいなものも表しているのかな、と思いました。前作からこの2、3年間で、4人の関係性において変化したこと、深まった部分、もしくは新たな気付きなどあれば教えてください。
ロッティ「個々に色々あったし、お互い頼り合いながらそれを乗り越え成長してきた。それは確実に私たちの絆を強くしたと思う」

――では最後に、2020年のベスト・アルバム、ベスト・トラック、もしくは小説でも映画でもドラマでも、この一年間であなた方の心を捉えたものも教えてください。あるいは、あらためてよく聴いたり観たり読んだりしたものでも構いません。
ロージー「チャーリーXCXの『How I’m Feeling Now』。あのアルバムのおかげで、自分の勢いを保つことが出来たから。あのアルバムを彼女はロックダウン中に作って、それは作品からも伝わってくる。何回あの作品を聴いたか覚えてないくらい沢山聴いたんだ。自分とルームメイトで聴きまくって、中毒になってた。自分にとっては、あのアルバムが今年のベスト・アルバムだな」
エリー「私は、エゴ・エラ・メイの『Honey For Wounds』。すっごく美しいアルバムで、サウンドは正にタイトルそのもの。栄養を与えてもらっているような、そんなサウンド。彼女は数日前にMOBOジャズ・アワードで賞を受賞したばかりで、本当に控えめで素晴らしいアーティスト」
ホリー「イヴ・トゥモアの『Heaven to a Tortured Mind』。〈WARP〉レコードのアーティストなんだけど、サウンドがすごく面白い。彼は大好き。聴かずにはいられらないサウンドだよね」
ロッティ「私は映画でいこうかな(笑)。『Bacurau』。最初に公開されたのは2019年なんだけど、イギリスで公開されたのは2020年だからいいよね? ブラジルにある人里離れた村の話で、とにかく素晴らしい作品。コミュニティや、人々の団結力のすごさについて描かれた作品なの。遠く離れた場所にあるから、人々に忘れ去られてしまい、もうグーグル・マップにも載っていない。観光客やブラジルの首都の人たちが来て、その村を破壊しようとしたりもする。そんな中で、村の皆が一つになって頑張るの。フィクションだけど、そういう状況って色々なところで実際に存在するんだよね」
ロージー「あと、『I May Destroy You』っていうテレビドラマもすごくいいよ。ミカエラ・コールが本当に素晴らしい。見るのが辛いシーンもあるけど、素晴らしい番組だし、重要な作品だと思う」
ロッティ「確かに」
――ありがとうございました!
全員「ありがとう!」
ロージー「早くまた日本に行けますように」
ロッティ「またね」
photography Holly Whitaker
text Junnosuke Amai https://twitter.com/junnosukeamai
edit Ryoko Kuwahara https://www.instagram.com/rk_interact/

Goat Girl
『On All Fours』
1月29日発売
(Beat Records / Rough Trade)
https://goatgirl.ffm.to/onallfours
01. Pest 02. Badibaba 03. Jazz (In The Supermarket) 04. Once Again 05. P.T.S.Tea 06. Sad Cowboy 07. The Crack 08. Closing In 09. Anxiety Feels 10. They Bite On You 11. Bang 12. Where Do We Go? 13. A-Men +日本盤ボーナス・トラック
国内盤CD
国内盤特典: ボーナス・トラック追加収録/ 解説書・歌詞対訳封入
BEATINK.COM:
http://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11453&admin=on
Tower Records:
国内盤CD
https://tower.jp/item/5108208
Amazon:
国内盤CD
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KDSYHFC
https://www.facebook.com/goatgirlofficial
https://www.instagram.com/goatgirlofficial/
http://goatgirl.co.uk/