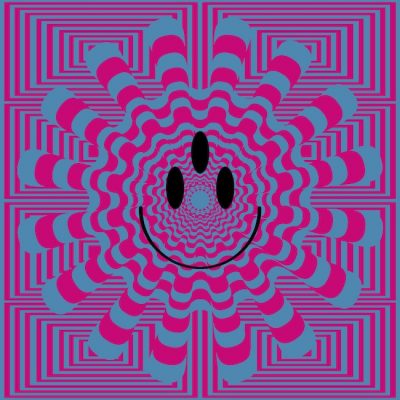今回は、このカメラマンにしようと決めた。アイコンのプロフィール写真も真面目そうだし、経歴も確からしく、いくつかの賞も取っていて、生々しくない写真のテイストも自分向きだと思った。
わたしは、カメラマン探しに、ツイッターを使う。他のSNSよりも、モデルとカメラマンのマッチングが盛んで、その点からも扱いやすい。
カメラマンの名前は山田浩二。すぐに忘れてしまいそうな平凡なものだけど、山田という知人はいなかったので、もしかしたら忘れないかもしれない、そんなことを考えた。年齢は、自称54歳。これまでの中で最年長のおじさんだが、たまにはそういうのもありかなと思った。
撮影当日、山田さんは、東京駅からすぐ近くのスタバでわたしをちゃんと待っていてくれた。アイコンと同じ顔だったのですぐに分かり、わたしから声をかけた。
山田さんは、会うなり、庭の百合が見頃でしてね、と今朝撮ったというiphoneの写真を見せてくれた。ちょっと変わった人なのかなと、軽く身構えたが、綺麗なものが単に好きなのだと、その後の雰囲気でわかり安心した。
初めて会う人の前で裸になるのだから、第一印象は大切だ。その人の声の質、言葉の選び方、目つき、服装などなど。それらを一遍にスキャニングして、ありかなしかを瞬時に判断する。わたしは、このことにかけては、鼻がきく方だと思う。下手したら、取り返しのつかないことになるのだから、自分の身を守るためには最初の5分は集中して接しているつもりだ。
山田さんの髪は半分ぐらいが白髪で、サイドと後頭部が刈り上げてあり、日に焼けた肌のせいもあって大工の棟梁みたいだった。身長は170前後。銀縁の丸メガネが似合っていて、中肉でお腹は出ていないようだった。水色の半袖のボタンダウンのシャツから見える二の腕が結構たくましい。
山田さんが運んできてくれたアイスラテを一口飲むと、少し落ち着いた。
「想像していたより小ぶりですね」
山田さんが微笑みながらそう言った。
「ええ、自分で言うのもなんですが、顔が小さくてバランスがいいので、写真だと背が高そうに見えるみたいです。」
わたしは、生まれて初めて「小ぶり」という言葉で自分が表されたことにちょっと驚いたが、それは表情に出さずにおいた。身体の特徴について何か言われるのは好きではない。それを山田さんは察したのか、それ以上わたしの「小ぶり」については話さなかった。
身長は159センチ。年齢は31。それはプロフィールに記してあるのだが、実際会うと、カメラマンたちはそれを改めて確認しようとする。いったい何故だかわからないが、話のとっかかりとして無難だと考えているのなら、それは間違いだと伝えたい。自分の平凡さを見せびらかすだけだ。
ビジネスホテルの小さい部屋は、割とセンス良くまとまっていて、濃いネイビーのカーペットと壁は、きっとわたしの白い肌を引き立ててくれるだろうと確信した。
山田さんは、ポートレイトの延長でヌードを撮っている人で、セクシーなポーズや表情は控えてほしいと、撮影前に穏やかな表情と口調で、わたしにリクエストした。
わたしは、基本的にカメラマンの要求には応じている。会う前のやりとりで、撮影内容や方向性については、何度も繰り返し確認し、現場でそれと違うことを要求したら、その時点で撮影は中止になると約束してもらっているので、これまで不快な思いはしたことがない。
とはいえ、裸を目の前にして変な気を起こす人もいるだろうから、人選もとても慎重にしている。HPを持っているかどうかは大切で、住所と電話番号ももらっておく。密室では何が起こるかわからないから。わたしがこんなことをしていると知ったら、きっと親は怒り嘆くのだろう。
それでも、わたしが裸の写真を撮ってもらいたがる理由は、自分でもよくわからない。承認要求とは違うのは確かで、どちらかというと、万引きに近い。要は、遊びなんだと思う。アートとかでもないし、ちょっとしたスリルを味わいたいのだと思う。
ヌードモデルのみんなが、スリルを求めているとは言わないが、もっともらしい理由は、わたしに言わせれば、能書きに過ぎない。言葉は時として、嘘を導く。本人さえ気づけない嘘を築く。わたしは、嘘を脱ぎたいのかもしれない。
山田さんは、わたしに熱いシャワーを浴びさせてから、ネイビーの壁の前に立たせた。わたしの白い肌がほのかなピンクに色づき、濡れた髪が肩に触れる感触が心地よかった。
山田さんは、いまだにフィルムカメラを使う。ローライフレックスというドイツ製の二眼カメラだ。それをカーボン製の三脚に置き、小さな金属的なシャッター音を鳴らしながら、一枚一枚とても丁寧に撮るのだった。使うフィルムはブローニーサイズで、一本で12枚しか撮れない。山田さんは最初の一本を撮り終えると、慣れた手つきで二本目を装填してから、ちょっと休みましょうと言って、休憩時間となった。
わたしは、朝に百合に惹かれた山田さんの眼が、今はわたしの裸に注がれていることを思った。
「高橋さん、ちょっと聞いていいですか?」
山田さんが、左手に持った露出計から視線を上げずに、わたしにそう言った。
「はい。なんですか?」
なんだか小津安二郎の映画に出てくる女優にでもなったような話し方をしてしまったと思った。山田さんは、うつむいて5秒ほどの間をとった。やはり小津映画のようだと思った。
「高橋さんのお母さん、もしかして名前、百合子ですか?」
わたしは、びっくりした。母の名は、まさに百合子だったからだ。
「はい。その通りですが」
わたしは冷静を装った。
「こんなことってあるんですね。お母さんの旧姓は、高幡さんでしょうか?」
わたしは、ちょっと身構えた。この人はいったい何者だろうか?探偵、警察?山田さんの灼けた肌が、刑事が外回りしている姿を連想させた。
「すみません、驚かせてしまって。でも安心してください。私は怪しい者ではありませんから。ただ、私も驚きました。まさか、こんなことってあるのですね。いやあ、まさか、まさか、です。」
わたしは無言で頷いた。山田さんは、その先を話していいものか、考えあぐねているようにも見えた。
「すみません、撮影を続けましょう。いいですか?」
「はい。大丈夫です。」
すでに肌はもとの白に戻り、わずかについていた水滴も乾いてしまっていた。
「シャワー浴びてきた方がいいですか?」
山田さんは、少し考えてから、今のままでいいですと指示をくれた。
二本目のフィルムも、山田さんは丁寧に撮り進めた。デジタルカメラで、カメラマンが集中して時を忘れたように撮り続ける熱量も好きだが、山田さんのように一枚ごとに心をこめてシャッターを押されるのは、もっと好きかもしれない。それはそのまま丁寧に扱われている気にさせてくれた。
二本目が終わり、山田さんがフィルムを交換している間に、わたしはベッドに仰向けになった。それがいかに無防備な姿であることはもちろん分かっていた。
「山田さん」
「はい、なんですか?」
「わたし、大丈夫ですか?」
わざと曖昧な言葉を置いてみた。
「はい。とてもいい写真が撮れていると思います」
山田さんは、無防備なわたしを見ずにそう答えた。わたしは、すこし迷ったが言ってみることにした。
「母とどちらがいいですか?」
自分でも馬鹿な質問だと思ったが、ちょっとした遊びのつもりだった。山田さんは、残りのフィルムを数えている様子であったが、それは手持ち無沙汰を誤魔化しているように見えた。
「君は知っているの?」
山田さんは、無防備なわたしを見ずにそう言った。ファインダー越しでなければ、モデルの裸を直視できないのか、もしくは彼の流儀なのか、とにかくわたしを見ないのだった。
「はい、だいたいは」
わたしは、何も知らないくせに、あてずっぽうに会話を繋いだ。
「百合子さんと君は瓜二つです。少なくとも僕にはそう見える。」
「裸も?」
わたしは調子に乗ってそう聞いた。山田さんは、やれやれといった表情で、ハンカチで額を拭った。
「恋人だったの?」
わたしは仰向けのまま、そう聞いた。
「それどころか」
山田さんは、言葉を濁したが、表情には晴れ間が差し込もうとしていた。わたしは、いったい何を知ることになるのだろう。山田さんはわたしの遊びに乗ってくれているだけなのか、本当のことを言おうとしているのか、察しかねた。
「君は、僕の娘かもしれないんだよ。」
わたしは、思わず笑ってしまった。冗談なのか、本当なのか、そんなことはひとまず置いておいて、なんだか可笑しくなってしまったのだ。
「山田さん、横においでよ」
わたしはベッドを軽く叩きながら、壁側に身を少し移した。
「いやあ、参ったな。なんだか、妙だな」
そんなことを山田さんはもごもご言いながら、わたしの横に仰向けになり、天井を見つめた。わたしはそんな山田さんの横顔を見つめた。彼はなおもわたしを見ないままだ。彼は抱く人の裸しか直視しないのだろう。
わたしは、山田さんの銀縁の丸メガネを外してみたいという欲求を持った。案外好きな顔だと思った。そして耳の形がわたしと似ていることに気づいた。
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある。