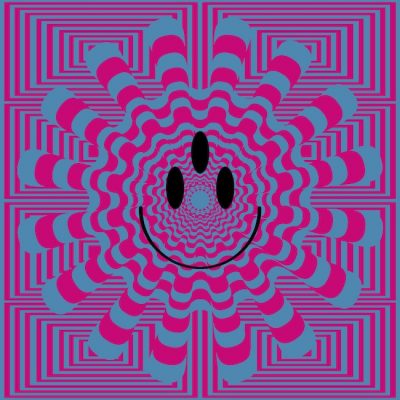2019年5月14日に可決成立した米アラバマ州の中絶禁止法。その後16州が同法案の制定に向けて動き、1973年の連邦最高裁が下した「ロー対ウェイド」の判決が覆される恐れが出てきた。女性による中絶の権利が保障されない可能性がある未来。次の世代が、私たちの世代より少ない選択肢の中で生きざるをえない可能性。それは日本に暮らす我々にとって決して遠くの出来事ではなく、そうした未来が我々にも存在するかもしれないという警鐘である。
『Our Body Issue』ではこの警鐘に対し、様々な側面からまずは自分の身体について知り、ひいてはその身体を愛すること、選択肢を持つことの大切さを考えるきっかけを作りたい。
ここでは自分の意思や考えを、歌/ヴォーカルという身体のアートに乗せて届けた女性ミュージシャンを追ったフィルム5選を紹介。(→ in English)
『ザ・スリッツ:ヒア・トゥ・ビー・ハード』
UKパンクのパイオニアSex PistolsやThe Buzzcocks、The Clashの存在は知られていても、同時期のパンクシーンを様々な話題で賑わせていたThe Slitsの名を知る人は少ないのではないだろうか。このバンドが関心を集めていたのは、オーディエンスを熱狂させる攻撃的なライヴ・パフォーマンスやレゲエの影響を受けたダブの手法をいち早く取り入れた稀有なサウンド、ダブ・レゲエの詩人らからインスパイアを受けた繊細で巧みなリリックのほか、“世界初の女性パンクバンド”という特徴だった。本作『ザ・スリッツ:ヒア・トゥ・ビー・ハード』は、バンドメンバーのインタビューとスーパー8におさめられた実際の映像で彼女たちの活躍を振り返るドキュメンタリーで、2010年に48歳で死去したヴォーカル・アリの遺言によって製作された一作。
1979年、ダブ・ミュージックの巨匠デニス・ボーヴェルをプロデューサーに迎えた彼女たちのデビュー・アルバム『Cut』のリリースは、イギリスの音楽シーンに衝撃を与えた。パンクとダブを融合させた特異なスタイルはその後のポストパンク、ニューウェイヴにおいてオーソドックスな手法となり、パンクという概念を定義する上で本質的に語られる“DIY”精神を体現したとして高く評価されるばかりではなく、メンバーたちが褌一丁の姿で泥まみれになっているジャケット写真はそれまでの男性優位的風潮が台頭していたパンクシーンでは一線を画す斬新なイメージで、世の女性パンクロック・ムーヴメントの指針を示した一枚となる。
一方で、その前衛的な出で立ちは当時のパンクシーンにおいて常に物議を醸していた。「女にパンクが表現できるわけがない」「演奏するふりをしているだけ」――しかし彼女たちは、劇中でも印象的に使用される楽曲『Typical girls』で悪評に中指を立てる。
“Typical girls get upset to quickly’(女はすぐに怒るって言われてる)
Typical girls can’t control themselves(女は自制心がないって言われてる)
Who invented the typical girl?(誰がそんな女性像をでっち上げたの?)
Who’s bringing out the new improved model?And there’s another marketing ploy
(誰がそんな価値観を持ち込んだの?で、またマーケティングで別の女性像が登場するんでしょ)”
ヴォーカル・アナの死去直前にリリースしたThe Slitsとして28年ぶりのアルバム『Trapped Animal』の中で彼女が放つ「私は浮浪者の中の浮浪者。私たちは生き続ける」のメッセージどおり、世界初の女性パンクバンドによる既成概念と戦ったその姿は、彼女たちの楽曲と本作に遺り普遍性を帯びて輝く。

『ザ・スリッツ:ヒア・トゥ・ビー・ハード』
監督・脚本・撮影・編集:ウィリアム・E・バッジリー
出演:ドン・レッツ、ヴィヴ・アルバータイン、ポール・クック、アリ・アップ、
デニス・ボーヴェル、テッサ・ポリット、ケイト・コラス、バッジーほか
2017年|イギリス|86分|カラー|G|原題 HERE TO BE HEARD: THE STORY OF THE SLITS
提供:キングレコード 配給/宣伝:ビーズインターナショナル (c) Here To Be Heard Limited 2017
amazon
『ニーナ・シモン~魂の歌~』
“ローリング・ストーン誌の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー”で第29位に選ばれるニーナ・シモン。ゴスペル、ジャズ、ブルース、R&B、フォークと多様な音楽ジャンルでその卓越した才能を発揮させ世界中で称賛を受けたのちも、60年代には黒人の尊厳を歌う楽曲を積極的にリリースし公民権運動の象徴と語り継がれる存在となった伝説のシンガーソングライターの一生を追う本作。
本作で明かされるのは、現在も世界中で語り継がれる偉大な歌手であるニーナにとっての音楽は、自身の全てであるとともに悪魔のような存在であったという驚くべき事実だ。
幼少期に母親に連れられ通っていた教会でピアノを弾いていたニーナ。その演奏を見初めた白人教師の熱烈な推薦により、その頃の黒人としては非常に珍しかったクラシック音楽のレッスンを開始したことで本格的に音楽の扉を開いた彼女は、将来的に生活の足しになると考えた両親の意志もあり毎日8時間の厳しい訓練をこなす生活の中で、白人たちからはおろか同胞の黒人コミュニティからも疎外され孤独感を募らせる(ここは『グリーンブック』の主人公である黒人ジャズピアニスト、ドン・シャーリーの葛藤にも重なる点だろう)。NYに渡り、ジュリアード音楽院で学びながらカーティス音楽大を受験するが、技術面は問題がなかったにもかかわらず黒人の入学者は前例がないという理由から入学を拒否される。その後困窮した一家の生活を支えるためにギャラの良かったクラブ・シンガーの職に就くことを余儀なくされたことで、図らずも歌手としてのキャリアをスタートさせるが、その類まれな深みのある歌声とクラシックで培った演奏技術が評判となり一気にスターダムへとのし上がる。愛する夫と子供にも恵まれた彼女の人生は順風満帆かのように見えたが、専属マネージャーでもあった夫による異常な過密スケジュールと、彼の日常的なDVによって強制される音楽活動により彼女の精神状態に異変が起こり始める。“これまで全てを捧げてきた音楽とは、自分にとって一体何なのか?”自身のアイデンティティが揺らぐ中、時代は公民権運動へ突入していく。ムーヴメントの中心人物であったキング牧師やマルコムX、ブラック・パンサー党のクワメ・トゥーレらとの出会いにより、初めて自らが音楽の道を歩む意味を見出したと言う彼女は運動にのめり込んでいき、暴力的な夫の支配からも決別を遂げる――。
本作『ニーナ・シモン~魂の歌~』は、単純な音楽伝記映画の枠にとどまらない作品だ。これまでも数々の社会派ドキュメンタリー作品で高い評価を受けてきた女性監督リズ・ガルバスが、30年代南部の貧しい家庭に生まれNYに渡ったのち名声と愛する家族を手に入れ社会活動に傾倒していったニーナの数奇な人生に焦点を当てることで、アメリカ社会に生きた一人の黒人女性によるアイデンティティの模索を暴き出す一作となっている。

『ニーナ・シモン~魂の歌~』
amazon
Neflixにて配信中
『ミス・シャロン・ジョーンズ!』
60s~70sのグルーヴィなソウル・ミュージックを現代に蘇らせ2014年にリリースしたアルバム『Give The People What They Want』ではグラミー候補となった“シャロン・ジョーンズ&ザ・ダップ-キングス”、そのリードヴォーカルをつとめるシャロン・ジョーンズは、女性版ジェイムズ・ブラウンとも称される60歳のベテランシンガー。オリジナルアルバムの初リリースは40歳を過ぎてからで、そのキャリアのほとんどをウエディング・シンガーとして過ごすかたわら様々な職業を転々とし生計を立ててきた彼女は、爆発的なヒット曲を抱えたスターではなく、まさに労働者階級のミュージシャンだった。NYを拠点とした地道な活動が実を結びようやく日の目を浴び始めた矢先、彼女のもとにステージ1の胆管がん宣告の知らせが届く。がん治療の為にトレードマークであるドレッドヘアをそり落とし苦しい化学療法を受け、友人や旧知のミュージシャン、長年の付き合いのマネージャーらによる支えのもと闘病生活を送りながら再びステージに立つ日を夢見るシャロン。自身の写真が一面を飾ったヴィレッジ・ヴォイス紙をカメラに見せながら語る、「ずっと良い音楽をやって認められることを信じてきた。歌い続けていれば、人は私の声を愛してくれるはずってね。レコード会社の人に“太りすぎ、黒すぎ、背が低すぎ、年を取りすぎ”って何度も言われたわ。この写真の私を見てよ、化学療法で少し痩せたし、癌はあるけれど私はまだ黒人だし、身長は150センチのまま」の言葉から、彼女の逆境は癌の発覚で始まったのではないということに気づかされる。抗がん剤によって身体の全ての毛が抜け落ちてしまっても“また髪を振り回しながら歌いたいわ!早く生えてこないかな?”と笑い飛ばしエネルギッシュに生き抜く“ソウル・ミュージック”を体現したような生きざまは、一筋縄ではいかなかった人生そのものを糧に築き上げられたものなのだ。
そして、闘病生活を無事終えた末に観客の前で愛するバンドと共に復活のステージをふむラストのライヴシーン。歌う歓びを爆発させる彼女の姿とそれに応え熱狂するオーディエンスが築く一体感は、音楽を愛する全ての人の胸を打つだろう。
本作製作後に再び癌を再発させ2016年に惜しまれながら息を引き取った彼女は、“こんな病気もすべてトランプのせいよ!”と冗談を飛ばし、病床に集まったバンドメンバーが奏でる音楽に合わせハミングするなど、最期まで彼女らしく在り続けた。

『ミス・シャロン・ジョーンズ!』
amazon
Netflixにて配信中
『ソニータ』
ソニータはアフガニスタンの難民としてイランに単身越してきた少女。夢はラッパーとして多くのオーディエンスの前でパフォーマンスをすることだが、女性が歌うことすら許されないイランでは児童保護施設の子供たちの前で密かに披露するのが精いっぱいである。
パスポートも滞在許可証も無く故郷を追われてきた不法移民の彼女にとってラップだけが唯一の居場所だったが、一方でアフガニスタンで暮らす両親は全く別の将来を準備していた。それは、古くから伝わる伝統どおり見ず知らずの男性に嫁がせようというもの。9000ドルで自分の身が受け渡されると知った彼女のなかに、両親は自分を売り物として育てていたのではないかという思いが沸き立つ。私の人生は誰のものなのか?どうしたら人々の前でラップが出来るようになるのか?思い悩んだ末に、彼女はある決断へと踏み切る。
この『ソニータ』で特筆すべき点は、従来のドキュメンタリー映画およびジャーナリズムに関わる作品であればご法度の“製作者による問題点への関与”に踏み込んだ点だ。製作者は取材対象者を取り巻く環境に極力コミットせず距離感と中立性を保つというドキュメンタリーの原則が、本作でメガホンをとった女性監督ロクサレ・ガエム・マガミがアフガニスタンにあるソニータの実家を訪れるシーンを皮切りに壊されていく。問題のシーンでは、彼女の母親に話をきくうちインタビュアーであるマガミの語気がだんだんと荒くなっていくのが分かる。“結婚を強要するのですか?”“自分の娘を売るなんて”怒りの感情をあらわにし、ついには母親の“ソニータがイランでいくらか金を工面出来たら結婚を延期してもいい”という言葉に対し、自身で出資しようとして撮影クルーから“それはさすがに倫理違反だ”と止められる展開にまで行きつく。
児童保護施設で働くいとこの紹介で16歳のソニータを知ったとき、たったひとつのスマートフォンで作ったとは思えないほどのクオリティによるラップとMVを見てそのクリエイティビティに大きな衝撃を覚えたというマガミがソニータを追ううち彼女を取り巻く社会問題への反発心を強固にさせていったのは単純に同情心が作用したからではなく、女性の同胞としてそして一人のリスペクトするアーティストとしての連帯意識が生まれたからであろう。
こうして暗黙の了解を踏み越えながらも称賛を呼んだ本作は世界中の映画祭で賞を獲得し大きな注目を集めた。ドキュメンタリー作品の新たな可能性を開拓したマガミと、兄の結納金のために母親から花嫁として身売りさせられそうになる痛ましい実体験をリリックに綴った「売られる花嫁(BRIDES FOR SALE)」を全身全霊をかけてスピットするソニータ、二人の姿は既定の倫理原則にとらわれず自由を渇望し真実を追い求めるアーティスト像として重なり、時代を挑発する。
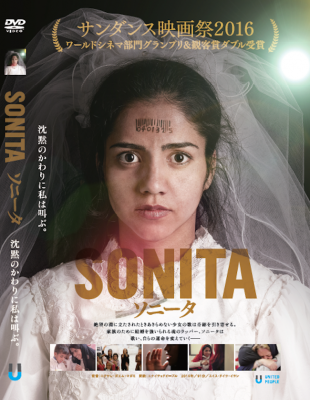
『ソニータ』
監督:ロクサレ・ガエム・マガミ
出演:ソニータ・アリザデ、ロクサレ・ガエム・マガミ
製作総指揮:ゲルト・ハーク
配給:ユナイテッドピープル 2015年 / 91分 / スイス・ドイツ・イラン
https://www.cinemo.info/dvd.html?ck=51&ippan=1
amazon
『HOMECOMING: ビヨンセ・ライブ作品』
2018年コーチェラ・フェスティバルでビヨンセが披露した“ビーチェラ”は「コーチェラそのものより偉大だった」と評され、後にも語り継がれるまさに歴史的ステージとなった。
「コーチェラ行きを決めた時、花冠を用意するより自分たちの文化を持っていく方が大切だった」――そう語るビヨンセは自身の楽曲をアフロビートからダンスホール、ロックンロール、バウンスまでありとあらゆるブラック・ミュージックでアレンジすることで、先人たちが築き上げてきた黒人文化のレガシーを讃える壮大なステージをコーチェラに築いた。彼女自身にとっても特別なパフォーマンスとなったビーチェラを、8か月にも及んだ製作風景、そして実際のライヴ映像で追うドキュメンタリー『HOMECOMING』がNetflixにて公開されている。
本作で印象を残すのは、ビヨンセ自身が製作の段階にてHBCU(歴史的黒人大学、アメリカにおいて差別と抑圧を受けていた黒人に高等教育の機会を与える目的で作られた)のマーチング・バンドや100人以上の黒人ダンサーらによって構成されるクルーを集め、全員の団結をはかり各個人のルーツや現状に関心を持たせることに精力を費やしている点だ。「これまで代弁者を持たなかった人たちが、舞台にいるかのように感じることが大事なの。黒人女性として世界は私に小さな箱に閉じ込められていてほしいのだと感じてきた。黒人女性は過小評価されてるとも。ショーだけじゃなく 過程や苦難に誇りを持ってほしい。つらい歴史に伴う美に感謝し、痛みを喜んでほしい。祝福して、不完全であることを、数々の正しき過ちを、みんなに偉大さを感じてほしい。体の曲線や強気さ 正直さにそして自由に感謝を。決まりはない、私たちは自由で安全な空間を創造することができる。私たちの誰ものけものにされない」。彼女が目指した最終的なゴールとはクルーへ語ったこの思いを、パフォーマンスを通じ12万5千人のオーディエンスと4000万人のライヴ・ストリーミングを見守る視聴者へ共有することで、自身のルーツや存在に誇りを持つことの意義を確立させることだった。
「I’m a-a diva!と叫んで!」ステージ上から投げかけられる声に熱狂するオーディエンスの姿。「人々に大きな夢を抱かせて、限界など無いのだと見せることができた。なんだってできる。田舎者の私ができるなら、彼らにだってできる」――スーパースターとして不動の地位を築いているビヨンセが披露したニ夜のパフォーマンスは彼女がコーチェラのステージを降りた後も、これまで“のけもの”にされてきた者たちに希望と居場所を与え続ける。


Netflixオリジナル映画『HOMECOMING: ビヨンセ・ライブ作品』
独占配信中
text Shiki Sugawara
edit Ryoko Kuwahara
This text is available in English