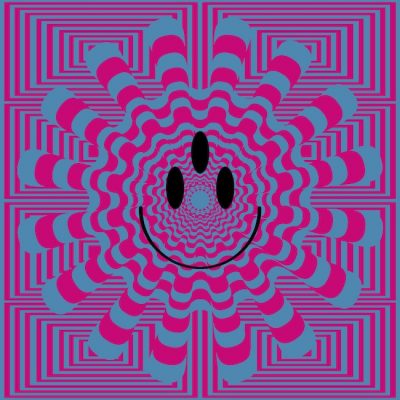ソウルを経由し現在はNYに拠点を置くエレクトロニック・プロデューサー/DJ/ヴォーカリストのYaeji(イェジ)は、初のフィジカルリリースとなる最新ミックステープ『WHAT WE DREW 우리가 그려왔던』をXL Recordingsからリリース。Yaejiは『WHAT WE DREW 우리가 그려왔던 (私たちが描いてきたもの)』というタイトル自体がプロジェクト全体の精神を捉えているという。このプロジェクトは“友人、家族、感謝と支え”が主なテーマとなっており、「私が支えられたり、支えたり、そしてお互いを支え合うということ」を描いている。彼女の中で特定の物語はなく、各トラックは彼女の人生の一部を切り取ったものというのだ。マスタリング・エンジニアは、坂本龍一やスロウダイヴ、ディア・ハンター、バトルス、プリンセス・ノキアなどの作品も手掛けるヘバ・カドリーが務め、アルバムには彼女のニューヨークシティのコミュニティーなどに属している新鋭のアーティストたちがゲストとして集っている。東京のDJ/プロデューサー、ヨンヨンのほか、オークランド 出身ブルックリン在住のラッパー、ナッピー・ニーナや、ロンドンのパフォーマンスアーティスト、トロント出 身のアジア系ドラァグ・アーティストのヴィクトリア・シン、ロンドンのプロデューサー、シャイ・ワンなどだ。ヴィジュアルアートにも造詣が深いYaejiによるMVも必見で、となりのトトロの「さんぽ」のオープニング映像にインスパイアされたという“WHEN I GROW UP”のリリックビデオも公開されたばかり。ポジティヴな気持ちになれるこれらの楽曲とヴィジュアルアートをぜひチェックしてほしい。(→ in English)
――あなたはニューヨークで生まれ、その後いくつかの国で生活をしてきました。その当時の様子や気持ちはどのようなものでしたか?
Yaeji : 私はニューヨークのクイーンズで生まれて、最初の4年間そこに住んでいました。その頃のことはあまり覚えていないけれど、その後、アメリカ南部にあるジョージア州アトランタに家族と引っ越して郊外に住んで、そこの公立小学校に通っていたんだけど、それはあまり良い体験としては覚えていません。私は唯一の有色人種で唯一のアジア人だった。何年生だったか忘れたけど一時期、モンゴル人の女の子と、韓国人だったかな? 忘れちゃったけどもう一人アジア人の子がいたくらい。とにかく、そこでは韓国人なんて滅多に見ないし、人種差別が確かにありました。だから小学校低学年の頃はかなり苦労しましたね。
――ニューヨークとは全く違うでしょうね。
Yaeji : そう。それに90年代だったから時代も違っていて。その後、家族が韓国に帰国することになりました。仕事や家庭の理由というのがあったと思うけれど、私が家で韓国語を話さなくなってしまったということもあって、韓国の文化にもう少し触れさせたいと親が帰国を決めたのだと思います。韓国で小学校の高学年と中学、高校を過ごしました。でも私は転校をよくしていて、その間の期間も日本に1年間住んでいたんです。韓国ではアメリカンスクールにほぼ通っていて、日本では中学生の頃に東京韓国学校に通っていました。だから日本に住んでいた時に初めて韓国の教育を受けたんです。どこに住んでいても私の状況は少し変わっていて、目立っていたり、周りと合っていなかったりしていましたが、そこから学ぶことは常にありました。
――音楽の道に進むきっかけは?
Yaeji : 一番大きなきっかけは大学生の時に大学のラジオ局WRCTに入ったこと。それまでも音楽は好きだったけれど、ずっとヴィジュアルアートに専念していたから、音楽をメインでやっていくとは想像もしていなかったんです。でもラジオ局で番組の司会をやったり、DJをしたり、音楽を通して自分が心から共感できる人たちと友達になったりしたことによって、音楽が大好きになって。それは情熱的ですごい勢いで芽生えた感情で、その結果、今の私がいるというわけです。
――影響を受けたアーティストや愛聴してきた作品はなんでしょうか?
Yaeji : この世にはくさんの音楽があるから、こういう質問は難しいですね……。覚えている限り、私は今までずっとR&B、ヒップホップ、ソウル、ジャズが大好きで、多大な影響を受けてきました。中学か高校の時は韓国にいたから、アメリカの音楽やヨーロッパの音楽は、少し遅れたタイミングで入ってきていて。だからミッシー・エリオットやアッシャーを聴いていたんだけど、海外の人たちとは少しずれた時期に聴いていたと思います(笑)。それから、周りの人が誰も聴いていなかったようなボーン・サグズン・ハーモニーとか。理由は分からないけど、学校のみんなはあまりR&Bやヒップホップを聴いていませんでした。みんなは当時人気だったロックを聴いていたのかな。私は、R&Bやヒップホップが基盤で、そこからジャズ・エレクトロニカやボサノヴァ・エレクトロニカなどを聴くようになりました。日本でも流行っていましたよね。渋谷系にハマっていたし、韓国でもClazziquai Projectという人気グループがいて、ダンスミュージックみたいなんだけど、ボサノヴァの影響も受けていて、特徴的な歌い方をする女性ボーカルがいて。それにも影響を受けました。日本ではファンタスティック・プラスティック・マシーンとか、それに似た感じのアーティストたちも他に何人かいましたよね。高校ではそういう人たちの音楽を聴いていました。その後、大学でダンスミュージックを聴くようになったけれど、その前段階として、今言ったアーティストたちには直に影響を受けていたと思います。
――私があなたの存在を知ったのは、4年ほど前にDISCWOMANのサイトで公開されたDJミックスでした(http://www.discwoman.com/mixes/yaeji)。いまでもブルックリンのアンダーグラウンドシーンとは繋がりが強いと思いますが、シーンと繋がるまでの経緯を教えてください。
Yaeji : ニューヨークに移った後、私はかなりの頻度であらゆるクラブやイベントに出かけていて、7日のうち5日間は遊びに行ってました(笑)。土・日で3つ、4つのパーティに行ったりね。色々なDJを聴きに行ったり、音楽という共通のものを愛する様々な人たちに出会える場に行きたいという熱い想いがあったんです。大学時代に出会えた今でも仲の良い友達たちとは、音楽を通じて繋がったんです。私のことを理解してくれて、私が素の自分をさらけ出しても安心していられる友達たち。コミュニティと出会ったのはそういう繋がりからです。今ここにあるコミュニティはお互いのことを強く支え合っていて、DISCWOMANはもちろんその1つ。私がBossa Nova Civic ClubでDJする機会を初めてくれた人たちです。Bossa Nova Civic Clubは大きなクラブでもないんだけれど、私たちみんなにとってとても大切なクラブだったし、今でもそう。DISCWOMAN以外にも、多くの人たちが私がギグをできるようにサポートしてくれました。それから私はコミュニティに深く関わるようになりました。自分でもパーティを企画したりしてね。お互いがお互いを高めようとする、とても良い環境でした。
――『What We Drew 우리가 그려왔던』は、XL Recordingsからのリリースとしては初めての作品になります。あなたは『What We Drew 우리가 그려왔던』はミックステープだと言っていますよね。ボリューム的にはアルバムと言ってもいいと思うのですが、あくまでミックステープとする理由はなんでしょう?
Yaeji : このミックステープの作曲プロセスはとてもゆるくてオーガニックなものだったんです。「今回のプロジェクトではこれを伝えたい」とか「こういう物語を語りたい」という主張を持たずに、毎日スタジオに行って、その日に感じたことや、メモしていたこと、その週に私に起こった出来事などについて書いていました。比較的カジュアルでゆるい短編集みたいなものだったから、ミックステープと呼ぶ方が合っていると思ったんです。“Free Interlude”という曲では、音楽を遊びでやっている親友たちと一緒にフリースタイルしたりしていて、その素材も意図的にこの作品に入れました。そういうのもアルバムじゃなくて、ミックステープっぽいでしょう?(笑)その方が自由に作れると思ったんです。
――これまでの作品はハウス色が濃かったと思うのですが、本作はとても多彩な作品に仕上がっていて、よりポップ・ソングの形に近い曲が多いと感じました。この変化は意識したものですか?
Yaeji : 作曲をしているときは特にジャンルを意識していません。だから私のこれまでの作品はハウス色が濃くて、今回はポップに近いということに気づきませんでしたが、その意見もわかります。このミックステープにたどり着くまで、私は色々なプロダクションの技術を学びました。そのおかげでより多様な音にチャレンジすることができました。もっと冒険することができた一方で、音響的には良いものしようとしました。プロダクションに自信がついて、自分の声をより面白い響きになるように操作できるようになったし、自分の声に自信を持つことができたんです。だから今回はより実験的なサウンドに仕上げることができたのかもしれません。
――本作にはナッピー・ニーナ、ヴィクトリア・シン、シャイ・ワンなど多くのゲストを迎えています。これらのアーティストとはどのように出逢ったのでしょうか?
Yaeji : “Money Can’t Buy”に参加してくれたナッピー・ニーナとは幸運な出会いをしたんです。“Money Can’t Buy”の作曲が終わって、最終的なミックスの仕上げを友人のミキシングエンジニアと一緒にしているときに、この曲に女性ラッパーを入れたいけれど結局誰も思いつかなかったという話をしていて。そしたらその友人がナッピー・ニーナのことを教えてくれて、私と彼女には共通の友達がたくさんいることがわかって。彼女はその日の数時間後にスタジオに来てくれて、バースを完璧に録音して、楽しい時間を共に過ごすことができました。今でもよく連絡を取り合っていますよ。運命的な出会いの一例ですね(笑)。ヨンヨンは学生の頃から知っていて、日本での同級生でした。彼女は昔から音楽の道に進みたいと言っていて、今も活躍しています。彼女がDJを始めた頃、私もアメリカでDJを始めた時期で、再び積極的に連絡を取るようになったんです。彼女にはいつかゲストで参加してもらおうとずっと思っていて、今回の曲で彼女にぴったりの曲ができたから参加してもらいました。ヴィクトリア・シンとシャイ・ワンはパートナー同士でロンドンに住んでいます。ミックステープの制作を始めた2年前の夏、私がロンドンのサーペンタイン・ギャラリーで個展をやった時にヴィクトリアと知り合いになりました。彼女たちもサーペンタインでパフォーマンスをやっていて、お互いがお互いの作品のファンだったから、その後も連絡を取り合って仲良くなりました。今回ゲストで参加してもらった人たちは、昔からの友達か、結果として友達になったという人たちばかりですね。
――『What We Drew 우리가 그려왔던』では、あなたが聴いていた韓国のインディー・ロックや、1990年代後半から2000年代初期のヒップホップとR&Bを取りいれたそうですね。具体的にどういったアーティストからインスピレーションを受けたんでしょうか。
Yaeji : そういう音楽が作曲中の私のサウンドトラックになっていましたが、どの程度の影響があったのかは分からないです。でもソランジュはよく聴いていました。今作の終盤くらいにソランジュの公演を初めて観る機会があって、衝撃を受けました。あとは、両親が薦めてくれた80年代の韓国の音楽を聴いていました。「春夏秋冬」という昔の韓国のバンドがいて、父親が大好きなんです。私が聴いていたのはこれだけではないけれど、私が再発見しようとしていたのはこの時代の音楽ですね。最近の音楽でよく聴いていたのは、ムーディーマン。でも彼の音楽はとても良いハウスミュージックだから以前から聴いていますね。
――本作の歌を聴き、これまでの作品よりもリラックスしていて、オープンな印象を受けました。以前よりも自分を出すことに積極的になったなどの変化があったんでしょうか。
Yaeji : それは確かにありました。その一因として自分について多くのことを学んだというのがあると思います。自分についての学びは毎日あるんだけど、特にこの2年間は私のキャリアにおいてめまぐるしい変化があって。その過程を経験したことで自分について多くを学べたんです。癒されたし、素の自分に対して自信がついたというか、心地良くいられるようになりました。それから、ある特定の音楽を作らないといけないというプレッシャーをあまり感じなくなったというのもあります。なぜかはわからないけどそのプレッシャーからは完全に解放されました。周りの環境がとても協力的で愛情に満ちているからだと思います。だから何を作ってもいいんだという気持ちが、リラックスした感じや、心地よさや遊び心として音楽に出ているんじゃないでしょうか。
――すべての収録曲がお気に入りですが、“Money Can’t Buy”には特にハマっています。この曲のヘヴィーなシンセ・ベースにはアシッド・ハウスの香りがありますが、アシッド・ハウスは好きなんでしょうか?
Yaeji : アシッドのベースラインはとても好き。ベースが全般的に、ものすごく大好きなんです。ベースが一番好きな音だし、ベースのパートを書くのが一番楽しいと感じる時が多いです。だから、そういうコメントをしてくれるのは嬉しいです。
――“Waking Up Down”のMVを初めて観たとき、思わず笑みを浮かべてしまいました。80年代エレクトロ的なトラックをバックに、『クッキングパパ』あたりを連想させる日本の90年代アニメ風の映像が流れるからです。このMVのアイディアはどこから生まれたんですか?
Yaeji : 両親が仕事で忙しかったから私は子供の頃から日本のアニメをたくさん観てきました。その影響は確かにあります。初めて観たのはセーラームーン。すごくハマっていました。私や私の友達が今でもよく観るアニメは実験的なものからポピュラーなものまで色々あって、20年以上もアニメを観続けてきたということに改めて気づきました(笑)。私はヴィジュアル・アートが好きだから、日本のアニメの作風での短編アニメーションの作り方に以前から興味があったんです。だから絵コンテを作って、MVのキャラクターになるようなキャラたちを描き始めた。“Waking Up Down”でそのアニメを作ったら一番面白いんじゃないかと思って制作することにした。アニメのオープニングみたいにしたら良いと考えていて、ラッキーなことに、私のルームメイトはプロのアニメーターだからビデオの制作を手伝ってくれて一緒に完成させてくれました。協力してくれた人たちがアニメについて詳しかったことはとても助かりました。アニメのビデオにして、ユーモアがあって、見た人がポジティブな気持ちになるようなものにしたいという考えがありました。
――最後に、チャリティー・コンピの『Physically Sick』に曲を提供するなど、あなたには確固たる信念や理想があるように感じます。それを育むうえで重要だった人や出来事を教えてください。
Yaeji : 説明するのは難しいけれど、アーティストは、それぞれが何かしらの形で社会に影響を与えていると思うんです。自分の最も脆弱な部分を人々と共有しているから。意見を声に出すということを実際にはしなくても、自分を表現していますしね。その共有の仕方はアーティストによって違うし、それを受けた人がどう活用するのかも人によって違う。私は、自分のプラットフォームが大きくなったことに心から感謝しています。私の音楽やメッセージを聴いてくれる人たちがいることは本当に恵まれていますよね。そういう状況にいて、私は、自分が大切に思っていることを主張していく必要があると気づきました。この素晴らしいプラットフォームを与えられたのだから、それを活用して、他の主張がある人たちが主張できるように手助けをしようと思ったんです。この考え方は、自分が育った環境によるものかもしれないけど、自分にとっては当たり前のことでした。最近、自分をさらにその方向性へとプッシュしたきっかけはMIAのドキュメンタリーでした。全ての人に観てほしい。音楽だけじゃなくて政治的な内容も含まれているんです。ドキュメンタリーの中でMIAは「ミュージシャンならなぜ主張しない?なぜ主張するために音楽を作らない?」と言っています。本当にその通りですよね。

Yaeji
『WHAT WE DREW 우리가 그려왔던』
(XL Recordings / Beat Records)
NOW ON SALE
国内盤CD ¥2,200+税
国内盤特典:歌詞対訳・解説/ボーナストラック追加収録
BEATINK.COM
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10918
AMAZON: https://www.amazon.co.jp/dp/B08566V61G
Apple Music: https://apple.co/2IE3LrA
Spofity: https://spoti.fi/2IAurtc
TRACKLISTING
01. MY IMAGINATION 상상
02. WHAT WE DREW 우리가 그려왔던
03. IN PLACE 그 자리 그대로
04. WHEN I GROW UP
05. MONEY CAN’T BUY (ft. Nappy Nina)
06. FREE INTERLUDE (ft. Lil Fayo, trenchcoat, Sweet Pea)
07. SPELL 주문 (ft. YonYon, G.L.A.M.)
08. WAKING UP DOWN
09. IN THE MIRROR 거울
10. THE TH1NG (ft. Victoria Sin, Shy One)
11. THESE DAYS 요즘
12. NEVER SETTLING DOWN
13. When In Summer, I Forget About The Winter *Bonus Track for Japan and South Korea