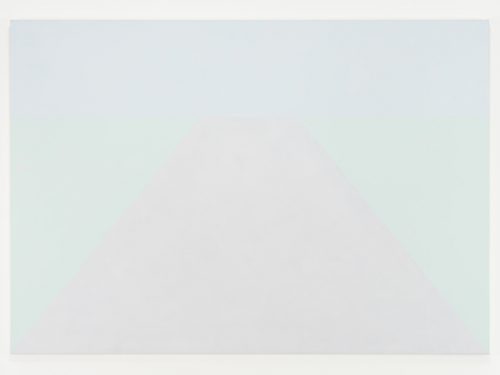セルフビルドで家を建ててみたい、いつの頃からか、そう願い続けてきた。理由は簡単だ。エゴが強かったからだ。要は自分の力だけで、どこまでできるのか、それを試したかったのだ。
段取りとしては、まずは土地探しである。
フリーランスとは言え、東京から遠く離れるのは、まずい。いや、フリーランスだからこそだ。作業はどこにいてもできるのだから、わざわざ都内にしがみつく必要はない、というのはこっちの言い分で、仕事を依頼する方にとっては、なんとなく近くにいる人の方が頼みやすいという心理がある。もともと地方で活動している人ならその例にもれる。だが、都内から北海道や京都に移住したとなると、半分やっかみもあるのだろうか、仕事は激減する。そういう例は結構見てきた。
なので、候補地は、千葉、埼玉、神奈川、あたりが適当だろう、と考えた。だが、自分がイメージする1000坪にポツンと建つ小屋のイメージを叶えるには、地価のことは考えないといけない。土地の予算は500万円。都内なら駐車場も買えない値段だろう。
そもそも潤沢な資金にモノを言わせて、田舎の一等地を鷲掴みするような手つきで買うことは、主旨とは違うし、だいいち、そんなお金はそもそもない。坪五千円の山林もしくは原野を見つけて、整地し、二年くらいかけて一人用の小屋を建てる、というのが夢なのであって、土地探しの苦労も楽しみのうちだと考えていた。
土地探しは、結構骨の折れる作業であった。
週末は、ほぼそれに費やした。南房総、秩父、奥多摩、相模湖周辺をドライブし続け、まずは気に入ったエリア選びに時間をとった。だが、こんなことをするのは初めてだし、パートナーもいないので、単独行を繰り返すうちに、正直なところ、夢が色褪せそうに何度もなった。正気になって考えれば、いったい何をしようとしているのか、分からなくなっていった。都内のマンションのローンも残っているというのに、なぜ貯金の多くを使って、ど田舎に小屋をセルフビルドしようとしているのか。
理由は簡単だ。エゴが強かったからだ。
自分の力を試し、自給自足し、あわよくば自分の存在理由などを肌身で感じてみたかったからだ。
そんなこんなで、当初の予定とは違ったが、山梨の北杜市に、元資材置き場の土地を見つけた。1000坪とはいかず、400坪とスケールダウンしたものの、大きな道から少し入っているため静かで、周りは森である。資材置き場だったくらいなので、大方の部分は伐採も済んでいて、坪1万だったため、400万もしたのだが、馬を飼うわけでもないから実際1000坪は要らないのだった。
400坪といえば、都内なら堂々した広さになるが、周囲が牧草地や畑に囲まれた中では、まるで箱庭同然である。それでも唐松や白樺などの樹木が隣の土地との目隠しとなっているため、八ヶ岳南麓の趣もしっかり楽しめるいい土地だと、気に入って購入したのだ。
次なる家づくりだが、予算は300万円。これは、木工を知る人なら分かると思うが、立派な物置は建つが、人が住む家の予算としては、かなり心細い金額だ。当然、ホームセンターなどの安価な資材を主に使い、できるだけ一人でやるつもりでいた。
セルフビルド関連の書籍は案外多く出ていて、それに加えて、ネットなどの情報を集めれば、知識としては十分な量が得られる。あとは、それを現実化していく作業力が問われるだけだ。
その作業力などは、全く無いも同然であった。犬小屋さえも作ったことが無いのだから、よくもまあセルフビルドで家を建てたいなどとぬかしたと、我ながら思う。だが、誰もが始めは初心者なのだ。そこから腕を練り機が熟すのを待つ代わりに、間を抜いただけのことだ。その分の苦労は多いと思うが、年齢的にもぶっつけ本番でいいと割り切った。
自分で言ってしまうが、もともと器用な方なので、プロの仕事と比べたらひどい結果になるかもしれないが、自分で合点がいく程度にはもっていける見込みはあった。セルフビルド系のメーカーからキットも販売されているが、あれだとまるでプラモデルの延長すぎる。組み立て手順から寸法まで決められては、何のためのセルフビルドだろう。そもそも自分のエゴを満たすためのものだから、やはり気ままがいいに決まっている。
土地を購入してからは、週末の居場所は、北杜市の某所となった。そこでテントを張って、金曜の夜から月曜の早朝まで居座り、まずはその土地と馴染むことに徹した。大きな道から入った土地だとは言え、車の通る音は聞こえるし、人の気配も遠くにある。だが、鹿や狐が堂々とテントの近くを通り過ぎてくのを足跡で知った時は、驚きと喜びに包まれた。野生動物の近くで暮らせるというのは、望んでいたことの一つだったからだ。
高井戸からわずか2時間ほどなのに、都会の光はすでに前世のように遠く、聞こえてくるニュースは木々のざわめきに置き換わっていた。
一週間のうちの半分以下、三泊だけの山生活であったが、計算して持ち込んだ食糧が尽きる頃には、細胞が入れ替わるような心地よさと静寂とが得られた。考えてみれば、そのような静寂を得るために400万円を費やしたのは、高いのか安いのか、適当なのかは分からないが、自分としてはいいお金の使い方をしたと満足した。そもそも絵描きとは名ばかりで、知り合いからイラストの仕事をもらってどうにか食い繋いでいる身分には、不相応とも言える暮らしだとさえ感じた。
ここを根城にして、自給自足の生活を数年以内に確立できたら、現金収入のために絵やイラストを描けばいい。そもそも自給自足ができていれば、月に10万円も稼げれば十分だろう。未来は、ほんのりと優しく微笑んでいるように感じられた。都内のマンションのローンは、あと15年ぐらい残っているから、もちろんそれは別に頑張って稼ぐか、途中で売ってしまってもいい、そんな風に気楽に考えていた。
20代の頃から、40才前には、誰にも頼らずに生きていけるようになっていたい、と考えていた。そんなことを友達と飲みながら話すと、大方の人は、誰かと助け合って人は生きていくものじゃないか、とか、むしろ誰かに頼って楽に生きていたいとか答えるのだった。それはある意味、衝撃的なことで、自分にとっては何よりも自立が幸福の前提であると思っていた。

そんなある週末、季節は夏の終わりだった。どういうわけか蚊がほとんどいない夕暮れのことだった。
基礎工事を明日に控え、わくわくしながら、焚き火に一人で向かい合い、立原道造の詩を読みつつ、あと30分はランプなしでも読み続けたいと片隅で気にしている頃だった。
誰かの視線を感じて、ふと視線を上げると、我が土地の入り口あたり、距離にして15メートル先に犬科の動物が一頭いた。大きさは、中型犬ほど。一目でそれが野生動物だとは分かった。首輪をしている、いないとかではなく、気配でそれが分かった。
最初は狐かと思った。鼻先の長さがそう思わせたからだ。色は夕暮れの半闇のために、はっきり分からないが、灰色に茶が少し混じっているようだった。だが、狐ではない。狐というよりは犬である。でも犬とは違う。
ハッとした。まさか。
記憶の影を辿る。一瞬にしてそこへアクセスする。おそらく、きっと、いや、違うだろう、でも、間違いない、まさか。感嘆詞や、呟きが脳内をぐるぐると巡る。そういう時の一瞬は長い。
私は携帯へと伸びようとする右手を、自ら制した。
経験上、野生動物を撮影しようとした時に、彼らは本能的に逃げると知っていた。撮影は、英語でシューテングとも言う。つまり狩りだ。捉えようとする気持ちを察した動物は、当然逃げようとする。
そんな半端な精神状態を察したのか、犬科の野生動物は、半身になっていつでも逃げ出せる態勢をとった。だが、その姿を違ったアングルから見定めるには、むしろ好都合であった。尻尾は真っ直ぐに伸び、狐のそれよりは膨らみと長さに欠ける。首のまわりには一際豊かに毛が密集し、立髪と呼べるような厚みがある。
秩父、大分、東北などの山塊での目撃例が報告されていることは、隣の富士見町にある書店で、立ち読みして知っていた。その本には、数枚の写真も掲載されていて、結構長い時間を費やして、魅入ってしまった記憶が蘇る。
その動物は、じっとして動かない目の前の人間に少しは気を許したのだろうか。我が土地を検証するように、うろうろし始めた。さっさと森に消えても良さそうなところだが、わざわざ人間によって整地された400坪の土地を嗅ぎまわり始めたのだ。所々に鹿の糞があるので、その匂いに気を取られたのだろうか。やがて、人間を全く気にしない様子で、時々寝転んだりし始めた。
その様子をじっと見つめて観察した。写真も動画も残そうとせずに、二つの裸眼に自分の全てを託すような覚悟すらあった。しっかり観察して、あとで絵を描くのだ。そのために、今を費やそう。
やがて夜が来た。焚き火の明かりも手元を照らすのみとなり、もはやその犬科の動物は見えなくなった。ライトで動物を照らしはしなかった。なんとなく、それがフェアに思えたからだ。テントに戻り、スケッチブックとボールペンを手にして、再び焚き火に戻った。小さくパチパチと音を立てる燃える木々。それを耳に音楽として与え、手を動かした。あの動物の様々な姿態を観察したのだが、結局描いたのは、四本の足でしっかりと大地に立ち、顔を正面に向けている姿だった。
明日になれば、自分の家が始まる。自分の400坪の土地に、自分の力を頼りに、存在証明的なエゴを満たすために。自分。自分。自分。
今まで付き合った6人の男たちは、みな、わたしを女らしいと言ってくれた。これからこの土地で一人で奮闘するわたしの姿を見ても、彼らはそう言うのだろうか。
描き終えた絵に、自分の名前を入れる代わりに、わたしはカタカナ7字を添えた。
ニホンオオカミ。
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
#4 裸を撮られる時に、百合は
#5 モルディブの泡
#6 WALKER
#7 あの日のジャブ
#8 夏休みよ永遠に
#9 ノーリプライ
#10 19, 17
#11 S池の恋人
#12 歩け歩けおじさん
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある。