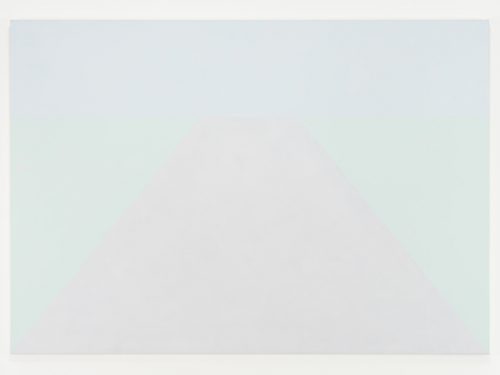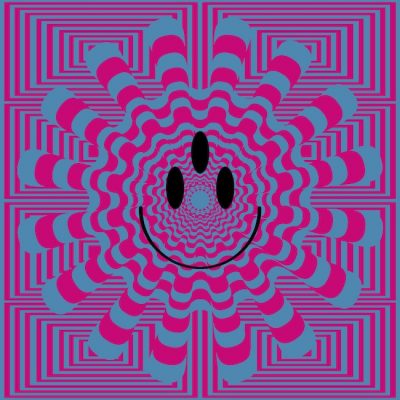柑橘類が送られてくると、ああ、もうそんな時期かと思う。
白い定型の段ボール箱を配達人から玄関先で受け取ると、伝票を確認するまでもなく、贈り主が分かる。小さい箱だが、受け取るには両手を必要とする重みがある。間違いない、あの人たち、からだ。
最後にあの二人と会ったのは、もう十年以上前になるだろうか。
息子さんのお通夜の時だから、やはり、そのくらいにはなるだろう。今治の市民葬儀場の一室に横たわる、26歳のすっかり様変わりした彼の姿は、おそらく一生忘れられないだろう。
すうっと伸びた鼻筋は生前のままだったが、窪んだ眼窩は、彼の闘病の苦しさを形にして伝えているようで、いたたまれなかった。わたしが焼香を終えると、二人は昔と変わらない微笑みを浮かべて、ありがとうね、と言ってくれた。
もう随分と前になるけれど、かつてわたしは週に一度はこの微笑みに接していた。久しぶりに見たその微笑みを見て、それまで彼の死を前にしても動じなかった涙腺が滲んでしまった。
二人の息子さんである彼とは、高校生三年生の時に一年間だけ付き合った。
お互いに受験を控えていたので、支障がないようにと、会う時間や電話も制限していたけれど、恋というのは、もともと融通が効かないから恋なのであって、わたしたちは、受験に支障が出るとわかった上で、会えるだけ会い、できるだけ電話をした。そうするしかできなかった。会わないでいたら、なおさら勉強など手につかなかったのだから。そう、わたしたちはそれぞれ初めての恋人で、ただ真っ直ぐにしか付き合えなかったのだ。
それでも、わたしたちは志望校に合格してしまった。その他の滑り止めまで全て落ちたので、まぐれが二つ重なったことになる。
憧れていた東京で、恋人といつでも好きなだけ会える新しい生活。
あの時のわたしは、全てを手に入れてしまったような気がして、喜びと戸惑いの重みをなんとか支えていたけれど、思えばあの時の幸せは、わたしには過分だったと今では分かる。幸せは、多すぎると、手に負えずにどれかを手放さなくてはいけなくなる。
結局、その彼とは、夏が始まる前に別れた。その後もしばらくは連絡を取り合っていたし、何度か会いもしたが、新しい恋人がクリスマス前にそれぞれにできると、連絡は完全に途絶えてしまった。以来、亡骸と対面するまで、彼とはそれっきりだった。
高校最後の年の思い出も、年月と共に色褪せて、今では彼と付き合っていたことすらあやふやだ。あの頃のわたし達は、いったいなぜあんなに盛り上がっていたのだろう。毎日のように会い、何を語り合っていたのか。将来の夢だろうか、お互いへの気持ちだろうか。
土日は、彼の自宅で受験勉強することが多かったので、当然彼の両親とも沢山会うことになった。
彼の真っ直ぐな性格と優しさは、両親それぞれから引き継がれていて、わたしは、何の気兼ねもなく、小さなお嫁さんにでもなったような気すらしていた。
娘のいなかった彼らにとって、私は、息子の恋人というよりも、娘のような存在だったのかもしれない。でなければ、別れた後も、毎年柑橘を送ってくれるのだろうか。

夫の仕事の関係で、今は、埼玉県の秩父に住んでいる。
学生時代から数えると、実に十回ぐらいは引っ越しをしているのだが、ちゃんと新らしい住所へと、柑橘類は毎年届けられてきた。彼らには年賀状を欠かしていなかったためかもしれないが、もし住所不定だったとしても、彼らはしっかり調べて送ってくれたことだろう。
しかし、改めて思えば律儀な人たちである。
言わば、たった一年しか実質的な付き合いがなかった人、息子の短期間の恋人に対して、こうまでする親がいるのだろうか。わたしは、親友にさえも、なぜかこの件を話してこなかったけれど、中には気持ち悪がる人がいてもおかしくないだろう。
もちろん、わたしは、ただありがたく受け取ってきた。
丁寧にしっかりと箱と同色の白いテープで留められた段ボールを開けると、いく種類かの柑橘がいつも入っている。様々なサイズの黄色い実たちから立ち昇る香りは、愛媛の風景を運んでくれる。わたしは、しばらくの間、その実を手に収めながら、彼らの姿を思い浮かべ、故郷の街を懐かしみ、なんともいえない安らぎを得るのが常だった。
だが、今年はゆったりもしていられなかった。
最近は、宅急便や郵便物が届くとなると、小学生3年生になったばかりの息子が、駆け寄ってきて、中身を見せろとせがむのだった。
息子は、箱の中の、柑橘類が行儀良く並んだ姿に、声をあげて興奮し、食べさせろと大声でせがむ始末だった。当然、愛媛の風景など立ち現れる隙間もなかった。
どれがいい?と聞くと、一番大きいのがいい、と言う。
「で、こ、ぽんっ!」
そんな風に柑橘に添えられた付箋を、息子は読み上げてから、奪うように箱から取り出すと、ベランダへと逃げ去るのだった。
やれやれ、と呟きながら、せとか、はるか、と私までもが付箋を読み上げていた。
糖度の高さや味の華やかさでは、せとか、なのだろうが、わたしは断然はるかの爽やかさが好きだ。なので、はるかが入っていたことに、子供のように喜んだ。わあい、と小さく声にして。
息子は、ベランダでしばらくわたしを待ち伏せていた様子だったが、追いかけてこないと分かると、つまらなそうな表情でキッチンへと戻ってきた。
「でこぽん、食べる?」
わたしがそう聞くと、息子は首を左右に力強く振って、キッチンを去った。
実は我が家では、夫も息子も柑橘類への執着がなく、段ボールで届く柑橘は、ほとんどがわたしの胃袋へと収まる。好む人のところへ届く方が、柑橘にとっても本望だろう。今回は、10個いただいた。1日1個ずつ、10日も楽しめる。私は、秩父の寒空の下に生える黄色やオレンジ色に、故郷の太陽の香りを得た思いがした。春を待つ季節の終わりに、素敵なアクセントをいただいたことを、あらためて感謝しながら。
早速、贈り主へメールを送る。いつもなら、返信は五分も空けずに帰ってくる。だが、今回は、そうではなかった。わたしはそのことをたいして気にも留めず、さっそくいただくことにした。
最初の1個は、多めに入っているせとかに決めた。
甘く、香りも強く、瑞々しい。外の皮を剥いてしまえば、中の薄皮ごともりもりと食べれるのも人気の秘密だろう。わたしが愛媛に住んでいる頃は、値段も高いのであまり食べなかったが、今では、もっと食べておけばよかったと後悔している。後悔という言葉は決して大袈裟ではない。せとかを食べたことのある人なら分かってくれると思う。
やっぱり、おいしい。
せとかの一粒一粒を隔てる皮は、とっても薄くて、粒を離すのが難しい。なので、適当にもぎると、二、三粒いっぺんに付いてくる。それを大きく口を開いてかぶりつく。口いっぱいに広がる果汁と香り、そして張りのある小さなつぶつぶ。
ああ、果報者だ、と、ちょっと古めいた言葉をあえて使いながら、そのおいしさに浸る。
贈り主からの返信メールは、結局その日中には来なかった。
翌日も、その翌日も、既読すらつかなかった。
少し心配になり始めた頃、ようやく返信が届いた。
こずえさんも、はるかが好きなのですね。私たちも同じなんです。せとかやでこぽんよりも、控えめなはるかを好んでいます。息子の豊もそうでした。覚えてますか?受験の直前、我が家での最後の受験勉強のおやつが、はるか、でしたね。二人とも志望校に合格したので、以来、我が家では、はるか、は縁起物になりました。今年のはるかは、まあまあの出来でした。また来年送りますね。一年、お元気でお過ごしください。
その返信を読み終えた頃、ちょうど夫が仕事部屋から出てきた。疲れた表情をしている。
「何か甘い物でも食べる?」
わたしは、豆大福を買っておいたことを思い出しながら、そう声を掛けた。夫はお酒も好きだが、甘い物にも目がない。
「うーん、そうだな。そのみかん、もらおうかな。」
夫は、私の手元を見ながら、呟くように言い、さらに続けた。
「ところで、生まれてくる女の子の名前だけど、なかなか決まらなくて」
夫は頭を掻きながらそう言った。わたしはお腹に手を当てた。再来月には、生まれてくる子。
「はるか、ってどうかな?」
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
#4 裸を撮られる時に、百合は
#5 モルディブの泡
#6 WALKER
#7 あの日のジャブ
#8 夏休みよ永遠に
#9 ノーリプライ
#10 19, 17
#11 S池の恋人
#12 歩け歩けおじさん
#13 セルフビルド
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある