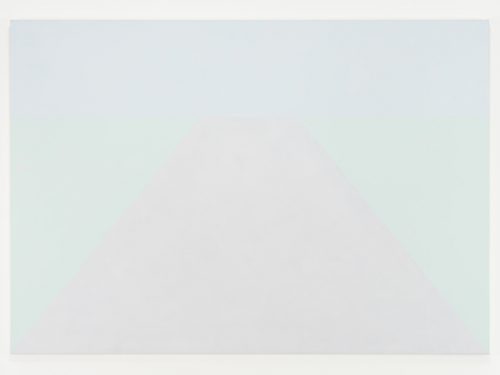「ねえ、ここ触ってみて」
3歳年下の新しいボーイフレンドが左耳をわたしに向けて、そう言った。
「さすがに2年もやってるとこうなるよね」
困惑と誇らしさの入り混じったような声で、彼は言い添えた。
彼の左耳上部の外側は、空気を入れて膨らませたかのように腫れていて、触ると固かった。
「えっ、固いんだ。」
わたしは思わず手を引っ込めてしまった。まさに腫れ物に触ったかのように。見た目は、ふわふわして柔らかそうなのに、肌の皮一枚越しに、小石が入っているかのように固かった。
カリフラワーや餃子に例えられるその耳の形は、柔術をはじめ、レスリング、柔道、ムエタイなどの耳を接触させる格闘技によって作られる。もちろん経験度や個人差にもよるが、それらの格闘技を嗜む人の耳は、そうなることが多い。それを格闘家の勲章のように思う人もいれば、醜いと嫌う人もいて、後者は定期的に針を刺して血を抜いたり、病院で治療してもらう。
私の彼はどちらかと言えば、前者らしく、最近白帯から青帯に上がったこともあり、尚更嬉しそうに見えた。
「これって、放っておいたらどうなるの?どんどん大きくなるの?」
わたしは、彼の容姿への心配ではなく、人間の身体への興味からそう聞いた。
「うん、大きくなるらしい。個人差があるらしいけど、耳全体に広がったり、大きくなったり、でも練習から遠ざかると、小さくなるらしい。」
「え、じゃあ、やめたら元通りにいずれ戻るってこと?」
彼は、わたしの興味津々な前のめり具合が意外だったらしく、一瞬わたしをしっかりと見つめ、少しの間をとってから続けた。
「詳しくはわからないけど、柔術クラスの先輩が昔よりも小さくなったって言ってた。だけど、元通りになるかは、わからない。そうだな、そういうのは聞いたことないな」
そんな会話を交わした2ヶ月後。驚くべきことに、わたしまで柔術を習い始めてしまった。
護身術として、というのが表立っての理由で、それは何歳になっても干渉してくる両親への牽制でもあったが、本当の理由は別のところにあった。
強くなりたい、というのも少しはあったが、わたしが欲したのは、あの潰れて膨らんだカリフラワー耳だった。わたしは、それを勲章としてでなく、アクセサリーのようなものとして憧れたのだ。ボディピアスやタトゥとかと一緒で、そのファッション性に目をつけたわけだ。
33という年齢が、果たしてカリフラワー耳に相応しいかは、どうでもよかった。おそらく彼のように2年もやれば、ああなるに違いない。タトゥだったら、何度かショップに足を運び、相応のお金を支払えば、それなりのものが数週間で得られるが、カリフラワー耳は、数年もかかる。その希少性にも正直惹かれた。
それは有名アーティストと有名ショップとの限定コラボなどの物欲的なものではなくて、タイの首長少数民族などに見られる身体操作への興味に近く、他者との差別化志向でもなく、言うなら変身願望に近いと思う。
わたしは、自分の内側にそんな願望があることに、少なからず驚いた。30年以上も生きてきて、それでも知らない自分がいる。だが、ちょっと考えば分かることだが、自分というのは固定化されたものではない。科学的には細胞が常に入れ替わり、体液は流れ続け、心臓は鼓動を打ち続ける。心や感情だって、3歳時とは全く違う。なのに、人は自分という意識を持つ時に、なぜか固定化された人格を描いてしまう。実際は、人は川の流れのようなものだ。それは大袈裟ではなく、ちょっと考えればすぐに分かることだ。固定化された自分という概念は、便宜上の架空のもので、幻想と言ってもいいくらいだ、と私は思う。わたしは、流れゆく川でありたい。

差し当たって、わたしは、彼と同じジムに通い始めた。
何か新しいことを始める時は、初日が大切だと経験から知っているのは、わたしだけではないと思う。それが物理的でも抽象的な意味でも、ドアを開けた先の、雰囲気、明るさ、匂い、それら様々なものが折り重なってわたしの前に現れて、その先に進むべきか、引き返すべきかを、教えてくれる。
既存のグループに加わるようなケースでいえば、そこに誰かの紹介があったりすると、気遣いや遠慮が入って判断力が鈍るのだが、あの日のわたしには、気を遣うものが何もなく、自分の印象だけが全てであった。
その初日は、もともと彼に一緒に来てもらうはずだったが、直前に仕事の用事が入ったとかで、結局わたし一人で行った。今まで、道着に袖を通した経験がなかったが、鏡に映った体験レッスン用の道着姿のわたしは、悪くなかった。
1時間クラスの流れは、最初にテクニックの練習、その後にスパーリング、といったものだった。
インストラクターさんの説明後に、そのクラスに居合わせた生徒さんからパートナーを選んで、教わったテクニックを反復して練習し、その後に相手を入れ替えながらスパーリングをするという流れだった。日々の練習は、基本的にこの流れの繰り返しで、テクニックがなかなか身に付かないもどかしさはあったものの、わたしの目的は、上達よりもカリフラワー耳だったので、とにかくたくさん練習をしようと毎日通っているうちに、半年が過ぎる頃には、自然にいくつかのテクニックも身について、私なりに上達しているように思えた。
その頃になると、ジム内でもほとんどのメンバーさんが顔見知りとなって、技術などを親切に教えてくれる人も多く、すっかり居心地のいい場所となってもいた。恋人の紹介で入会したことも周知の事実で、その彼が割と社交的で人好きされる性格でもあり、口には出さなかったが、居心地の良さは彼のお陰だと内心感謝していた。そのことをいつか伝えようと思っているが、改めて言うのも何だしと躊躇しているうちに、ずっと言いそびれている。
始める前は抵抗があったスパーリングなどでの男性との接触も、意外と始めから全く気にならず、それもすんなりはまった理由のひとつだ。そして、今や柔術が日常の中で大きなウェイトを占めるようになっていた。
そしてさらに半年が過ぎた。
わたしの白帯には、2本のストライプが巻かれていた。それは上達度の目印のようなもので、4本巻いた後では、次の色の帯に昇格するというのが流れであった。わたしが上達したかはあまり自覚がない。ただ週に5回も通っているので、努力賞的なものかな、と自分では考えている。
インストラクターさんに巻かれるテープは、想像よりも誇らしく嬉しいもので、日々の稽古の励みになる。だが、本音を言えば、わたしはそこには何の執着はなかった。試合にも出る気はなかったし、なんなら一生白帯でもいいくらいだ。
わたしが欲しいのは、カリフラワーだ。
柔術を始めて、1年になろうというのに、いまだにわたしのカリフラワーは芽さえ出していない。ボーイフレンドやインストラクターさんや、先輩に聞いても、みんな笑ってまともに取り合ってもらえなかった。それは、わたしが真剣さを表に出さなかったせいでもあるが、内心は焦り始めていたのだ。これが個人差ってものだろうか。全く耳が変形しない人もいるよ、などと軽々しい返事を受け取るたびに、愕然として憮然として、そして悲しみに沈んだことを、きっと誰も知るまい。

そして、今年の8月。
わたしとボーイフレンドは、一週間の夏休みをとって沖縄に来ている。連日天気もよく、わたしたちはレンタカーでドライブして人気のないビーチでシュノーケリングをしたり、夕方は海沿いのレストランで真っ赤な夕日を眺めながらビールを飲んだりして、夏の休暇らしい過ごし方をしていた。
そして、3日目の朝9時半から12時まで、柔術の出稽古に2人で出かけた。
先月オープンしたばかりのそのジムは、東京で通っているジムの支部で、わたしたち2人は快く歓迎された。ビーチに近いそのロケーションや、大きな窓からたっぷり入る外光などの効果のためか、開放的なその雰囲気は、初日から居心地の良さを感じた。
結局わたしたち2人は、残りの沖縄滞在の午前中のすべてを、そこで費やすことになった。
メインのインストラクターさんは、明るく気さくなブラジル人で、彼の醸し出す雰囲気につられて、クラスは笑顔が絶えず、強くなるよりも楽しむことを第1にしているような緩さが、わたしたちの夏休みとうまくマッチしていた。わずか数日の滞在でしかなかったが、沖縄に、というよりも、このジムにまた来たいと思わせる居心地の良さは、とても印象に残った。
米軍基地から参加している人も多く、一見屈強な外見な彼らだが、わたしの未熟な英語に対してもフレンドリーに対応してくれて、スパーリングもちゃんと力加減をしてくれたので、怪我もなかった。
そんな楽しい出稽古だったが、そのジムで出会った全ての人の耳を観察することも忘れていなかった。白帯の初心者の耳の全ては、普通の耳だった。青、紫、茶、黒帯の人たちのほとんどは程度の差こそあれ、変形していた。やはり時間は必要なのだ。
沖縄から東京に戻り、自分のホームジムへ行くと、その空間がいつもと違って見えた。それは初めての海外旅行から戻った時の、日本の印象と似ていた。家に戻った安心感、ここで出会った多くの知人友人たち。いつものインストラクターさんたち。すべてが丸みを帯びていた。それは出稽古の副産物ともいえた。自分のホームジムに対して、今まで感じていなかった愛着が生まれていた。
クラスが終わると、沖縄での出稽古の感想を、数人に求められた。わたしは、クラスの後で連れて行ってもらったブラジル料理についての感想ばかりを口にして、それらは彼らがもともと聞きたかったことではないのに、わたしがやたらと熱心にディテールまで語るものだから、それはそれで面白かったらしい。ブラジルの格闘家はアサイーとフルーツのサラダを好むこと、パステルという大きなパイみたいな軽食を路上で食べる楽しさについてなどなど。
そうこう話していると、聞いている人も自分の出稽古体験について語ってくれる。それが順番に回るようにして、久留米での体験だったり、岐阜での体験だったり、ロンドンでの話だったりと、まるで柔術をめぐる出稽古旅行記のようになり、なんだかわくわくしてくるのだった。
そんな最中に、左耳の上がちょっと熱い気がして触れてみると、僅かだがはっきりと腫れているのがわかった。わたしは一瞬躊躇したが、思い切ってそこに居合わせた人の全てに触ってもらった。
「これって、カリフラワーの前兆ですか?」
わたしの耳を摘んだ人は、みな頷いた。
芽が出たのだ。
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
#4 裸を撮られる時に、百合は
#5 モルディブの泡
#6 WALKER
#7 あの日のジャブ
#8 夏休みよ永遠に
#9 ノーリプライ
#10 19, 17
#11 S池の恋人
#12 歩け歩けおじさん
#13 セルフビルド
#14 瀬戸の時間
#15 コロナウイルスと祈り
#16 コロナウイルスと祈り2
#17 ブロメリア
#18 サガリバナ
#19 武蔵関から上石神井へ
#20 岩波文庫と彼女
#21 大輔のホットドッグ
#22 北で手を振る人たち
#23 マスク越しの恋
#24 南極の石 日本の空
#25 縄文の初恋
#26 志織のキャップ
#27 岸を旅する人
#28 うなぎと蕎麦
#29 その部分の皮膚
#30 ZEN-は黒いのか
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある