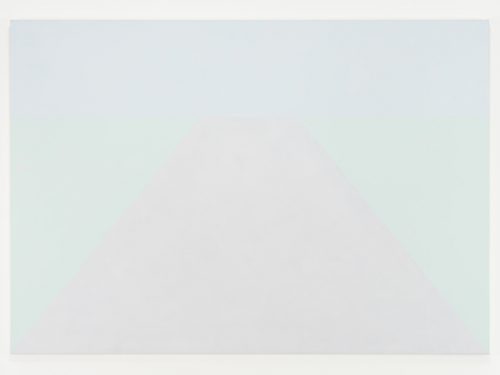守昌は、別荘内のカーブをゆっくりと下っていた。かつてトラックの運転手をしていたこともあるので、腕には自信がある。80を過ぎたとはいえ、まだ視力も確かで、反射神経もそこまで劣化していない、そんな自負が守昌にはあった。
息子の健一とは、元々うまが合わなかった。年齢からいって、息子と2人で旅をすることは、もうないだろう。せめて最後の旅くらいは、トラブル無しでいこうと、守昌はあらかじめ決めていた。そして、そのためにはなるべく顔を合わせないことが何よりだと理解していた。せっかく息子と水入らずなのだから、これまでのいろいろな思いを語り合いたいという気持ちもあったが、なにしろ気が合わないのだから、余計なことをせずに、穏便に済ませることを優先すると決めていた。
息子の健一は、中卒で無学の守昌にとって自慢の息子であった。小さい時から何をやらせても上手くこなし、東京の有名大学にもストレートで合格すると、さっさと家を出てバイトで自活しはじめたのだから、何も言うことのない息子のはずだった。もともと優しい子だったが、なんでも自分で出来てしまうので、親を全く頼りにせず、泣き言も甘えも一切なく、いつも一人で淡々と努力を重ねて前進していく姿に、我が子ながら、頼もしかった反面、何も必要とされていない冷えた距離を感じて寂しくもあった。そんなことを妻のスミ江に呟いたことが一度だけあるが、そんな悩みは贅沢だと一蹴された。
別荘は、自分たち夫婦で使うために買ったのだが、健一やまき子ら子供たちと一緒に過ごせる場所にしたいという期待もあった。春、夏、秋、と家族で集まり、数日を過ごす。これまで働きづくめで、子供たちにも十分な愛情を注ぐ余裕などなかった代わりに、別荘で孫も交えて、ゆっくり過ごし、余生の楽しみに加えたいと守昌は内心願っていたのだ。
だが、そんな人並みの幸せを得るのも、簡単ではなかった。
長女のまき子は、2度に渡る離婚など、自分の家庭のことで精一杯であり、最初の夫に譲った養育権のせいもあって、唯一の娘ともそう会うこともなく、教育費などはかからないのだが、家計はいつも逼迫していて、たまに親としての援助はするのだが、そのたびに、定期的な援助を逆に求められたりして、あまりいい関係ではなかった。別荘にも何度も誘ったのだが、ついにまき子は一度も訪れることもなかった。
健一は、最初は家族で何度か訪れたものの、あまり気に入らなかったようで、足遠くなっていて、年に一度くらいは数泊使っているようでもあった。
そんなわけで、息子や娘たちとゆっくり過ごすという夢は、あまりうまく進まずに、守昌とスミ江だけが、定期的に通っているだけだった。

守昌は、健一を一旦別荘に残し、街まで戻ってスーパーで夕食用に弁当でも買うつもりでいた。
昼食は、蕎麦を健一にご馳走になったので、夕食は家でのんびり食べたかったのだ。たしか健一は、寿司やうなぎをご馳走したいと言っていた気がするが、外食は気疲れするので、先手を打って弁当を買って来てしまおうと考えていた。
健一が幼い頃に、父である自分のテーブルマナーが悪すぎると指摘されて以来、なんとなく自分の食べ方の悪さが気になってしまった。もともと裕福ではない大家族に生まれ育った守昌は、そんなことを気にしたこともなかったが、就職したての祝いの席で、同僚にそのことを揶揄われて以来、ちょっとしたトラウマだったのだが、まさか自分の子供に指摘されるとは夢にも思わず、だが、それ以来自分でも情けないほどに萎縮してしまって、今でも息子と食事をする時は怖々と箸を伸ばしたり茶碗を持ったりしている。
守昌は、スーパーに着くと、適当に弁当をカゴに入れて行き、ついでにガソリンを満タンにして、再び別荘へと戻った。
健一は、古道具屋に売りにいくものを整えて、玄関にまとめている最中だった。
「弁当、夕飯用に買ってきたぞ」
朴訥にそう言って、スーパーの袋を差し出した守昌は、意外な表情で受け取る息子を尻目に、二階へとすたすたと上がっていった。
台所へ行き、なんとなく中身を確認した健一は、幕内弁当、チャーハン弁当、バナナ、栗饅頭2個、大福2個をシンク台に並べた。夕飯にしては、質素で量も少ないなと感じた健一は、さてどうしようかと考えた。
せっかく父が買ってきたものも無碍にできないし、かといってこれでは足りない。買い足しにいくべきか、それともこれを朝食用にして、父を外食に誘おうか迷っていると、守昌が2階から降りて来た。
「好きな方、選んでいいぞ。オレはどっちでもいいから。今日は移動で疲れたから、オレはさっさと食べて早めに寝るぞ」
父は、健一の目を見ずにそれだけを言って、再び2階に戻り始めた。
「ちょっと用があって、街に降りるから、その時にラーメンでも適当に食べてくるよ。せっかく買って来てもらって悪いけど、これ明日の朝にでもお父さん食べたら?」
「あ、そうか。そうだな、じゃあそうする」
守昌は、息子の言葉をしっかり聞いたのか怪しいほどに、機嫌の良さそうな高い声で、そう答えると2階へと消えた。

翌朝の、守昌の起床は早かった。
5時には目覚めてしまった。若い時から2度寝する習慣がなく、一旦目覚めると、すぐに布団から出て、昆虫のように決められたことをこなすように動き出すのだった。
隣の部屋で寝ていた健一は、父が片付けを始めているのに気づいたが、布団を頭から被って、しばらく布団に居座り続けた。
父は確か9時には出発すると言っていたっけ。となると、きっかり9時に出発することになるだろう。昔から父はなぜか時間にだけはきっちりしていた。バスの時間に合わせて、時間が余っていても、前倒しすることなく、最初に決めた時間通りに動くような人だった。健一は、それを父の生真面目さというよりも、小さな狂気のように感じて不気味であったことを思い出した。
健一は、6時頃に起床して一階へ降りると、すでに昨日の残りの弁当が食べ尽くされていて、父は坂を登ったり下ったりして、車へ荷物を運び出している作業の真っ只中だった。ベランダから健一が身を乗り出すと、ちょうどこちらに登ってくる父と目が合ったので、おはようと声をかけると、おう、という短い返事だった。上から見下ろすと、守昌の頭頂部の毛が僅かなことが露わになっていた。八十過ぎにしては元気な方だと思うが、やはりそれなりに相応な外見だなと健一は、労るような心持ちで、父を眺めた。
カシガリ山が綺麗だね、ベランダから正面に見える山の稜線を見やりつつ、居間に戻った父に、声をかけると、「ああ?名前なんか知らねえよ」という雑な答えが返って来て、健一は、その不機嫌さに、朝からの荷物の運び出しで疲れてイライラしているのだなと察した。
名前を知らないわけはない。その山がカシガリ山だとは守昌から教わったからだ。健一は、雑な言葉を発する時の、守昌の声や表情や態度がとても嫌いだったのだが、その時は顔に出さずにやり過ごした。
「明日は、あの山に登ってみようかな。いちどあの山からこっち側を眺めてみたいと思ってたから」
守昌は、健一の言葉を聞いていたのかどうか分からなかった。少なくとも何の返事もしなかった。興味がまったくなかったか、すでに自分の思考の世界に入ってしまっていたのだろう。現代で言うならコミュニケーション障害だとか、発達障害などという言葉で説明されるだろう個性を守昌に見ていた健一は、それでもいい気はしなかったが、9時までの辛抱だと自分に言い聞かせた。
9時になれば、守昌は、じゃあ行くな、と雑な口調で言い残して去っていくのだ。
早朝、2人は精力的に働いた。
出すべきものを、車へ運び尽くしてしまうと、別荘の譲渡者を想定して、掃除に取り掛かった。文字通り、黙々と作業をこなす守昌につられるようにして、健一も黙々と作業をした。ゴミ出し、掃き掃除、拭き掃除。それらを全て済ませてしまうと、ようやく2人でソファに深々と腰を下ろした。時刻は8時を少し過ぎていた。

「どうにか、片付いたね」
カシガリ山に視線を伸ばしながら、息子の健一がまず呟いた。
「ああ、これで、こことも終わりだ」
投げやりな口調だったので、やはり疲れたのだろうと健一が察した。こういう時は余計に喋らない方がいい時だ。
「本当は、お母さんが一緒だったら、よかったんだけどな。でも足が悪いからしょうがない。まあ、ここは十分楽しませてもらった。だから、最後に、お母さんも連れてきたかったんだけどな。まあ、しょうがない」
健一は、守昌の言葉が相変わらず投げやりなのが気になった。普通に喋れば、もっと友達もできただろうに、と思った。幼い頃から、父には友達が少ないことが気になっていた。他の家の父たちは、ゴルフやら飲み会やらで、友達付き合いが盛んなのに、父はいつも1人で気難しい時間を過ごしていた。そして、そんな父の姿が嫌でもあった。もっと普通に笑ったり、友達を家に連れて来て飲んだりしていてほしかった。そう健一はいまなお感じるのだった。もう少し社交性があったら、この人はきっと楽な人生を送れたのではないか。
「この家は、別荘地の一番ハズレにある。つまり一番自然に近い場所だ。そこがオレは気に入ってた。ほらすぐ裏は、山だろう?その山は、深い深い山奥へと繋がっていて、そこから時々鹿やら狐やらが降りてくる。いわば、ここは自然の入り口でな。そこがオレたちは気に入っていたんだ。玄関まで坂道を登ってくる価値があるってもんだ」
そう言うと、守昌は目を固く瞑って、腕を組んで動かなくなった。こうなったら、会話は強制終了である。守昌は自分が言いたいことを言い終えると、時々こうしてシャットアウト状態になるのだった。
「そうか、だったら明日カシガリ山からこっちを眺めて、確認しておくよ」
健一は、もはや誰にそれを言っているのか分からなかった。誰のための確認なのだろうか。
それから沈黙が続いた。長い長い30分だった。その沈黙に耐えきれずに、健一は最終確認をするような素振りで、各部屋を点検してまわった。そんなことをしながら、父と過ごす最後の濃密な時間になるかもしれないのに、はぐらかしてしまっていいのだろうか、という思いも過った。だが、あらためて何を語ればいいのだろう。そもそもこちらがそれなりの思いを持って、何かを伝えようとしても、それに応えてくれる父ではないだろう。おそらく雑な対応で終わる可能性が高い。そして、お互いに気まずい思いをすることになるのだ。それはやはり避けたい。
しかし、すでにやることがないのなら、さっさと別荘を去ればいいのに、なぜ父は時間調整をしているのだろう。
やがて9時になると、アラームをかけていたわけでもないのに、守昌は目を開けて、じゃあ、そろそろ行くかな、と呟いいて、さっさと身支度を整えると、玄関を開け、坂を降りて行き、車に乗り込み、エンジンをかけた。健一が、気をつけてと握手をするために手を差し出すと、守昌はその手を軽く握っただけで、何も言わずに走り去っていった。二十年以上通った別荘を振り返りもしなかったのは言うまでもない。
翌日、健一はカシガリ山に登った。登山口から往復3時間程度の簡単なルートだった。
山頂から東側の斜面を歩き、別荘地群をまもなく遠くに見つけ、望遠鏡を使って、どの家かを特定するのに少し時間を要した。だが、わけもなかった。
ベランダにはその朝干したばかりの洗濯物が揺れていた。間違いない、あの家だ。守昌が言ったように、確かに別荘地の外れにその家はあった。だが、それは裏山から続く大自然に面しているわけではなかった。別荘の裏山は小さな膨らみでしかなく、その先は別の会社が運営する隣の別荘地へと斜面が連なっているだけに過ぎなかった。
だが、この事実は父には伏せておこうと、息子は考えた。守昌は妻のスミ江と共に、大自然に接している場所で過ごす日々を楽しんだのだし、その裏山は隣の別荘地との緩衝地に過ぎなかったとしても、それは知る必要のない事実だ。
健一は、望遠鏡を覗きながら、その場にしばらく佇んだ。今、別のアングルから、彼らが慣れ親しんだ思い込みを眺めているのだ。僕たちが信じている永遠や愛すらも、別のアングルから眺めたら、思わぬ場所と接しているかもしれない。それこそ裏切りや嫉妬や、脆さなどと。
次にあの別荘を使う人々も、おそらくあのベランダからこのカシガリ山を何度となく繰り返し眺めるのだろう。そして、ある日、ある者は、この山のこの場所の辿りつくかもしれない。その人は、その時何を気づくのだろう。守昌が立たなかったこの場所で。
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
#4 裸を撮られる時に、百合は
#5 モルディブの泡
#6 WALKER
#7 あの日のジャブ
#8 夏休みよ永遠に
#9 ノーリプライ
#10 19, 17
#11 S池の恋人
#12 歩け歩けおじさん
#13 セルフビルド
#14 瀬戸の時間
#15 コロナウイルスと祈り
#16 コロナウイルスと祈り2
#17 ブロメリア
#18 サガリバナ
#19 武蔵関から上石神井へ
#20 岩波文庫と彼女
#21 大輔のホットドッグ
#22 北で手を振る人たち
#23 マスク越しの恋
#24 南極の石 日本の空
#25 縄文の初恋
#26 志織のキャップ
#27 岸を旅する人
#28 うなぎと蕎麦
#29 その部分の皮膚
#30 ZEN-は黒いのか
#31 ブラジリアン柔術
#32 貴様も猫である
#33 君の終わりのはじまり
#34 love is not tourism
#35 モンゴルペルシアネイティブアメリカン
#36 お金が増えるとしたら
#37 0歳の恋人20歳の声
#38 音なき世界
#39 イエローサーブ
#39 カシガリ山 前編
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある