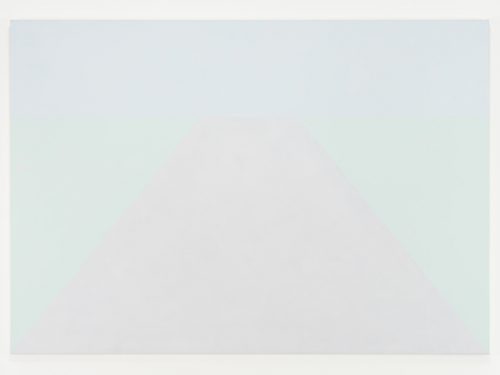消えてしまうもの、がある。
たとえば、命。たとえば、金。たとえば、恋。結構大きくて、存在感のあるものでも、消えてしまう。不思議といえば不思議だが、当たり前だと言えばそうでしかない。
むしろ、消えてしまわないもの、永遠、普遍、そんなものがあるのだろうか?お日様だっていつかは消滅すると科学者は断定するし、地球なんてのは宇宙生命の尺度からしたら瞬きのようなもの、らしい。本当かどうかなんて分からないけれど、多分本当だと私の中の何かが実感している。
子供の頃、美術の授業中、教科書の中に「消失点」という言葉を見つけた。今でも覚えているのだけれど、わたしは消失点という言葉そのもの、概念、に衝撃を受けた。なんと恐ろしい言葉であり、物事の捉え方なのだろうという衝撃の残響は今でもけっして静かではない音色で、私の胸の内側をえぐっている。
消えてしまう。それはいったいどういうことか。わたしは教科書の中に示された消失点の一点を見つめながら、今でもそのアンサーを言いあぐねている。
消えてしまうものは、なにも巨きなものだけではない。財布だって、スマホだって、消失するし、さっきまでそこにあったプラスドライバーが消えてしまうこともある。
目に見えるものだけでなく、昔の恋人の下の名前もほとんどが消失してしまっている。2つ前の住所とか、最後の固定電話の番号とか、あの時はそれなりに大事だった何かが、現在と遮断されているのは、不可解だ。
そういう随所にある消失点のことを思うと、何事にもこだわる気が萎えるのはしかたないことだ。スニーカーの型とか製造地などを慎重に選んでも、いずれはどうでもいいことになってしまうし、例をあげればきりがないのだが、結局霧散する全てに適度にナイスに付き合うのが、まあ無理がないのかな、と思っている。
答えを探すな、答えはいずれ現れる、ということだ。
そんな前フリを経て、僕が言いたいのは、今週はバターナイフが見つからなかった、ということ。
朝食は、大きく和食か洋食のどちらかで、そのサイクルは1週間から10日で入れ替わることが常で、今週は洋食だった。ホームベイカリーで焼いた食パンのトーストにコーヒー、少しのサラダ、といったのがルーティンだが、2日に1度はバターナイフが見つからずに、小さいスプーンや大きなナイフで代用するのだが、やはりバターを塗るにはバターナイフが最適なのは言うまでもなく、その小さな綻びが、1日のスタートに小さくはないノイズをもたらすのが、不満であった。
もちろん、そんなことに気を取られない大きく朗らかな人格を作るのがいいのだが、性格っていうのはそういうもんじゃない。数十年の歳月と経緯は軽んじられないし、おしゃべりなおばさんが静かになるのには、もう半世紀必要なのと同じくらい難しい。
それはさておき、バターナイフというのは、箸のように家にたくさんストックしておくべきではないと僕は思うから、予備を考えはしない。たくさんでなくても2本はあっていいのではないか、と指摘を受けるだろうが、僕はそれをよしとしない頑固さもあって、バターナイフというのは、家庭に1本だけあるのが、凛々しく美しいし、それがバターナイフへの経緯の示し方というものだ。なんというか、表札は1枚でいいという理屈を僕はバターナイフにも当て嵌めたい。それはこの国の、この文化の一夫一妻と同じくらいに、倫理的な面すら思わせることなのだ。
で、この話は長くなったので、もうおしまいなのだが、僕が最近はまっているのは、「日常」だ。どういうことかというと、「日常」の微細を観察することにはまっている。それがもたらす効果とか結果にコミットすることもなく、現在進行形の日々の微細から機微を紐解くだけの行為を遊びと捉え、それに夢中になっている。
それはモノの観察でもあり、物事の観察でもある。可視と不可視の両方に向けられる観察遊びは、実に知的で、時には高尚でもあり、そして大概無意味な馬鹿馬鹿しいものだ。
生産性は0であり、鶏を穴が開くほど観察するが、それを描かない若冲のようでもあり、とある人間関係をニュートラルな場所から内面の襞を余すところなく受け取りながら何も書かない三島由紀夫のようでもあり、つまり表現という場所からも遠く、ただただ観察するのみという立場だ。
どちらかと言えば求道者的とも言えるが、けっして第3者を想定していないので、宗教者からも程遠い。無機的な宇宙空間で、とある軌道を周回するだけの衛星的な存在行為が、僕のはまっている観察なのだろう。
では、いったいどんな感じでそれが行われているか例をあげよう。
先日、とある私鉄沿線のカフェに言った。打ち合わせ場所として指定されたその店は、季節の新鮮フルーツを贅沢に使用したスイーツなるものが売りで、僕は様々なパフェにも惹かれたが、値頃なフルーツサンドのハーフを注文した。
店員の心あらずな接客と共にレジ前のショーケースから運ばれてきたそれは、ごく普通のフルーツサンドに見えた。僕は打ち合わせの相手がトイレに立っている間に、その物体をしげしげといつものごとく観察し始めた。これは、「さあ、今から観察をはじめるぞっ」と明確な意識のスイッチが入るわけでもなく、シームレスでスムースな心の動きである。
観察とは、まず違和感の立ち上がりから始まることが多い。
昼前の休日、裏通りのカフェに奥まった席には入り口からの自然光と、天井からの蛍光灯の照明というミックス光によってその存在が可視化されている。だが、その自然界にはないものが目の前に出現しているという不自然さに意識のフックを掛けたりはせずに、その色や質感、あれば匂いをただ自分の感覚器を通して受け入れる。固有名詞や一般名詞も外して、ただの物体としての特質を観察する。
パンの木目、クリームの粘り、フルーツの水分などをじっくりと観察する。うまそう、とか、いい匂い、とか、甘いのかな?などという思考は極力外し、ただひたすらに見つめるのだ。そのうちにちょっとした面白いことが起こる。
それは境界の消失である。
まあ、それだけで十分伝わるはずだが、蛇足説明すると、観察者と非観察者の境界が薄れ、やがて曖昧になり、自分がシャインマスカットだったり、生クリームだったり、パンであったり、フルーツサンドという総体にすり替わってしまう感覚が訪れる。これがとても愉しい。まさに一体感、小さなワンネスである。じっと観察しているだけで、マジックマッシュールームもペヨーテも要らずに、何かがすうっと消えて観察していたものと一体となった自分がふわりとある。なんという愉しさよ。
ただ、注意しなくてはいけないのは、この愉しさを目的としてしまうと、観察の純度が鈍る。これは期待せずに転がり込んできなものだと、受け流すべきで、それにこだわると執着になって心が澱む。心が澱むとそれは観察ではなくなってしまう。

まあ、こんな感じで僕は日常の観察にはまっているのだが、先日山手線外回りに乗っていると、僕の座る反対側から三十代半ばの男が僕のことをじっと見ているのに気づいた。その無機質な視線の質から、彼が僕と同じような観察人であることを瞬時に悟った。そしてこの僕が彼の観察の対象になっていることに戸惑いつつも、僕も彼を観察することになっていた。
向かい側の彼は、老けた学生のような雰囲気であった。グレーのパーカーはヘビーウェイトな感じで、チノパンは履きこんであるようだった。黒いベースボールキャップはPの文字のみで、メジャーリーグのものだろう。白いエアフォース1は、割と真新しい。まあどこにでもいるような服装であり、ぽっちゃりとした体型のようで、顔の作りは地味で目は小さく、気弱のようにも見えなくもない。そんな感じだった。
僕は彼の目を見つめるのは避け、視線が合わないように、全体をぼんやりと見つめ、時々服のリブだったりスニーカーの紐にだったりと、細部に集中することもあった。
その日は上野に行くつもりだったのだが、結局その男の観察から抜け出せずに、上野を過ぎてもそのまま座り続けていた。
向かい側の彼はいっこうに下車せずに、僕の観察を続けているようだった。彼は僕の目、もしくは顔をずっと見続けているようだった。昼間の空いている時間帯だったから、僕たち2人を遮る立客もなく、ずっと指しの状態で向かい合うという特異な時がだらだらと流れ続けた。
一般的には、これは妙で、おそらく異常なことかもしれない。赤の他人が見つめ合っているのだから。ただ、僕らは観察人という共通した認識があるから、ただお互いの邪魔しないようにと気遣う余裕すらあった。少なくとも僕はそうだった。
やがて僕らはそんな観察合戦をはじめて再び上野へと到着した。山手線を一周してしまったのだ。向かい側の彼は僕が目白駅から乗車した時には既にそこにいたわけだから、さらに長い時間座っていることになる。
僕は、その休日の予定は上野の科学技術館に行くことだけだったから、彼が下車するまでこのままでいいなという気になっていた。こういうチャンスは滅多にない。1人の人をずっと観察できるなんて、なかなか無いことだ。
その後も、僕は彼の観察を続けるのだが、そのうちに彼のことを見ているのか、彼の身体を覆う服や靴を見ているのかの区別がわからなくなってきた。フォーカスしている対象が彼本人そのものとそれを覆う物体との間で揺れているのであった。実はそういうことはよくあることで、ミカンの皮と中身のどちらかを観察しているのかという問いである。
こういう時は、必ず思考が前面に出ようとしている時で、純粋な観察に思考という邪魔が入ってくる瞬間である。なので、ここは深追いせずに、そういう思考を遠ざけるために問いすらも無化する。ただ観察だけを続けること。分析もせずに、ただの入力に徹すること。
やがて僕はトイレに行きたくなり、遂に下車することにした。僕が席を立つと、なんと彼もほぼ同時に立ち上がった。その時には、さすがに僕から視線を外したようだが、ちょうどホームに降りる時に肩と肩とが擦れた。それに対して詫びるというよりも、これまでの共有した時間へのお礼をするように、お互いに小さな会釈を交わした。
僕が階段を登り始めると、彼は僕から意図的に離れるようとしたのか、登る場所とタイミングをずらした。名前も知らない男だし、きっとこれから会うこともないだろう。僕は階段を上がり、トイレを済まし、せっかくだからと改札を出て、生まれて初めて駒込の駅前に立った。
そこからなんとなく北へと歩き、やがて飛鳥山公園に行き着いた。ずっと昔の彼女と桜を見にきたことを思い出した。あの時、桜が見たかったのは僕だけで、彼女はずっと興味なさそうにしていたことを思い出した。
もう少し歩くと王子駅だった。王子といえば、KOHHだよな、と呟いて周囲を見渡した。交番の前に差し掛かり、何気なく中を覗くと、帽子の位置を整えている警察官と目が合った。おそらく、いや、間違いなく、電車の中で観察し合った男だった。
僕は驚きのあまり、交番の前で、その男を見つめたまま立ち尽くしてしまった。その男は落ち着き払ったゆっくりとした足取りで、交番から出てきて僕の前に立った。そして、ちいさく数度ゆっくりと頷くと、口を開いた。子供のような高い声だった。
「あなたのしていることは、ある種の窃盗ですよ。今後気をつけてください」
それだけを伝えると、男は再び数度うなずいて、無表情のままくるりと背を向けて交番に戻っていった。
僕は、王子駅には行かずに、来た道をなぞるように引き返し、駒込駅へと向かった。
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
#4 裸を撮られる時に、百合は
#5 モルディブの泡
#6 WALKER
#7 あの日のジャブ
#8 夏休みよ永遠に
#9 ノーリプライ
#10 19, 17
#11 S池の恋人
#12 歩け歩けおじさん
#13 セルフビルド
#14 瀬戸の時間
#15 コロナウイルスと祈り
#16 コロナウイルスと祈り2
#17 ブロメリア
#18 サガリバナ
#19 武蔵関から上石神井へ
#20 岩波文庫と彼女
#21 大輔のホットドッグ
#22 北で手を振る人たち
#23 マスク越しの恋
#24 南極の石 日本の空
#25 縄文の初恋
#26 志織のキャップ
#27 岸を旅する人
#28 うなぎと蕎麦
#29 その部分の皮膚
#30 ZEN-は黒いのか
#31 ブラジリアン柔術
#32 貴様も猫である
#33 君の終わりのはじまり
#34 love is not tourism
#35 モンゴルペルシアネイティブアメリカン
#36 お金が増えるとしたら
#37 0歳の恋人20歳の声
#38 音なき世界
#39 イエローサーブ
#39 カシガリ山 前編
#40 カシガリ山 後編
#41 すずへの旅
#42 イッセイミヤケ
#43 浮遊する僕らは
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある。